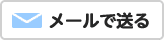「進撃の巨人」エレン・イェーガー役や「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役で知られ、2024年にデビュー20周年を迎えた声優・梶裕貴。今年は40歳という節目の年となる。その梶が現在、力を注いでいるのがキャラクタープロジェクト「そよぎフラクタル」。これは梶の声をもとにした音声合成ソフト「梵そよぎ」を軸に、プロアマを問わず“ものづくり”の場を広げていくことを目指したプロジェクトだ。
梶はこのプロジェクトで自ら指揮を執り、ソフトの発売のみならず、クリエイターとのコラボレーションによる動画や楽曲、マンガ制作を展開。6月30日には、ライブイベント「そよぎEXPO」と、それに向けたクラウドファンディングの開催を発表するなど、プロデューサーとして精力的に活動している。
声優界のトップランナーと言えるキャリアを歩んできた中、節目の年を迎え、声優・梶裕貴はどこへ向かおうとしているのか。「そよぎフラクタル」にかける思いと、自らの未来について、アニメ評論家の藤津亮太が紐解く。
取材・文 / 藤津亮太 撮影 / 番正しおり ヘアメイク / 小田切亜衣(emu Inc.) スタイリング / ホカリキュウ
「そよぎフラクタル」とは
梶裕貴の声をもとにした音声合成ソフト「梵そよぎ(そよぎそよぎ)」を軸に展開するキャラクタープロジェクト。幾何学模様(=フラクタル)の図形のように「同じ理想を持ったクリエイターが集まって作品を生み出していった結果、俯瞰で見てみると、これまでにない全く新しい形を織りなしているはず」という願いを込めて命名された。「梵そよぎ」のキャラクターデザインは、アニメーター・イラストレーターの米山舞。また作曲家の澤野弘之がメインテーマを担当している。
コロナ禍の取り組みから、みんなが参加できる場所づくりへ
──梶さんは2021年に出された書籍「梶裕貴 対談集 えん」の中で、後半「絶望」や「限界」といった言葉でそのときのご自身の心情を語っています。2020年前後に感じていたそういった重たい気持ちが、その後、自ら「そよぎフラクタル」を始める原動力へと昇華されたのではないか……と感じたのですが、どうでしょうか。
うーん……。つながっているとは思います。でも意識的に、というか、直線的につながっているというわけでもないです。結果的にそうなった、という感じでしょうか。対談集の「えん」には、2020年前後に考えていたこと、感じていたことが全部詰まっていて、もちろん嘘ではないし、決して現在と断絶しているわけでもない。それは間違いないことです。でも今は、それらを経て、次のフェーズに入ったような感覚で仕事をしていますね。
──6月30日に「そよぎEXPO」など新しい展開が発表されましたが、そもそも「そよぎフラクタル」の発想はどうやって生まれたのか。そこから改めて教えてください。
コロナ禍を受けてのステイホーム期間に、改めて「自分自身の手でゼロから創って届ける」ということをしたい、していかなければいけないと感じ、積極的に朗読劇の企画制作を行いました。ただ、そのときは最終的に目標にしていた“公演”という形にまでたどり着くことはできなかったんです。やはり、資金面やコネクションなど、自分1人でできることには限界があったんですよね。そこで逆説的に「もっとみんなが気軽に参加できる、広がりがあるものを目指すべきだ」という発想にいたって。
──“もの”を作るというより、“もの”を作れる場所を作ろうという方向にシフトしたんですね。
そうです。とはいえ、どうしても"声"にはこだわりたくて。やっぱり私は何をするにしても、あくまで声優でありたい人間ですから。それを誇りに思っていますし、同時に責任も感じているので……で!(笑)そこで結びついたのが、自分の声をもとにした音声合成ソフト。みんながそれを楽しみながら利用してくれれば、自然発生的にいろんな作品が生まれていくだろうし、それに伴ったムーブメントも誕生していくんじゃないかと思ったんです。自分1人じゃ作れないものも、みんなでなら作っていけるんじゃないかと。
才能があるのにあがいている人に少しでもチャンスを
──そうしてクラウドファンディングを経て、昨年11月には音声合成ソフト「梵そよぎ」がリリースされました。「そよぎフラクタル」というプロジェクトが個性的なのは、音声合成ソフトを出すことがゴールではなく、そこがスタート地点ということです。ソフトのリリースと前後してコラボカフェが開催され、年が明けると1月から2月にかけては、小説、マンガ、展覧会とさまざまなコラボレーションが一気に展開されました。
整理してみると、確かにそういう時系列ですね。もちろん音声合成ソフト制作からスタートさせていましたが、どうしても完成までには時間がかかるので。加えて、仕込み時期も準備期間もバラバラなので、今ご指摘いただいて「そう言われれば、そうだったかな?」みたいな感覚ですが(笑)。年明けにコラボレーションが続いたのは偶然でありつつ、そうした露出が連続したのはプラスだったのかなと感じています。
──「そよぎフラクタル」は、梶さん自身がプロデュースし、マネジメントもされているんですよね。
そうなんです。まさに、自分自身の手でゼロから進めている企画で。なので、普段は事務所のマネージャーさんやデスクさんがやってくださっているような事務作業も、自ら行います。昨日も夜中までメールのやり取りをしていました(笑)。もちろん大変さもありますが、それ以上に楽しいですし、やりがいを感じますね。
──“ひとりメディアミックス”といった状況なんですね。例えば2月に雑誌掲載されたコミカライズ「性悪男とAIのセオリー」は、「進撃の巨人」の諫山創先生がネームを担当しました。これはどういう経緯で実現したのでしょうか?
自分の声優歴20年のうち「進撃の巨人」が、その半分の10年を占めていて。まさに自分の人生を変えてくれた大切な作品と言えます。なのでコミカライズを展開するチャンスがあるなら、そんな「進撃の巨人」の原作者である諫山先生に、真っ先にお願いしたいと考えていました。TVアニメ完結後、諫山先生の出身地である大分県日田市での植樹祭でご一緒したときに、「コミカライズをお願いできませんか」と直接ご相談し、ありがたいことに諫山先生からはご快諾いただけて。その後、講談社さんにご挨拶させていただき、数々の打ち合わせを経て実現にいたりました。
──「梵そよぎ」のコンセプトは「“声”を手に入れたことでデジタル世界に誕生した、もう1人の梶裕貴」です。そのうえで、“自由を手にしているはずなのに不自由な現実の人物(梶裕貴)”と“不自由でありながら自由を手に入れたデジタル世界の梵そよぎ”の対照関係が世界観の軸に設定されています。マンガ「性悪男とAIのセオリー」は、そのコンセプトがしっかりと咀嚼したうえで描かれていました。このあたりはどんなふうに諫山先生と打ち合わせをしたのでしょうか?
諫山先生をはじめ、本プロジェクトに関わってくださるクリエイターの方々には、「梵そよぎ」や「そよぎフラクタル」についてのコンセプトと、そこに込めた思いをまとめた資料をお渡ししています。それは6月30日に発表したEXPOにご参加くださる皆さんも同様。そのうえで「そこから着想されたイメージで自由に創作してください」とご依頼しています。なので私自身、どういった作品が仕上がってくるのかまったく想像ができないですし、誰よりその化学変化を楽しみにしている気がしますね。そして、それこそが「みんなで作っていく」ということだろうと。
──「そよぎフラクタル」のコンセプトを踏まえたうえで、作り手のクリエイティビティは自由に発揮してもらいたい、と。
その通りです。例えば「性悪男とAIのセオリー」は、「そよぎフラクタル」の作品でありながら、完全なる諫山イズムによって構成されています。「進撃の巨人」と世界観は違えど、そこからは、まごうことなきご本人の魂が感じられました。それは冲方丁先生に書き下ろしていただいた短編小説「君とそよぎと終末世界を」も同じ。作家さんそれぞれの解釈はあれど、「そよぎフラクタル」の理念からズレていない、ブレていないんです。そんな諸々を含めて、改めて0を1にする創作活動、そして、それを形にするクリエイターさんたちの凄さを実感する機会にもなりました。
──「性悪男とAIのセオリー」は、作画を熨斗上カイさんが担当しています。熨斗上先生は「『そよぎフラクタル』作画担当者募集コンテスト」で抜擢された方です。このコンテストも「そよぎフラクタル」ならではのユニークな試みでした。
私自身、10代で声優業界に飛び込んだものの、いわゆる下積み時代には、チャンスをうまく掴めずに苦しんだ経験があります。だからこそ、才能があるのにあがいているクリエイターがいるとすれば、そんな人たちに少しでも夢と希望を持ってもらいたいという気持ちが強くあって。なのでコミカライズの際は、プロアマ問わず参加できるコンテストを行って、その中から作画担当の方を決めることにしたんです。その後開催した「そよぎフラクタル 創作コンクール」も同じ思いから生まれたもの。参加してくださった方々のリアクションを見ていると、やはり企画してよかったなと感じています。
「そよぎフラクタル」は自分の人生の柱の1つ
──“みんなで作る”ということの中に“新たな才能に光を当てる”という側面もあるわけですね。それで言うと、2月に行われた東京造形大学とコラボレーションした展覧会「梵そよぎと未来のクリエイター展」も、まさにこれから世に出る才能に光を当てる企画でした。
はい。これまでやってきた声優としての活動、そこで生まれたご縁というものがこれでもかとつながって……少し怖いくらいでした(笑)。「そよぎフラクタル」のロゴデザインを担当してくださったデザイナーの海士智也さんは、私の主演作「キズナイーバー」のタイトルロゴや、私がプロデュースしたアパレルブランド「en.365° エンサンビャクロクジュウゴド」のロゴも担当してくださっていた方なのですが、デザイナー業の傍ら、東京造形大学で教授も務められていて。打ち合わせを続ける中、プロジェクトのコンセプトを大変面白がってくださっていたんです。
──そこで造形大学とつながったんですね。
私が生み出した「梵そよぎ」を中心に、プロアマを問わずいろんな人がアクションを起こす。そしてそのリアクションを受けて、私が新しい発想でまた何かを作っていくという、クリエイティブが拡散と収縮を繰り返していくサイクルに着目してくださったんです。それは美大という教育の場にも活かせるんじゃないかと。その後、無事に開催が決まってからも、どのように参加者を募集し、どうやって展覧会を開くのかなど、海士さんと一緒に1つひとつ決めていきました。学生さんにとっても、すでに世にある何かを題材にするのではなく、プロジェクトが立ち上がっていく過程を感じながら、ゼロから一緒に制作を行えるという機会はなかなかないので、そこに価値があると考えてくださっていたようです。
──学生の作品に触れてみていかがでしたか?
参加したからといって単位がもらえる授業ではないので、あくまで有志という形だったのですが、にもかかわらずかなりの生徒さんがエントリーしてくださって驚きましたね。とてもうれしかったです。ネット上の二次創作だと、どうしてもイラストや音楽での表現が中心になってしまいがちですが、そういった枠にとどまらない作品……例えばアパレルやオブジェのような作品もたくさんあって、その可能性の幅が面白かったですね。1つのプロジェクト、1つのコンセプトに対して、ここまで自由に受け取り、形にできる才能があるんだなと感動しました。実際に私も現地に赴き、先生方と生徒さんと一緒に講評会をしたのがいい思い出です。全部で200点以上の参加作品がありましたが、その1つひとつにコメントを用意して。
──それはすごいです。
あ、別に頼まれたわけじゃなく勝手になんですけどね(笑)。全部書くのに5時間くらいかかりましたかね。でも一生懸命参加してくれた以上、私もちゃんと向き合って、直接リアクションを届けたかったので。コラボを終えた今、まさに「そよぎフラクタル」を象徴するような素敵な企画だったなと感じているので、ぜひいつかまたやりたいなと考えています。
──コラボカフェを開催したときも、営業中に自ら足を運んでいたそうですね。
感謝の気持ちが第一というのはもちろんのこと、コラボカフェの場合は、お客様がどんなところに興味や価値を感じてくださっているのかというリアルを肌で感じたくて、暇さえあれば立ち寄るようにしていました。何を楽しんでくださっているのか、どうすればプロジェクトの方向性が正しく伝わるのか、そういったことをお客様から直接感じ取ることに意味があるだろうと考えたんです。とても勉強になりましたね。それを踏まえたうえで、これからもっと多くの皆さんに、もっとストレートな方法で「そよぎフラクタル」を知っていただく機会を設ける必要があるなと感じたんです。
まさに。今後の自分の人生を考えたときに、絶対に揺るがない3本の柱を挙げるとすれば、1つはもちろん「声優」。もう1つは「家族」。そして、最後の1つが「そよぎフラクタル」なんです。それぐらい本プロジェクトは、自分にとって大きな存在。決して比喩表現でなく、人生を懸けて向き合っていくライフワークと断言できます。
──梶さんをそこまで「そよぎフラクタル」に向かわせるその根底にあるのはなんでしょうか? 後半は、そのあたりを聞かせてください。
(後編に続く)
梶裕貴(カジユウキ)
1985年9月3日生まれ、東京都出身。2004年に声優デビューし、アニメ、ゲーム、ナレーション、洋画吹き替え、舞台などで活躍。代表作にアニメ「進撃の巨人」のエレン・イェーガー役、「七つの大罪」のメリオダス役、「ワールドトリガー」の三雲修役、「僕のヒーローアカデミア」の轟焦凍役ほか多数。
(c)梶裕貴/そよぎフラクタル
(コミックナタリー)
 ERR_MNG
ERR_MNG