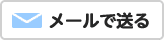アニメーションの作画をテーマにしたイベント「井上俊之の作画殿堂」第5回が、去る7月20日に東京・立川シネマシティのシネマ・ツーで開催された。今回は「安藤雅司と語る東映長篇から続く作画世界」と題し、「わんぱく王子の大蛇退治」を主な題材として取り上げながら、アニメーターの井上俊之と安藤雅司が作画についてのトークを繰り広げた。
「わんぱく王子の大蛇退治」から見る月岡貞夫の功績
東映動画(現・東映アニメーション)の長編第6作として、1963年に公開された「わんぱく王子の大蛇退治」。今回同作を取り上げた理由について、井上は戦前にアニメーション制作を行っていた日動の功績から、東映動画が1958年に制作した「白蛇伝」などの流れを軽くさらいつつ、「わんぱく王子の大蛇退治」が戦後の日本のアニメーションの技術がある程度のレベルに達した、再スタートの起点として位置づけできる作品であると説明した。シネマシティではイベントと連動して同作の上映も行われ、劇場のスクリーンで鑑賞するのは井上と安藤ともに初めてだったという。“わんぱく王子”ことスサノオが母イザナミを亡くしたことを受け入れられないさまが、虚実が入り混じったように表現される場面など、今観ても面白く感じられるポイントを語り合った。
また「わんぱく王子の大蛇退治」での大きな見どころが、約15分にわたって繰り広げられる、八叉の大蛇を退治するシーン。「長いですよね(笑)」「十六叉だったらどうするつもりだったのか(笑)」と2人も笑ってしまうほど、異例の長尺で展開されるシーンだが、これを手がけたアニメーターの大塚康生と月岡貞夫の功績に話題は移っていく。井上は「“大塚康夫ショー”のような素晴らしいシーン。クレジット上は動画だけど、大蛇退治のシーンの1/3ほどは原画を月岡さんが描いている。プロのアニメーターになってから観ても、どちらが描いたのかわからない」と、当時20代前半ながら大塚と肩を並べていた月岡の「アニメーションの申し子」ぶりを紹介した。
また日本大学芸術学部在籍時に月岡の授業を受けていた安藤。「いわゆる動体視力的なもの、見て、つかまえる感性がすごい」とリスペクトを込めて語る。月岡が富士通のCMとして制作した「タッチおじさん」のアニメーションを取り上げ、「どこかすごくリアリティがあって、だけどマンガ的な誇張が入りこんでいる、その塩梅がすごい」とその卓越性を伝えた。
「漫画映画」のルックの魅力
宮崎駿監督のもと、スタジオジブリ作品の作画監督を多数務めてきた安藤。森康二が手がけた「わんぱく王子の大蛇退治」のキャラクター設定について、宮崎が「衝撃を受けた」と話していたというエピソードなど、貴重な話も聞くことができた。また演出を高畑勲が、場面設定・レイアウトを宮崎駿が手がけた「母をたずねて三千里」についての話題では、「高畑さんの演出力はもちろんすごいんですが、そこにたまたま宮崎さんがいた、というのが奇跡ですよね。ただ移動するだけとも言えるような内容でも緊張感を持って観られるのは、宮崎さんのレイアウトの凄さ」と語った。
イベントの後半では、アニメーションが「漫画映画」と呼ばれていた時代のルックの魅力についての話題が展開された。井上は1971年の東映動画作品「どうぶつ宝島」のような作画が自身の原点であり、いつかやってみたいという憧れがあるという。また「漫画映画」時代のルックを復興したい理由の1つとして、今のアニメーションが「重労働だし、過剰」であるとも語る。「当時はもちろん時間も人材もない中で、最高のものをと思って作った結果だと思うけど、その物語を表現するのに最適なルック、最適なレイアウト、最適なアニメーションをされている。今はいろんな意味でアンバランスだと思うんです。もっともっと削ぎ落していくべき」と話すと、安藤も「ある意味、要領のいい芝居の組み立て方ですよね。絵を分解して細かく描くことに、今は固執しすぎている。ちょっとした連続性に細かいニュアンスが読み取れるアニメーション、あれは取り戻したいですよね」と同意した。
(コミックナタリー)
 ERR_MNG
ERR_MNG