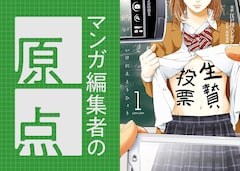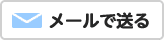マンガ家が作品を発表するのに、経験豊富なマンガ編集者の存在は重要だ。しかし誰にでも“初めて”がある。ヒット作を輩出してきた優秀な編集者も、成功だけではない経験を経ているはず。名作を生み出す売れっ子編集者が、最初にどんな連載作品を手がけたのか──いわば「担当デビュー作」について当時を振り返りながら語ってもらい、マンガ家と編集者の関係や、編集者が作品に及ぼす影響などに迫る連載シリーズだ。
今回は、本連載史上、最も“黒い”編集者──もとい、アングラな世界をテーマにした作品やダークな作品の編集を得意とする、講談社の若きエース編集者・白木英美氏に迫る。ヤンマガを牽引する人気作「満州アヘンスクワッド」「ねずみの初恋」「邪神の弁当屋さん」などを担当し、2024年に始動したヤングマガジンのYouTubeチャンネル「ヤンマガ日常ch」では、「白木氏の超多忙な1日」に密着した動画も公開されるなど、名実ともに同誌の“顔”である白木氏。ヤンマガのカラーをさらに黒く塗り込めていく精力的な編集者は、これまでどんな人生を送り、どんな信念を持つのか──。
オンラインで行われたインタビューであり、筆者と白木氏は初対面だったが、そうとは思えないほど盛り上がった取材。回答がいちいち面白く、こちらからもツッコミを入れたくなるラリーの応酬。一朝一夕で身につくものではない、天性の磁力。いつまでも話していたくなるような不思議な魅力に富んだ白木氏のロングインタビューをお届けする。
取材・文 / 的場容子
“性癖を歪められた”音無響子という女
少年・白木氏が育ったのは茨城県。最寄りの駅まで徒歩1時間くらいかかる“山の上”で暮らしていた。
「サッカー少年団に入っていて、絵を描くことも好きな子供でした。母がマンガ好きだったので、家の本棚はマンガで埋め尽くされていて、そこから取って読む。そんな感じでマンガ好きになりました。小学校の卒業アルバムの『将来の夢』欄には『マンガ家』と書いてありましたね。
母が高橋留美子先生のファンだった影響で、僕も『らんま1/2』や『めぞん一刻』、あとは、『動物のお医者さん』(佐々木倫子)なんかを読んでいて。それ以外で好きだったのは、父が読んでいた『栄光なき天才たち』(森田信吾)。父の影響で『火の鳥』(手塚治虫)や『美味しんぼ』(原作:雁屋哲、作画:花咲アキラ)も読んでいました。自分でも『サイコメトラーEIJI』(原作:安童夕馬、漫画:朝基まさし)とか『GTO』(藤沢とおる)を本棚に追加していきました」
女性向けマンガに青年マンガと垣根なく読んでいった。年齢相応にジャンプも好きだったという。人生で一番影響受けたマンガは「『めぞん一刻』か『SLAM DUNK』(井上雄彦)」。
「意外だと言われるんですが、僕、会社に入るまではヤンマガとは無縁の人間でした。学生時代はラブコメとかスポーツマンガが好きで、特に好きだったのが『めぞん一刻』。先生の描く女の子がかわいいと思いつつ、音無響子さんに性癖を歪められましたね。まさに高嶺の花で、五代くんに感情移入して読んでいました。僕はすれ違いが起きるラブコメがすごく好きなんですけど、その原点だと思います」
名作、「めぞん一刻」。一刻館に下宿する貧乏浪人生・五代裕作のもとに、新しい管理人である音無響子がやって来る。恋心をつのらせる五代だが、響子の心を占めるのは、結婚半年でこの世を去った夫への思いで──。ビッグコミックスピリッツ創刊号(小学館)である1980年11月号から連載を開始し、それから半世紀(!)経とうかという令和の現在でも、多くの人の胸に残り続ける、高橋の初期代表作であり、青春ラブコメの金字塔的作品だ。
「あくまで個人的な意見ですが、僕は今のラブコメって優しすぎると思っている。すでに付き合っている状態から、その愛を深めていく、みたいなパターンも多くて、すれ違いも起こらない。でも僕は『すれ違ってほしい!』とずっと思っていて(笑)。『恋愛ってこんなにつらいことも起こるんだ……!』みたいな、きつい恋愛を見ていたいんです。『めぞん一刻』はもちろん、『I"s』(桂正和)に夢中になっていたことも起因している気がします(笑)」
甘さではもの足らず、恋愛のもたらす苦しさ、しんどさが欲しい──。いや、むしろつらさが恋愛を一層甘く、切なくする。議論を先取りすると、まさにその指向が、大ヒット作「ねずみの初恋」につながっていったのかもしれない。
さて、マンガ家を夢見る白木少年のマンガ家としての理想は、「とにかく絵がカッコいい」という理由で井上雄彦だった。目指すのをやめたのは、1つ上の兄の影響があったという。いわく、兄は「僕から見ると天才。サッカー部で運動神経が良くて、イケメンでヤンキーだけど、成績は学年で一番」という、まさにマンガの主人公みたいな存在。
「そのマンガの主人公の下に、僕が平々凡々に生まれてきちゃった。だから子供のときに、『自分は才能がある側じゃないな』ってどこかで思っちゃったんですよね。多分、自分は井上先生みたいな天才にはなれないだろうという気持ちがあって、ふと諦めたのかなと」
少し切なくも聞こえる話だが、そうした思いや経験は、今の白木氏が持つ美点や魅力につながっているように思える。兄とは今もとても仲が良いという。マンガ家を目指すのをやめた白木氏が情熱を傾けたのは、部活だった。
「僕は、ひたすらスポーツをやっていた人間なんです。サッカー、バスケ、ハンドボール、大学でラグビー。『SLAM DUNK』を読んで部活っていいなと思ったし、編集者になりたいと思ったのも、やっぱりスポーツマンガに受けた影響が大きかった。
講談社に入りたかったのも、スポ根文化の影響が大きかったんです。マガジンで連載していた作品だと『ダイヤのA』(寺嶋裕二)や『あひるの空』(日向武史)が代表的ですが、『天才ではない主人公が努力で成り上がる』という描き方が好きだったんですよ。必殺技を基本的には使わず、敗北もしっかり描く。講談社の作品は、挫折を経ての成長を描くのがすごく上手だと思っていたから、講談社に入りたいと思っていました。僕は高校のときにジャンプからマガジン派になったんですけど、移行するにあたって、講談社のそういう点が自分に合っていたのではと思っています」
若かりし読者の段階で、出版社によってスポーツマンガの組み立てやカラーが異なることに気づいていたとは驚きだ。大学は東京外語大に進学し、ロシア語を専攻。モスクワ大学に1年留学した。
「ロシア語を選んだのは、ロシアに興味があったからというより、単純に一番難しい言語をやってみたい気持ちがあったから。僕、1回自分を追い込む癖があって、めっちゃムズいところからやってみよう!とロシア語を選んだんです。だけど、大学に入ってみたらもっと難しい言葉が普通にあって、『あれ、ちゃうやん!』となりました(笑)」
“わけがわからない試験”をヤケクソ突破した就活
留学と留年を経た、合計6年間の大学生活。就活では、講談社と小学館で出版社を2社、あとは商社やメーカー、海運を中心に受けていたという。
「出版がめちゃくちゃ倍率高いってことだけは聞いていたので、第一希望でしたが出版は正直ダメ元の気持ちで受けていました。出版業界の就活って、商社とかに比べてわけがわからなかったですね。例えば商社の面接だと、形式通りの質問で『リーダー経験はありますか?』と聞かれて、『ありません』と答えたら、面接官がみんな一斉にバツをつける、みたいな。スペックで見られている感じ。そちらのほうが求められているものがわかりやすくて対策しやすかったですが、出版社はまったく対策していなかったのでかなり翻弄されました。
講談社や小学館の筆記試験は激ムズで、まったくできなかったのを覚えています。一般常識問題という、いわゆるSPIとは別の試験があるんですが、時事問題だけではなくて女性誌とかの知識も問われるんです。『スカーフのこういう巻き方の名称は?』みたいな。こんなんわかるか!みたいな(笑)。あまりにわからなくて、講談社の試験では、最後に作文があったからヤケクソで彼女に振られた話を書いたんです。ポエム調で『ロシア留学中、彼女を寝取られました』というエピソードを書いたら、それが面接官にすごく刺さったらしくて。次の面接では『ねえねえ、今どんな気持ち?』って聞かれたんですよ(笑)。それで、すごく面白い会社だなと思いました」
筆記試験はスットコ(予想)だが、作文で一風変わったエッセイを書いてきた候補者を残す──。曲者を好む、出版社ではありえそうなエピソードだ。
「出版社の面接では、『どんな企画がやりたいの?』と聞かれることが多いと思います。だけど僕はそうした常識をまったく知らず、『企画って持ってこないとダメなんですか?』みたいなリアクションしたら、面接官が2人とも『え!?』みたいな感じになって(笑)。でも逆に面白いって思ってもらえたのか、『じゃあ好きなマンガでいいから教えて』と言われて、『ヤバい、捨てられる!』と思って一生懸命話しました」
「挫折からの勝利」のストーリーを好む白木氏だが、それを地で行くような人生だ。
治安の悪い人たちが巣食う部署=ヤングマガジン編集部へ
2014年、念願叶い講談社に入社した白木氏。希望部署は、週刊少年マガジン編集部かモーニング編集部だった。
「マガジンでは『ダイヤのA』や『あひるの空』、『ベイビーステップ』(勝木光)のようなスポ根もの、モーニングでは『宇宙兄弟』(小山宙哉)、『GIANT KILLING』(ツジトモ)、『ブラックジャックによろしく』(佐藤秀峰)みたいなお仕事ものに携われればと思っていました。モーニングのお仕事ものって超カッコいいな!という気持ちがありましたね」
ところが蓋を開けてみると、その2誌とはかなり毛色が違うヤングマガジンに配属となった。
「人事部から『君はヤンマガ!』って言われて『え?』って。うれしい3:困惑7みたいな気持ちでしたね(笑)。今でも覚えてるんですけど、ヤンマガ配属の日の部会で、会議室で四角形に並べられた席の前に出て僕がしゃべるんですけど、席にはドレッドヘアの人とモヒカンの人がいて、どちらも顔が怖かったんですよ。その人たちはみんなヤンマガの部員で、なんなら同じタイミングでヤンマガに異動してきた人も顔が怖かった(笑)。『俺はなんてところに来てしまったんだ……』という気持ち、強烈に覚えていますね」
治安の悪い見てくれの、コワモテ編集部(現在は女性部員も4人いて、柔和な雰囲気に変わっているそうだ)。それまでヤンマガをまったく読んだことがなかったという白木氏。編集者のキャリアをスタートした新人時代は、「脳が思い出すのを拒否する」くらい、大変な日々だった。新人・白木氏が担当したのは、「賭博堕天録カイジ ワン・ポーカー編」(福本伸行)と、グラビアページ。
「全部で5作品を担当して、グラビア以外の記事ページも膨大にあったんですが、特にその2つが時間的にものすごく大変だったんですよね。どちらの仕事も楽しかったんですけど、グラビアは急に朝6時からロケが入ってその日1日潰れることもあるし、福本先生の打ち合わせは夜22時くらいから入ることも多い。その2つだけでけっこうパンパンだったんです。ただ、“せっかくマンガ編集者になったからには新作も立ち上げたい!”と思い、必死こいて新人作家さんと打ち合わせをしていたのが、1年目ですね」
そして福本の担当で忘れられないのは、「1回、ネーム描いてきて」と言われたこと。
「もちろん『お前が話を作れ』という意味じゃなくて、『1回描いてみて、俺のと比べてみよう』と。要は、ネームを描くのがどれだけ大変かを1回体感してみてほしいということだと思います。福本先生にネームを見ていただけるなんてかなり貴重な機会なので、徹夜で描いて自分なりのベストを持っていったんですが、当然結果はまったくダメで(笑)、さすが福本先生という感じでしたね。自分にとってはすごくいい経験でした。福本先生やマンガ家の方々をよりリスペクトするようになりましたし、ネーム1つでもこれだけの時間がかかるんだ!というのが身にしみました」
今度は、福本作品を地で行くようなエピソードだ。そんな福本には、一度だけ褒められたという。
「『お前は作品に対して嘘はつかないよね。そこは続けてね、信用してるよ』という旨のこと言っていただいたんです。打ち合わせを終えてタクシーで帰るときに、泣きそうになりました(笑)。うれしかったですね、あの日は」
「エグい作品といえば白木」の原点……「生贄投票」
そんな経験から、自分で作品を立ち上げたいと考えるようになった白木氏が最初に手がけたのが、「生贄投票」だった。原案は葛西竜哉が小説投稿サイト・エブリスタに公開していた小説で、同社からマンガ化の提案があり、江戸川エドガワが作画を担当する形で実現した。
「小説版は、アプリで選ばれた人が順次死んでいくというストーリー。その時点で面白かったんですけど、マンガにしたとき、ただ死ぬだけだとすでに市場にある作品と大きな差がなく、あまり目立てない気がしていました。エブリスタさんからも『原案のニュアンスを尊重してくれれば、設定を大幅に変更してもよい』というご連絡をいただいていたので、何かプラスアルファが欲しいですねという点を江戸川先生とすごく話し合って、『生贄に選ばれた人に訪れるのはただの死ではなく“社会的死”』ということにしました。あくまで原案の設定ありきですが、その変更には大きな意味があったと思っています」
物語は、高校生・今治美奈都のスマホに「生贄投票」というアプリが突然表示されるところから始まる。そこには、候補者としてクラス全員の名前が並んでおり、生贄に選ばれた者には「社会的死」が与えられるという。深く考えずに友人の名前を押してしまったが、この投票がクラスに大きな波紋と崩壊をもたらしていく──。2015年からWebのeヤングマガジンで連載を開始し、2016年に1巻発売。腹部にマジックで「生贄投票」と書かれた女子高生が黒板の前に立たされ、その様子を生徒がスマホカメラを向けている。扇情的でものものしいイラストが表紙の1巻は、当時の書店で目立つ場所に必ず見かける話題作だった。そして、何より電子書店で爆発的に売れた。
「かなり手応えありましたね。当時はバナー広告がものすごく回っている時代でした。毎日編集部に各電子書店からバナーの確認が10本ぐらい届いて、マンガってこうやって売れていくんだと実感していたんですけど、同時にすごく苦しんでもいて。初めての立ち上げだったんで、単純に、どういうふうに打ち合わせをして作品を回し、どういうふうにゴールに持っていくのかがまったくわかってなくて。ずっと迷子みたいな気持ちで、なんとか一筋の光を探す、みたいな作業でした。江戸川先生にはご迷惑をおかけしてしまいましたが、作品がどんどん大きくなっていく感じがして打ち合わせは楽しかったですし、先生にはたくさんのことを教えていただきました」
手探りながらも、徐々に自身の方法論と強みを探り当てていく。
「当時、『生贄投票』に加えて『食糧人類-Starving Anonymous-』(原案:水谷健吾、原作:蔵石ユウ、漫画:イナベカズ)というマンガを担当していたので、会社では『エグい作品といえば白木』という感じになっていました(笑)」
心のキレイな人間なのに、なぜこんなにエグいマンガを……
のちに「満州アヘンスクワッド」や「ねずみの初恋」などを立ち上げる“エグ系”編集者としての片鱗が、すでにこの時点で見えすぎている。本人はそこをどう考えているのだろうか。
「不思議ですよね。こんなに心のキレイな人間なのにどうして、って思うところが多々あります(笑)。まあそれは冗談ですが、もともと主人公が残酷な運命に立ち向かうような話は大好きなので打ち合わせしているときはめちゃくちゃ楽しいですし、僕がエグいマンガが好きになったのには、明確にきっかけがあるんです。
ヤンマガに、20才くらい年上のレジェンド編集で、『ザ・ファブル』を担当した田坂さんという方がいるんです。その方が、僕の配属直後ぐらいに『白木、これを見ろ。サスペンスの面白さはこれに詰まってる』って、急にDVDを渡してくれて。それが、韓国映画の『チェイサー』でした。それまでは僕、エグい映画とか全然観る人間じゃなかったんですけど、勧められたので観たら、もう半端じゃないぐらい面白くて! 翌日田坂さんに興奮を伝えて、そこから『サスペンスって面白いな!』と思うようになりました。運よく、1年目の後半から『三億円事件奇譚 モンタージュ』の渡辺潤さんの担当をさせていただいたことも大きかったです」
まず、ヤンマガファンには「タサカ兄さん」として有名な田坂氏については、講談社のマンガ投稿サイトDAYS NEOに自己紹介があるのでぜひ一読いただきたいのだが、同誌の名物編集者である。そして、田坂氏が勧めてきた映画「チェイサー」は、2008年に公開された韓国映画で、ナ・ホンジン監督の長編デビュー作。韓国で実際に起こった連続殺人事件をベースとしたノワール作品で、デリヘル店を経営する元刑事と、連続殺人犯との攻防を描く。容赦ない暴力表現、スリリングな展開、非情な結末が世界に衝撃を与えた一作だ。レオナルド・ディカプリオがリメイク権を獲得していることでも知られている。白木氏の資質を見抜き、「覚醒」させた田坂氏は、けだし慧眼である。
「僕の何を見て、なんで貸してくれたのか未だにわからないんですけど、本当に慧眼でしたね」
首をひねりながら話す白木氏だが、エグさとキレイさが同居している話題作もある。「邪神の弁当屋さん」(イシコ)は、ダーク×ほのぼの世界観が魅力の、いま注目のファンタジー作品だ。主人公・レイニーはかつてソランジュという名の邪神であり、戦争を引き起こした罰を受け、今は人間として生活している。営むのは、一日一善をモットーとする弁当屋。一見、ぽわんとしたかわいらしいキャラクターデザインや世界観なのだが、ところどころにヒヤッとするような残酷な世の理が見え隠れする。これもまた不思議な読後感が残る傑作だ。
「そんな流れでもう1つ言うと、以前先輩に『お前の中の“心の一作”って何なの?』と聞かれたことがあって。売れた作品という意味じゃなくて、『世に残せてよかったなと思う作品』。それは、『アンサングヒーロー』(原作:うらたにみずき、漫画:鯛噛)という作品です。レコード会社を舞台にしたお仕事ものマンガなんですが、僕はこの作品を残せてよかったと心から思っています。お仕事ものをやりたかったのもありますし、原作・作画担当の方はどちらも新人さんで、素晴らしい描きっぷりだった。個人的に名作で、心の中で大事にしている、矜持みたいにしている作品ですね」
深淵を覗く白木氏は、深淵に取り込まれるのか?
「キレイな白木氏」の話は聞けたので、ここでまた「エグい白木氏」の話に戻ってみたい。これだけアウトローものや、人が無惨にも殺されていく作品を多く担当している白木氏だが、「深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いている」(ニーチェ)と言われるように、闇に取り込まれそうになることはないのか聞いてみた。答えは「めちゃめちゃあると思います」。
白木氏の現在の担当作の中でも、特に“エグさ”が現れているのが「満州アヘンスクワッド」(原作:門馬司、漫画:鹿子)。現在のヤンマガのダークカラーを間違いなく代表する一作だ。2020年に連載を開始し、現在、単行本の累計発行部数は300万部を突破している。昭和12年、関東軍の兵士として満州にやって来た日方勇は、ある農場の片隅でアヘンの原料であるケシが栽培されていることに気づく。病気の母を救うため、アヘンの密造に手を染める勇に、中華民国の秘密結社・青幇(チンパン)の首領の娘・麗華(リーファ)が近づき、利害が一致した2人はアヘンの密造と販売網をどんどん広げていく。2人のもとには、日本人や中国人のみならず、モンゴル人やロシア人など、民族も目的もさまざまな個性的な面々が集まり、最強の“チーム”=スクワッド(squad)が形成されていく──。
正直、少し前であれば、「アヘンの密売グループ」がヒーローとなり活躍する作品が、これだけ大々的なヒット作となる事態は想像できなかったように感じる。白木氏の暗躍、もとい奮闘により、ヤンマガ掲載作や青年マンガ全体のアウトロー度合いや残酷さの総量は増大しているように感じているが、白木氏も同意見だと前置きしたうえで、ヤンマガの現在について語ってくれた。
「僕の中でヤンマガの何がカッコいいかって、“俗とハイエンド”があるところだと思うんです。過去の連載作品だと、俗っぽいマンガは、例えば『ビー・バップ・ハイスクール』(きうちかずひろ)や『行け!稲中卓球部』(古谷実)など、時代の空気感を鋭く切り取った究極に面白い作品。ハイエンドの作品は、『AKIRA』(大友克洋)や『攻殻機動隊』(士郎正宗)など、SFやファンタジーをはじめとした、国や時代を超えて愛されるスケールの大きな作品。それらが一緒に載っていて、掲載作が雑多でギャップがあるのはすごくいい雑誌だなって思っているんです。
今は、言うなれば“俗”側の強化。俗なマンガは売れやすいし、ヤングマガジンだから振り切れたこともできるということで、いろんな作家さんに描いていただける。だからおそらく俗のほうに軸が振れているのですが、僕の編集者としてのここからの課題としては、ハイエンドのほうをもっと増やすこと。具体的には、SFやダークファンタジーで、やっぱり世界で売れるマンガを世に出したい気持ちもあるので、今まであまり担当してこなかったジャンルの作品の担当をしてみたいですね」
タブーを描く際に気をつけるのは「曖昧な歴史を描かない」
“俗”は極めつつある段階の白木氏の、“ハイエンド”作にも注目していきたい。さて、白木氏の編集手腕で1つ飛び抜けていると感じる点がある。それは、タブーや歴史の描き方だ。新人の頃に担当していた「モンタージュ」では3億円事件、「満州アヘンスクワッド」では満州時代の大アヘン政策という、未解決事件や“暗い歴史”とでも言うべきものをエンタメに昇華させる際、何に気をつけているのか聞いた。
「『曖昧な歴史を描かない』に尽きると思っています。『これは史実です』と言えるような、実際にあったと確定しているものしか描かない。
社内での確認も頻繁にしているので、法務部からはヤンマガってめちゃくちゃ相談に来る部署だと思われている気がします(笑)。インドを舞台にした『ラージャ』(印南航太)という作品でも、カースト制度を作品に出していいのか?という点をかなり検討しました。カースト制度自体がそもそもセンシティブなものなので、これを描くことは正義か否かという話になったときに法務に確認し、監修をつけることになりました。さらに、その道の権威の方にお話を聞いたり、いろいろと準備をしましたね」
一般的な感覚なら「この話題を扱ったが最後、厄介な確認が山程発生し、鬼のようなクレームも来る」と用心し、正面から扱う人が少ないテーマも、白木氏にかかると大ヒット作に生まれ変わる。用意周到に地雷を避けながら地雷原をつき進んでいる感がある白木氏だが、こうした勇ましさやギリギリまで攻める姿勢が、作品の面白さや唯一性、ひいてはヒットにつながっていることを確信した。
「究極の純愛は残酷さの中にある」──「ねずみの初恋」
さて、大瀬戸陸「ねずみの初恋」も、近年白木氏が手掛けた大ヒット作だ。2023年に連載を開始した同作は、昨年筆者の周りでも大変な話題になった。昨年の夏頃、本連載企画の発案者であるコミックナタリー増田氏が「最近ヤンマガがめちゃくちゃ面白いんですよね。『ねずみの初恋』っていうマンガがヤバくて……」と興奮気味に話していたのが思い起こされる。
主人公のねずみは、ヤクザに殺し屋として育てられ、人の愛を知らずに育った少女。何も知らない普通の青年・碧(あお)と恋に落ち、ともに暮らし始めるが、平穏に見える日常のすぐそこに魔の手が迫っており……というクライム・サスペンス&ラブ・ストーリー。ねずみという一見童顔で愛らしいキャラクターが、表情一つ変えず、プロフェッショナルに淡々と殺しをこなす日常と、碧との初々しく甘々な同棲生活が並行して描かれていくのが奇妙で印象的。心を深くえぐり、今までにない読書体験をもたらしてくれる。連載スタートからわずか1年で30万部を突破したという、「ヤンマガ史上最速ヒット」作。単行本は6巻まで刊行されており(25年7月時点)、その時点で累計100万部を突破している。2025夏、歌舞伎町タワーにてポップアップショップも開催されるほどの人気作となった。
作者の大瀬戸は、2022年にヤンマガWebで「影霧街(えいむがい)」の連載を開始し、デビューした新人。「ねずみ」は連載2作目となる。まだ20代前半という若い大瀬戸だが、「影霧街」から「ねずみ」では、どちらもアングラで薄暗い、そして人がたくさん死ぬという世界観を共有しているものの、絵や物語の構成が大きく変化しているように感じられる。大瀬戸の変化について語ってくれた。
「大瀬戸さんの、どメジャーを狙いたいという意志がそうさせたんだと思います。いつも『売れたいです』『メジャーに行きたいです』とおっしゃっていて、高い志を持っていたんです。ただ、大瀬戸さんが一番やりたいものって、『影霧街』なんですよ。ご本人も『影霧街』のほうが好き、とおっしゃっている」
影霧街は、街の名前である。主人公・みおんの兄がある日突然失踪するところから物語は始まる。兄が残した「影霧街」という情報を頼りに、みおんは兄を見かけた怪しいビルに潜入しようとするが、そこは恐怖の入口だった──。
「大瀬戸さんの初連載作として『影霧街』を担当させていただいてからは、『読者の感情を下げただけでは厳しいと思います』という話をよくしていました。きついシーンとかエグいシーンを“下げ”って呼んでいるんですけど、大瀬戸さんに必要なのは“上げ”、つまりキャラにとってのうれしいシーンや、読者が気持ち良さを感じられるシーンです。そこで感情を昂らせ、“下げ”との振り幅を作ることが重要だと思っていたので、次回作では読者が楽しみやすいものを題材にしてほしいです、とお伝えしていました。
具体的には、『影霧街』の次は『天才か恋愛か殺し屋を描いていただきたい』という話をしていました。『最強要素』や『恋愛要素』は読者にとっての“上げ”になりやすいからです。この“上げの意識の変化”が大瀬戸さんの中では大きかったのかなと思っています」
読者の感情の“上げ下げ”。極めてシンプルな表現であるが、こうした言葉遣いをする編集者に初めて出会った。ストーリー全体を見渡して、読者の感情がどう振れるかのバランスを見る。編集力である。
「『影霧街』でも、ヒロインの女の子が意外とへこたれなくて、不器用なところや間の抜けたところにクスッとできる描写はあるんですが、“上げ”までは行ってないなと。そんな『影霧街』では、僕がものすごく好きな上げが1個あって、それは純愛のシーンだったんです。『ねずみ』では、その感情をベースにしてほしいと思っていました」
「ねずみ」においては、2人の初恋・純愛ゆえのイチャイチャ、もぞもぞするシーンや、エッチなシーンは上げ。殺したり、メインキャラがかわいそうなシーンは下げ。そう思いながら「ねずみ」を読むと、確かに上げと下げは交互に訪れ、かなり感情を揺さぶられる。
「僕は勝手に『究極の純愛は残酷さの中にある』って思ってるんです。『タイタニック』や『ロミオとジュリエット』も、登場人物が悲劇に遭えばいいってわけじゃないですが、2人の愛が試される瞬間って絶対に必要だなと思っている派……って、急にロマンチックなこと言いましたが(笑)。
“上げ”の大切さについて、大瀬戸さんが突き詰めて考えてくださったのが大きかった気がします。そして実際、上げがとてもうまかった。天才ですね」
「影霧街」から「ねずみの初恋」で、画力も格段に上がったように見受けられる。
「絵については、僕は『模写をしてほしい』ということ以外は言っていなくて、『とにかく練習しましょう』『画力は絶対に上げたほうがいい』という話をしたら、大瀬戸さんが予想の100倍ぐらいがんばってくれた。『勉強します!』と言って、恋愛描写のエッセンスを取り入れるためにたくさん少女マンガを読まれたり、絵柄の勉強のために『ベルセルク』を読まれたりして、とにかくがんばっていらっしゃいました」
ヤンマガのYouTubeチャンネルで大瀬戸に密着した回で、本棚に「サクラ、サク」(咲坂伊緒)があるのが印象的だった。松本二郎や山本英夫、新井英樹や花村萬月、平山夢明の作品の中に奇妙に混じって。
「ヤンマガで、大瀬戸さんと魚豊先生の対談を実施したのですが(2025年1号)、魚豊先生の意見がめちゃくちゃ面白かったんです。Instagramにあるフィルターみたいなイメージで、“『ねずみの初恋』はフィルターを使っている”というお話で。殺人シーンとかでもエモく“玉ボケ”とかしてるじゃないですか。そういうシーンを指して、『殺人をエモく描いたのは、『ねずみの初恋』が初めてですよね』とおっしゃっていて、確かにそうだ……! と思いました」
フィルターを使って、殺人をエモく……!「チ。」の作者である鬼才・魚豊らしい、シャープすぎる目の付け所だ。そして、「ねずみ」では、個人的にもう一点気になるモチーフがある。3巻で、対抗するヤクザの組織に捕らえられた碧をねずみが救いに行くシーンで、ねずみが容赦なくヤクザたちを殲滅していくなか、死んでいくとあるヤクザが身につけていたロザリオや、フロアに置かれていたマリア像が大写しになるのだ。大量殺戮シーンとクリスチャンのモチーフ。絶妙な味わいを残すシーンである。
「そこを見ていただいてありがとうございます、うれしいです。大瀬戸さんって、十字架に対する気持ちが強いんだと思います。『ねずみ』でも、“実は十字架”って構図がけっこうあるんですよ。例えば、1巻の5話のラストで、碧が訓練でねずみにナイフを突きつけているシーンも、よく見ると窓が十字架の構図になっているんです」
ぜひもう一度ページを丹念に眺めて、いろんなモチーフが隠されているのを探してみてほしい。殺し屋という俗と、純愛という聖。対極にある2つの、どちらの極北も同時に描いていることを象徴するシーンと言えるだろう。メシア(救世主)というキャラクターが輝いていたのも忘れてはならない。読めば読むほど、深読みしたくなる味わいがある。
「考察要素は多いと思います。大瀬戸さんに先の展開についてお聞きする中で、『ここはこういう意味なんです』と教えてもらって、『えーっ!』と驚くこと、僕も多いんです。やっぱり天才だと思います。
大瀬戸さんには独特な死生感があるのですが、韓国映画の影響も受けているんですよ。韓国ってキリスト教徒の方も多いので、映画にもそのモチーフが出てくることが多いんですよね」
なぜ私たちは残酷なものが好きなのか?
大きな声では言えないが、私は残酷な物語が大好きである。「羊たちの沈黙」に「セブン」、「ひぐらしのなく頃に」「バイオハザード」「アウトレイジ」「ミッドサマー」「地面師たち」。だけど、なぜ? 自問したときに、納得の行く答えまでたどり着けない。刺激的だから、血が好きだから、死を思い起こせるから、なんかスカッとするから……。エグい編集の白木氏は、どう考えているのか聞きたくなった。
「『キャラクターに過酷な運命が待ち受けているほど、物語は面白くなる』というのは、エンタメの基本だと思っています。主人公が悲惨な目に合うのは面白いじゃないですか。少年誌でも、『NARUTO-ナルト-』はけっこう壮絶な始まり方をしていますし、『ONE PIECE』でも、シャンクスはルフィの眼の前で腕を食べ られちゃう。みんな心の根っこでは『残酷なものが好き』というのはあるんだと思います。でも残酷なシーンがあるから面白いというわけではなく、そこにキャラクターが立ち向かうから面白くなっている。“死にそうな状況”やピンチでの立ち振る舞いというのは、ある意味キャラの究極の人間性が描かれる瞬間なんだと思います」
以前、とあるインタビューで白木氏は、読者に作品を買ってもらうには「まだ世の中にない要素」が必要であり、新人作家には「読者を驚かせる意図があるかどうか」を重視している、と語っていた。これだけ物語が溢れている世の中で「まだない要素」を見つけるコツとは、「“もうある”をいかに知っておくか」だという。
「まだない要素を見つけるのは、めちゃくちゃ難しいです。裏を返せば、どれだけ知っているかにかかっている。だから、とにかく『摂取するしかない』と思っています。僕は物量型の人間で、とにかく教わった映画を観る、ドラマを観る、マンガ読む。全部やります。それで、ストーリーの“型を見る”んですよね。『この型はなかった』という発見をしたとき、マンガってすごいなって思うんです。ゼロからまったく新しい型を作るのはとても難しいことなので。例えば、『満州アヘンスクワッド』は、仲間を増やして旅をするという点で『ONE PIECE』と近しい型になっています。
時代によって流行ってる型に加え、普遍的に面白い型というものも存在します。例えば、『JIN-仁-』(村上もとか)というマンガは、医者がタイムスリップして無双する話という部分は、今流行っている異世界ものとまったく同じ型だと思っている。ただ、医療知識を活かして活躍するという部分が新しかった。新しさを見つけるときって、世の中にある型に対して、何を掛け算できるかが重要だと思っていて、異世界の型に医療ものを掛け合わせたのが『JIN』だと思うんです。当時はまだ異世界は流行っていなかったので、あくまで僕がそう因数分解しているだけなんですが。あと、僕がすごく好きな作品で言うと、『青野くんに触りたいから死にたい』(椎名うみ)は掛け算として新しかったです。ラブコメの型にホラーを掛け合わせたもので、そのパターンはなかったと思うんですよね。物語は、そうして型を見ながら、因数分解で考えているのかもしれないです。どう掛け算したら新しくなるかな、と」
物量型の編集者です、と言い切るのはすさまじい。何より、時間がものすごく必要だ。
「時間はなんとでもなりそうな気がします。もっとやっている人はいくらでもいるだろうから、僕もがんばらなきゃですね」
そう笑う白木氏は、やっぱりスポ根型かもと漏らすと、「そうですね。僕は完全に気合と根性の民なんで」と笑った。そして、これだけの物量を摂取した結果、世界はまだまだ隙だらけなのが見えたという。
ヒットの条件は「欲の数の多さ」/「僕は揺さぶり編集です」
そんな白木氏の目には、「作品がヒットする条件」はこんなふうに映っている。
「1つは、先ほど言った掛け算の話で、『この手があったか!』と思える新しさがあるときは売れるなと思います。『ダンジョン飯』(九井諒子)のファンタジー×グルメなんかもそうですよね。もう1つは、楽しめる“欲の数”が多い場合。いい企画って、欲の数がめちゃくちゃ多い。例えば、編集界隈でお手本だと言われるのは『ゴールデンカムイ』(野田サトル)なんですよ。
金銭欲に冒険欲、知識欲、食欲、生存欲求も追い求めて満たされる、みたいな作品で、欲の数がものすごく多い。やっぱり読者の方々にお金を払ってもらうためには楽しめるものが多くないと。とはいえ『ゴールデンカムイ』くらい完璧な欲の詰め合わせは、なかなか難しいんですけど(笑)」
欲の数! 「ゴールデンカムイ」は、埋蔵金を探しながら、北海道の大自然や宿敵たちとの生存競争に晒され勝利し、恋をし、見たことのない食べ物を料理し、食べる──ハラハラしながら読み進めると、なぜだかさまざまなものが満たされていく。これは、キャラクターたちの欲とその充足が、読者のそれらダイレクトに繋がっているということだろう。しかしながら、欲の数が多い作品は、匠の作家や編集だからこそうまく組み立てられるように思う。そんな白木氏が得意分野だと自認している編集スキルは、「揺さぶり」だという。
「あくまで作家さんありきなので横柄な言い方ですが、僕自身の強みをあえて一つ挙げるとすると、読者を揺さぶるのが得意だと思います。揺さぶり編集ですね(笑)。さっきの話でいうと、上げ下げを作家さんと一緒に考えるのがめちゃくちゃ得意で、これはサスペンスを長く担当してきたおかげなんですよね。サスペンスって基本的に上げ下げの繰り返しなので。それが培われたのは、『モンタージュ』とか『クダンノゴトシ』などの、渡辺潤先生の作品や、千代先生の『ホームルーム』を担当させていただいた経験がとても大きいです。
揺さぶりというのは、いわゆる緩急と意味が近くて、簡単に言うと、1話の中で『上げて落とす』みたいなことです。『ねずみの初恋』の1話って、最後めちゃめちゃ下げるとこで終わらせているのですが、直前まではめっちゃ“上げ”にしてるから、大瀬戸先生の揺さぶりが成功したと思うんですよね」
「ねずみ」第1話は68ページ。読者側の感情があっちこっちに行って、情緒が忙しい第1話だ。
「実は1話を最初に大瀬戸さんからいただいたときって、『おつかれぇ ねずみちゃん』『おつかれさまぁ 碧くん』のシーンで終わってたんですよ。殺し屋の女の子が同棲生活始めました、で終わり。その時点でも告白シーンはありましたし、殺し屋と恋愛のギャップがあって面白かったんですが、読者の心を揺さぶるにはまだ弱かった。大瀬戸先生の才能を考えるともっとインパクトが出せるはずで、そのラストではさすがに勝負できないから、どこで切るかを考えて、一番いいところでということで、今の箇所になりました」
(※これから読む人にはネタバレ)完成版の第1話、終盤のストーリーはこうだ。同棲を始めて幸せいっぱいな2人は、数日後のねずみの誕生日に「エッチ」する約束をする。ところが当日、ねずみの仕事を碧が目撃したことが組織にばれ、碧は拉致される。碧が拷問を受けているところにねずみが連れてこられ、「碧を殺せ」と命じられて──、というものだ。結果、揺さぶり大成功の第1話となった。揺さぶりのコツとは、「めっちゃ上げてから落とすこと」。
「結局、振り幅だと思うんです。落としてから上げるのもありですが、そっちのほうが難しくて、かつ重要だと思っています。大瀬戸さんがすごいのは、上げのパターンがめちゃくちゃ多いこと。下げのほうが全然簡単で、編集が手伝える部分もある。例えば『こいつをひどい目に合わせましょう』とかは誰でも言えることなんですが、上げはそうではない。がんばった碧くんへのご褒美として『ねずみが乳首を見せる』(3話のラストページ)とかって思いつかないじゃないですか。
それに、上げのシーンが面白くならなかったとき、大瀬戸さんは『じゃあ、こういうのどうですか?』って出してくるのが信じられないくらい早いんですよ。ご本人曰く、常に4パターンくらい考えていて、一番よくできたのをネームで送ってくださると聞いています」
「誠意と馬力」で作家に尽くす
残酷で純粋。「ねずみの初恋」は、さまざまな極限と矛盾、それらが渾然一体として煮込まれたときに何が起こるのかを見せてくれる、得難い思考実験のようだ。こんなに面白いマンガを大瀬戸氏とともに生み出してくれて、感謝しかないのだが、「めぞん一刻」の音無響子が白木氏の性癖を歪めたように、「ねずみ」もまた、リアルタイムで多くの人のなにかを歪めつつ爆走しているように見える。この先、どんな未来が待っているのだろうか。
さて、多様な作家/作品を担当している白木氏だが、マンガ家について語るとき、言葉の端々に作家への敬意が溢れている。そんな白木氏にとって、マンガ編集者として大事な要素は2つ。それは「誠意と馬力」。
「第一に、圧倒的に必要なのが誠意。作家さんのためにどれだけできるかです。作家さんのためを考えて、どれくらい早く返事したり、役に立つ打ち合わせをできるか。企画書を作るにしても取材するにしても、それが一番大事だし、たくさんマンガを担当するためには馬力が必要だと思う。
さらに、どんなに尽くせたとしても、やっぱり最終的には作品として立ち上げなきゃ意味がない。そのためには編集者はがんばって働かなきゃいけないんですよね。そこをがんばるという意味でも馬力が必要です。だってこの仕事って、やっぱり自分で作品を立ち上げないとあんまり楽しくないし、自分で作品の全責任を追える状況じゃないと、本当の意味で作家さんの人生を背負っていないと思うから」
さらに、編集者を目指す人には、自戒を込めて言いたいことがあるという。「今のうちに映画とかドラマとかいっぱい観といてほしいなって」。白木氏は、作家との共通言語になりそうな“基本的な”作品でも入社するまで見ていないものが多く、とても苦労したそうだ。そんな白木氏が今後叶えたい夢の1つは、「1000万部作品を出すこと」。ちなみに、これまで担当した作品で一番売れているのは、「満州アヘンスクワッド」で、前述のようにシリーズ累計300万部を突破している。
「まだまだ売れてほしいと思っています。それに、僕はすべての作家さんに、とりあえず300万部売れてほしいんですよ。そうするとサラリーマンの生涯年収くらいは稼げたことになる。マンガ家になってよかったなって思えるはずなんですよね」
そしてもう1つは、世界をまたにかけた夢。
「海外に支社を立てたいですね。現地の作家さんが、その国の人しか知らない価値観で生み出したものを担当してみたい。フランスやイタリア、台湾やインドネシアもいいし、行けって言われたらどこでも行くと思います。いずれそうなるんじゃないかと勝手に思っています」
白木英美(シラキヒデミ)
1990年、茨城県生まれ。2014年に講談社に入社し、ヤングマガジン編集部に配属される。現在は月刊ヤングマガジンと、北米増刊・ヤングマガジンUSAのチーフを兼任中。現在の担当作品は「満州アヘンスクワッド」「ねずみの初恋」「邪神の弁当屋さん」「やちるさんはほめるとのびる」など多数。
(コミックナタリー)
 ERR_MNG
ERR_MNG