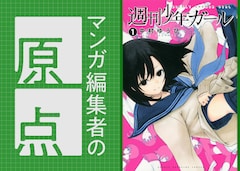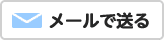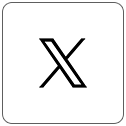マンガ家が作品を発表するのに、経験豊富なマンガ編集者の存在は重要だ。しかし誰にでも“初めて”がある。ヒット作を輩出してきた優秀な編集者も、成功だけではない経験を経ているはず。名作を生み出す売れっ子編集者が、最初にどんな連載作品を手がけたのか──いわば「担当デビュー作」について当時を振り返りながら語ってもらい、マンガ家と編集者の関係や、編集者が作品に及ぼす影響などに迫る連載シリーズだ。
今回は「ブルーロック」をはじめ、「七つの大罪」「アルスラーン戦記」「神さまの言うとおり」「炎炎ノ消防隊」「ランウェイで笑って」などのヒット作を担当する週刊少年マガジン編集部の土屋萌氏が登場。ファンには「担当・T屋です!」から始まる個性的なアオリ文でお馴染みの名物担当編集の、初めての本格的インタビューとなる。
2012年に講談社に入社して以来、週刊少年マガジン編集部で少年マンガ一筋。テンションと自意識高めのアオリ文やX投稿から、一体どんな人物なのかといつもより少し緊張しながら登場を待っていたところ、現れたのは物静かでシャイな雰囲気の、微笑をたたえた男性だった。胸に秘めたる少年マンガへの愛情を深堀りしながら、「担当・T屋」が爆誕した意外な舞台裏にも迫った。
取材・文 / 的場容子
ずっと1人でマンガを読んでいた
土屋氏の記憶の初期にあるマンガは、「ゲゲゲの鬼太郎」(水木しげる)や「落第忍者乱太郎」(尼子騒兵衛)だった。
「父親がマンガや本を読む人で、毎週マガジンを買っていたり、家に『ゲゲゲの鬼太郎』があったりして、僕も読んでいました。自分から進んで読んだのは『落第忍者乱太郎』が最初だと思います。その後、物心ついた頃にはジャンプっ子になっていて、小学校3、4年生くらいからは毎週ジャンプを読んでいました。
その頃のジャンプでは『ONE PIECE』(尾田栄一郎)や『NARUTO -ナルト-』(岸本斉史)、『HUNTER×HUNTER』(冨樫義博)を読んでいて、少し前の『幽☆遊☆白書』(冨樫義博)や、『ジョジョの奇妙な冒険』(荒木飛呂彦)も単行本で読んでいました。ジャンプ以外では、『らんま1/2』(高橋留美子)も大好きだった。いわゆるメジャーな作品を読んでいましたね」
一人っ子の土屋氏は、友達とワイワイマンガを読むタイプの子供ではなかったという。
「部屋にいるときは大体ずっと1人でマンガを読んでいました。兄弟がいる友達の、マンガがいっぱいあるおうちに行ったりしても、せっかく遊びに行ったのに友達と遊ばずにずっと黙ったままマンガを借りて読んでいるときもあって(笑)。
編集者がこんなこと言っちゃいけないんですけど、自分の感想を人に話すのがすごく恥ずかしくて。読んだマンガについて論を交わす、みたいなことを編集者になる前に一度もしたことがない。未だに、映画を観にいって、映画館を出た後に一緒に観ていた人と感想を言いあうのも恥ずかしくてできないんですよね。本当に1人で摂取して……摂取とか、カッコいい感じで言っちゃいましたけど(笑)。みんなでそういう話になるときも黙ってることが多くて、感想を言い合うのは、打ち合わせのときの作家さんとだけかもしれないです」
マンガ好きが高じて、将来は漠然とマンガ家になりたいと思っていた。
「とはいえ絵やマンガを描くわけでもなく、ただなりたいと思っていただけでなんの努力もしていなかった。そんな感じで、何も考えずに大学まで行ってしまいまして」
大学では文学部日本文学科で学びつつ、バンド活動に勤しんだ。担当はベース。
「僕が中学生くらいのときにGOING STEADYやガガガSPとかのバンドが流行っていて、日本版パンクロックが盛り上がっていたんです。そういうのを聴きつつ、THE BLUE HEARTSやThe Clashとか、もっと古いパンクを聴きながら、オリジナルで活動していました。パンクロックって、本当にちゃんとやるのはすごく難しいと思うんですけど、ただ表面的に真似して弾くぶんにはすごい簡単なんですよ。簡単なのを弾いて悦に浸っていました(笑)」
バンド活動はしていたものの、音楽で身を立てるつもりはなかったという。
「生意気なんですが、あんまり欲もないし、いわゆる普通の生活をさせていただけていたので『飯を食わなければ!』みたいなハングリーさとか、お金がなくて本当に困ったこともあんまりなくて。バンドをこのままやって別に売れなかったらフリーターでもいいな、くらいの話をメンバーと話していました。そんな感じで就活もちゃんとやらずにいたら、2回留年しちゃいまして。6年になったときに、さすがにいっちょ前に焦りだし、就活をしなければ!となりました。
でもどんな会社があるか、あまり知らない(笑)。そんなときに、変わらずマンガは好きでずっと読んでいて、かつ『バクマン。』(原作・大場つぐみ/漫画・小畑健)や『編集王』(土田世紀)も好きだったので、マンガ編集者という仕事に思い至り、好きだったジャンプとマガジンのサイトを調べたら新卒募集があったので、応募しました。そこでたまたま運よく拾ってもらった感じです」
卒論のテーマは「水木しげると妖怪」。子供時代の原体験としっかりつながっているのが印象的だ。
「七つの大罪」で新人の意見が通った!
こうして2012年に講談社に入社した土屋氏は、希望していた週刊少年マガジン編集部に配属された。最初に担当した作品は「ねらいうち!」(篠原知宏)、「神さまの言うとおり」(原作・金城宗幸/漫画・藤村緋二)、「七つの大罪」(鈴木央)の3作品だった。
「『七つの大罪』は連載前で、ネームの1話目を作っている準備期間でした。先輩の編集者についてやらせていただいたのですが、鈴木先生は新米の僕が言うこともちゃんと聞いてくださって。わけわかんないことを言っていたと思うんですけど、取り入れるかは別として、すごく真摯に自分の意見を聞いてくださったので、その分、滅多なことは言えないなと感じました。
トンチンカンなことを言ったときも、それがただ『よくない』というだけじゃなくて、『土屋さんが言ってることはこういう理由で、後々こうなっちゃうから今はやめといたほうがいいかもです』みたいに、理屈できちんと教えてくださいました」
「七つの大罪」は2012年に連載を開始。ブリタニアの地を舞台に、かつて王国を脅かしたとされる伝説の逆賊「七つの大罪」の1人である主人公・メリオダスと、王国の第三王女・エリザベスが繰り広げる壮大なバトルファンタジーだ。2014年にアニメ化され、2015年には講談社漫画賞・少年部門を受賞。全世界のシリーズ累計発行部数は5500万部(2023年9月時点)を突破する、メガヒット作だ。
「打ち合わせの原体験として一番印象に残ってるのは、第 4話で、ディアンヌという巨人の女の子がメリオダスと再会して、『団長ぉ~~~♡』と抱きしめて頬ずりした後、メリオダスが別の女子と来たことに気づいて『この浮気者──っ!』と彼を放り投げるシーン。最初のネームでは、抱きついて放り投げるまでの間に1、2ページあり、そのページを取ったほうがテンポがいいんじゃないか?と思い、鈴木先生にそうお伝えしたんです。
でもすぐに、せっかくマンガ家さんが描いてくれたページをなくしたほうがいいなんて、めちゃくちゃ失礼なんじゃないか?と、ヤバいヤバいと思ってたら、先生が『確かに』と言ってピッて取っちゃったんですよ。それが、自分の意見が初めて通った経験でもあるし、1年目の編集者が言ってしまった生意気な意見を反映してくださるすごい人だなと驚いた経験でもあります。
1話20ページなので、ページを取るということは代わりのページを作らなきゃいけない。僕は取ることしか考えてなくて、その後のことを何も考えずに無責任に言っちゃったんですけど、そういうことも含めてすぐ反映してくださったのはすごいなと思った。忘れられない経験になりましたね」
17歳でマンガ家デビューし、「七つの大罪」連載開始時にはすでにマンガ家歴18年を数えていた鈴木央。大学を出たばかりの新人編集者の意見を真摯に受け止め、有用な意見は躊躇なく取り入れる姿勢は、清々しい。そして、新人である土屋氏の編集者としての自信を支えたのは、マンガを読んできた経験と、「少年マンガが大好き」という思いだった。
「本当に好きで、少年誌という志望通りの部署で仕事をすることができたので、当時、自分が面白ければ面白いのでは、という感覚は漠然とあったと思います。自分の新人時代──10年くらい前までは、作家さんが『あの作品のあのシーンみたいに……』と例に出す作品は、ちょうど読んでいたものだったことが多くて、そういう意味でのズレは感じなかったです。
むしろ今のほうが、若い作家さんと仕事をするときに、目線を合わせるために最近の作品や新しいエンタメを見たりすることはありますね」
初めて企画から作家と立ち上げた作品は、マガジンSPECIAL(1983年に創刊され、2017年に休刊)に掲載された「週刊少年ガール」(中村ゆうひ)。入社1年目の終わり頃だった。
「中村さんはコミティアでイラスト集を出していらっしゃって、それがすごく素敵だった。『マンガを描くおつもりはありますか?』と聞いたら、短編マンガみたいなものを描かれていたことがわかり、それがすごく面白かったんです。そこから準備をして、既存のものもリライトしつつ3本の連作短編にまとめてもらって、マガジンの新人賞に応募したら入選することができました。その企画が連載という形になりました。いまだにすごく面白いと思っている素敵な作品です」
異色のサッカーマンガ「ブルーロック」ができるまで
土屋氏が最も長く担当している作家は2人いる。「アルスラーン戦記」(原作・田中芳樹)、の荒川弘と、「神さまの言うとおり」の原作者である金城宗幸の2名だ。金城は、「神さまの言うとおり」でマンガ原作者デビューする前は、お笑い芸人を目指した過去もあるという異色の経歴の持ち主だ。
そんな金城が現在手がけるのが、2018年に連載を開始した「ブルーロック」。日本サッカーをワールドカップ優勝に導くストライカーを養成するために、ユース代表のFW300人を集めて“青い監獄”=ブルーロックに閉じ込め、サッカーで競わせる。最後に残る1人は世界一のストライカーとなるが、敗者は日本代表入りの資格を永久に失う──“史上最もイカれたサッカーマンガ”の異名を持つメガヒット作は、どのように誕生したのだろうか。
「まず金城さんとは、僕が入社1年目のときに別冊少年マガジンで『神さまの言うとおり』を先輩の下で担当させてもらい、その後週刊少年マガジンで続編『神さまの言うとおり弐』が始まりました。途中から自分がメイン担当となり、連載が終わったときに次回作はどうしよう、という話になって。そのとき、ご謙遜だとは思うのですが金城さんが『自分は邪道の作家で、メジャーなやり方には向いてない』みたいなことをおっしゃったんです。僕たちとしてはやっぱり売れる作品、それも一部の趣味の合う方に売れる作品ではなくて、広くメジャーに売れていく作品を描いてほしいし、描ける作家さんだと思っていた。
そこでご相談して、土台となる題材はメジャーなものにというお願いをし、じゃあファンタジーはとか、教師ものはどうだとか、パイが広そうなジャンルを金城さんと後輩の編集者と話し合っていきました。その中で、スポーツものはどうだろうという話が出て。金城さんはスポーツ観戦がお好きで、特にサッカーとテニスがお好きなので、まず雑談が盛り上がったんです。金城さんの目線では、『日本サッカーも最近面白くなってきてるんだけど、ヒーロー的なストライカーがいなく感じて、そこだけちょっと残念』とおっしゃっていて、じゃあそのテーマでやってみますか、となりました」
こうして、「世界一のストライカーを作る」ことをテーマに打ち立てた「ブルーロック」が動き出した。
「同時に『キャラクターがいっぱい出る作品にしたほうがいい』という話もしていました。というのも、『神さまの言うとおり』はキャラクターがすごく魅力的な作品なのですが、デスゲームマンガなので、キャラがどんどん死んでしまう。そうするとキャラのファンの方も『ここまで応援してたのに死んじゃった』と悲しいですよね。皆さんに応援してただくにあたりそれはもったいないと思っていたので、次はキャラが死なずにいっぱい出てくる作品を描かれたらすごいんじゃないかな、という気持ちがありました。金城さんももっと売れてたくさんの読者に作品を届けたいというお気持ちをお持ちだったので、僕が言うまでもなくキャラは多いほうがいいと思っていたのですが。
こういう感じで、金城さんのやりたいことがどんどん頭の中でできていきました。そのとき例として出ていたのは、『カイジ』シリーズ(福本伸行)とか『帝一の國』(古屋兎丸)だったと思います。ダーティな閉鎖空間で戦わされるイメージと、金城さんが実績のあるデスゲームのイメージが混ざり合っていき、『ストライカーを作るマンガの企画を持ってきます』と言って出てきたのが、『ブルーロック』でした。1話のネームは最初からほとんどあの形で、ものすごく面白くてびっくりしました」
「売れちゃったけどモチベない」の対処法
土屋氏が手がけるヒット作は20巻を超えるロングシリーズになることも少なくない。「七つの大罪」は全41巻、「ランウェイで笑って」(猪ノ谷言葉)は全22巻、「神さまの言うとおり弐」は全21巻、「炎炎ノ消防隊」は全34巻。連載中のものでは、「ブルーロック」は既刊34巻(2025年9月現在)、「アルスラーン戦記」は既刊23巻。ここで気になるのは、長期連載作における作家のモチベーションの保ち方だ。
「まさに最近、そういう話を作家さんとすることがあります。どの作家さんでも連載が始まった最初のうちは、雑誌だったら『アンケート1位を取りたい』とか、『雑誌の表紙になりたい』『あのマンガより売れたい』など、数字上の目標や身近な仮想敵みたいなものを作ってそれを超えていくのが最初のモチベーションになっていることが多いと思います。そこを超えると今度は、マンガ以外の形でもどれだけのお客さんに届くだろうか?というところで、アニメ化や実写化、グッズ化なんかが目標になったり。
例えば『ブルーロック』のおふたりとはすごく具体的な話をしていて、『100円ショップに売っているような商品になれたらいいね』とか『普通に生活している人が生活の中で1日1回みかけるように露出したいね』。つまりマンガ好きだけが行く場所じゃなくて、普通に生活している中に『ブルーロック』がある状態にしたいね、と。そのためにはじゃあこれが必要だ、と考えて作戦を実行してくというか。そうやってだんだん目標を広げてくという、2段階があるような気がしています」
とても具体的な“登山計画”のようだ。問題は、次の段階。
「売れることができた作家さんって、初期に見えていたものは一度全部手の内にできてしまったあとに、何をモチベーションにするかで悩まれたり苦しまれたりすることがあるように感じます。そうなったときのモチベーションの作り方・保ち方は特にその人独自のものが出るというか。例えばお子さんがいる作家さんでは、『今はまだ赤ちゃんだけど、いつかこの子に面白いって言わせたい』と思う方や、読者とその子供の2世代にわたり『“パパと息子で読んでます”と言われたい』と思う方も。
今出したのはキレイな例ですが(笑)、『◯億円の家を建てたい』みたいなことでもいいですし、その先に何か見つけられるかというのは、ロマンや忘れてしまっていた原初的な欲望の領域なのかもしれません。2段階目まではなんとなく皆さん近しいところもある気がするんですが、その先のモチベーションは人それぞれ。それを見つけるために僕たちは雑談をするわけですが、こういう話ができる相手って作家さんのプライベートの身の回りにはきっとあんまりいないんだと思うんです。『ぶっちゃけ、売れちゃったんだけどモチベないんだよね』って、友達とかご家族にもしづらい話かなと。でもクリエイターさんにとってモチベーションってすごく大事なことなんです。大ヒットを出した作家さんというのは実力は折り紙つきで、マンガ制作においてはお手伝いできる領域が減ってくることもあります。そういう方たちのお役に立つために、そこを話し合える珍しい相手として、常にモチベーションをなくさないお手伝いができればいいなと思っています」
「贅沢な悩み」と感じるかもしれないが、苦悩は理解できる気がする。メガヒットを経験した後は、ある種の「解脱」が必要になるのかもしれない。
「いろいろ例を挙げましたが、結局最後は『子供に読んでほしい』というところに行き着く人が、少年誌作家さんには多いような気がします。とはいえ、3段階目のステージまで行ける方がほんの一握り。実際は、 1段階に行けない、2段階ができないからどうしようと悩むことがほとんどです。僕の感覚では、3段階目になると、自分のモチベーションの持っていき方を自覚している方が多くなる印象で、『こういうときはこうすればいい』という方法論を持っている方が多いように思います。ちなみに『ブルーロック』では、『今読んでいる人が、いつかプロのサッカー選手になったらいいね』と話していますね」
作家の前で必要なのは「自己開示」
ここまで土屋氏と話してきて感じたのは、例えがうまく、話しているといつの間にか会話に夢中になってしまう、率直で、魅力的な人間性を備えた編集者だということ。作家との打ち合わせではどんなことを心がけているのか、気になった。
「編集者を12、3年やってる中でいろいろ変遷はあったのですが、最終的には、作家さんと仲良くなるというか、なんでも言えるようにならないとダメだなと強く思っています。これは作家さんと友達になるという意味ではなく。順を追って説明します。
売れている要素や絵柄を分析して、『じゃあこういう要素で作って売れる絵柄で描こう』と決めても、それが全部借り物だとうまくいかない。
じゃあ何がハマったときにうまくいったり、あるいは売れなくても悔いなし!となるかというと、作家さんの中にあるものを引っ張り出せるかだと思うんです。メインテーマでもいいし、小さなこと──例えば女の人の髪の毛を描くのがめっちゃ好きな作家さんなら、それが毎話出てくるだけでもいいし、とにかく作家さんの中にあるものを出したほうがいい。となってくると、『女の人の髪の毛を描くのが好きなんですよ』って、けっこう仲良くないと言ってくれないですよね。原稿を見ていてこちらが気づいて指摘できればいいのですが、そういうある種恥ずかしいことを含めて言い合える仲にならなければいけないと思っています」
相手から本音を引き出し、素顔をさらけ出してもらうためには、「自己開示」が重要だという。
「僕から先に変な話とか自虐っぽい話、失敗談とか恥ずかしい話をしたり、普通人に言わないようなことを言うことは心がけているかもしれない。そうすると、作家さんも恥ずかしいことでも言ってくれることが多い。売れている作家さんって『自分を作品に投影させるべき』ということがわかっているので、最初から話してくれたりするんです。なので、若い作家さんとも、まずそういう話ができるようになることが大事だと思います」
まずは自分の恥部をさらけ出す。目の前の相手と実のある関係になるうえで、とても大事な話が聞けたと思う。いつまでも気を遣ってうわべの話しかしなければ、相手も永遠に同じレベルの話しか打ち返してこないだろう。土屋氏流のコミュニケーション術は覚悟がいるが、誰かと一歩踏み込んだ関係になるには有用ではないだろうか。
「担当・T屋です!」爆誕の舞台裏
さて、そんな土屋氏の、とりわけ見逃せない一面にいよいよ迫っていきたい。土屋氏は、唯一無二のアオリ文職人としても名を馳せている。「担当・T屋です!」から始まり、作品の世界観をさしおいて自身の“モテ事情”を唐突にブッ込む名&迷アオリが登場したのは、「神さまの言うとおり弐」だった。その“ウザ面白さ”は、例えばこんなふうだ。
「担当・T屋です! この間一緒に飲んだ女子大生のMさん! 見てるー!? 約束通り書いたよー! 芋だって! 今度はジャーマンポテト食べにいこうか!」
「決まった! 明石×丑三弾(ダブル・シュート)!! 私事ですが担当・T屋も初彼女獲得秒読み(カウントダウン)状態です! 来週ご報告しますね!!」→その翌週:「ついに交わる『出席者』と『欠席者』! 空前の新展開スタート!! ※今週の担当・T屋ですが、プライベートな問題で本人が精神的に強く傷ついており、業務にあたれる状態でないため、お休みをいただきます」
マガジン愛読者にはお馴染みの個性的なアオリ文は、「神さまの言うとおり弐」のほかには、XのT屋氏アカウントでも同様のキャラが味わえる。一体どんなきっかけで、「担当・T屋」キャラは誕生したのだろうか。
「『神さまの言うとおり弐』が始まる際、先輩の編集といろいろ話していく中で、『編集者がアオリでわけわかんないこと言ったら面白いんじゃないか?』という話をしてくれました。そこからスタートして、『すごくモテると言っているが、実際はまったくモテてなくて、マンガそっちのけで自分の話してるヤツ』という、ある種のキャラができてきました。というのも、『神さまの言うとおり』は、デスゲームの中ではギャグっぽいテイストがある作品で、見る人によっては『人の命や死を茶化してる』みたいな見え方をしてしまうかもしれない。そのときに、怒りの矛先をこの“担当T屋”という架空のムカつくやつに向けてもらえばいいのではと。今で言う炎上商法というか、要は作品を守りつつ、話題にもなればいいなという思惑からスタートしました。
どうすればムカつかれるかを考えていく中で、ああいうキャラを作ってそのままTwitter (現X)も始めました。『ブルーロック』でも最初はそのキャラでやっていたんですけど、デスゲームとは相性がよかったと思うのですが、スポーツものでやると本当にただムカつくだけになっちゃったというか、うまくはまらなくて(笑)」
なんと、「担当・T屋」誕生の裏側には、編集者としての切実な思いが隠れていたのだ。
「『ブルーロック』は本当に読者にムカつかれているだけのような気がしたので、誰も何も得をしていないぞと反省し、今一旦やめています。一時期、Xで作品関連の投稿をリポストしたら、『こいつが担当ならこのマンガ読まない』と言われちゃったこともあるので、ジョークに受け取れない方には本当にムカついたと思うんですよ。担当作家さんたちはむしろ笑ってくれる人たちなので面白がってくれていたのですが、このキャラのせいで作品イメージに悪い影響が出るとよくないなとか思ってXの更新もやめているうちに、3年くらい経ってしまって。
素の僕はインタビューなどをしていただく機会もほとんどありません。当時、あのキャラでラジオとかテレビへの出演依頼も頂いたのですが、お断りしました。作品を取り上げて宣伝いただけるのであればありがたいのですが、自分にフォーカスがあたるのは苦手で。編集者は基本的には表に出ていくものではないと個人的には思っていて、ほかの編集者さんがやっているのはキラキラしてカッコよく見えるのですが、自分という編集者が表に出るのはカッコわるく思えてしまって嫌ですね(笑)」
作品との相性や変遷もあって、“T屋”からの供給が安定しないのはファンにとってはさみしいところだが、少なくとも作家からの愛されっぷりは、金城が2016年に描いた読み切り「担当・T屋物語~Yahoo! TOPの載り方~」でも確認することができる(マンガアプリ・マガポケで読める)。私たちはある意味、“担当・T屋”の手の平で踊る無邪気なピエロだったのかもしれないが、「ただ、ああいう部分が僕の中にもあるのかもしれないですね」と土屋氏は笑う──そして、注目を集めた分、過激なアンチも存在したようだ。
「ほとんどの方は楽しんでくれていたと信じているんですけど、お怒りの方からは犬の糞が送られてきたり、殺害予告とかも来ましたから(笑)。いろいろありましたが、作品の役に立てば表に出ていくこともあって、T屋はその形の1つだったと思っています。お嫌いだった方は、申し訳ありませんでした」
「よい少年マンガ」とは?
直接的な言い回しではないが、言葉の端々から、少年マンガへの深い愛がうかがえる土屋氏。かつて氏が述べていた「少年マンガ」の定義やそこにかける思いが味わい深いので、そのまま引用する。
「いつの時代でも誰の心にも響く少年漫画の特徴の1つは、『最後は必ず正義が勝つ』というものだと思っています。(…)どんな正義でも、仮に一般常識では悪いとされていることでも、あなたの思う正義が正解だと思います。描きたい『正義』をお持ちの方、ぜひお話を聞かせてください。その『正義』を貫いて、泣いたり笑ったり、時には死んじゃったりしながら、最後に勝つ主人公の物語を描くお手伝いができれば幸せです」(マンガ投稿サイト「DAYS NEO」のプロフィールより)
「あなたの思う正義が正解」とはっきり言い切っているのが新鮮だ。こうした考えに至った経緯を聞いた。
「きっかけは、僕が 6年目ぐらいのとき。自己分析ではあるのですが、僕って自分発信というより、作家さんの中にあるものを見つけて、それを企画にして描いていただくタイプの編集者かなと思っていて。でもそれでいいのだろうか?と、自分が編集者として全然優秀じゃないのではと悩んでいた時期がありました。同僚にはすごくやりたいことがあったり、めちゃくちゃマンガや文化に詳しかったり、『このジャンルなら俺に任せろ』みたいな人がいたりする中で『俺って無色透明な編集者だよな』みたいなことを思っていたんです。
そんな折、飲みの席である後輩に『土屋さんってめちゃくちゃ個性あると思いますよ』と言われて。えっ?と思って聞いたら、『この部署で一番少年マンガ好きですよ』と言われたんです。確かに僕はプライベートでもずっと少年マンガを読んでいる。そう気づかされたときに、改めて『少年マンガってなんだろう?』と考えたんです。引用していただいた文章もそのぐらいの時期くらいに書いたものですね」
そこからさらに、「いい少年マンガ」について深く考えるようになったという。
「個人的な見解ですが、『主人公が最初に思ったり、やりたいと志したことを、最終回まで絶対に変えないマンガ』だと思いました。当時の僕の言い方では最初のモチベーションのことを『正義』と言っていたんですが、今は第1希望とか、最初の悩み、初期衝動というほうが近いのかもしれない。
『ブルーロック』って突き詰めれば『ワールドカップで優勝する』という話なんですが、実はそれ自体は出来事というかすでにあるルールの中での勝敗であって、そこに思想はない。つまり『ただ勝ちたい』という気持ちって、第1希望とか初期衝動じゃないような気がするんですよ。
じゃあこのマンガの第1希望は何かというと、『世界一のエゴイストになる』のほうで、極端な話、最終回でワールドカップで優勝できなくても、世界一のエゴイストになっていたら読者はうれしいと思うんです。逆に、『俺はエゴイストじゃなくていい、ワールドカップで優勝する』という最終回だったら、多分面白くない。とはいえ、ワールドカップで優勝するほうを優先して、第1希望のエゴイストを捨てられるのって“大人”で、現実ではそっちに行くほうが多いと思う。だけど、少年マンガって夢を描くものだと思うので、じゃあ夢って何よと言うと、『第1希望を最後まで曲げずにいながら成功できる話』という感覚なんです」
主人公の「第1希望」を最後まで貫くのが「いい少年マンガ」。ただし、その第1希望が理にかなっていたり、立派であるかどうかは問わない。とてもエキサイティングな定義だ。
「作家さんがそんなことを言っているわけじゃないんですけど、僕はそここそが『ブルーロック』の“少年マンガ性”だと思っています。例えば、『もう一生勉強したくない!』って悩みから始まるマンガがあったら、主人公は一生勉強しないほうがいい。失礼ながら『売れてないな』と思うマンガって、主人公のモチベーションが『ワールドカップで優勝する』しかないんです。そうではなく『エゴイストになりたい』という第1希望があり、さらにその部分に、作家さん自身から引っ張ってきたものがあると、個性のあるいい少年マンガになるんじゃないかと思っています」
大人になってからの都合を優先せず、自分の中の少年性を無視しない。外の世界で何が起ころうと自分と向き合い続け、社会がどう自分を変えようとしても、自分を曲げない。これこそ、ロマンと言わずとしてなんと言おうか?
「でも、やっぱり難しいんです。話が長くなればなるほど、そこを曲げたほうがストーリーを考えるのが簡単で、違うことをやったほうが新鮮にも見える。もし『ブルーロック』の主人公が『俺はパスで世界一になる』とか言い出したら、その瞬間は意外で面白いかもしれない。でもそれだとちょっと“大人”だよね、という。
例えば、第1話で『俺は俺のボケで人を笑わせてM-1で優勝する!』という夢を持った主人公の物語があるとします。そのうち彼がボケ芸人としての限界にぶつかって、でもツッコミの才能に気づいて。それでもっと才能のある別の相方にボケを任せて、自分はツッコミに転向してM-1で優勝したとします。これも素敵な物語だし、現実でもあり得る立派な人生の選択ではあるのですが、やはりある種“大人”の判断なんですよ。
よい悪いの話ではないですが、あくまで少年マンガとしては『M-1で優勝する』より『ボケで人を笑わせる』のが第1希望なんです。それを一切曲げずに主人公が成功するのが少年マンガの持つ『夢』だと思うので、ボケで優勝しなきゃいけない。あるいは、夢を曲げてツッコミでM-1を優勝するリアルよりも、ずっと第1希望のボケを続けてM-1には出られなくても、全然お客さんのいない小さな劇場で1人のお客さんが初めて自分のボケで笑ってくれるというファンタジーのほうが、少年マンガのラストシーンとしてはふさわしいかもしれない。それが僕にとって『最後は必ず正義が勝つ』なんです」
だとすると、自分の中での「少年」を大事にするためには、どうすればいいのだろうか。自然の摂理で、編集者は言葉通りの意味での少年とは、年齢的にはどんどん離れていく。──「難しいですね」と悩みながらも答えてくれた。
「クサい言い方になりますが、正しいことや正しい価値観を思い出して、大事にする。『人に優しくしましょう』とか『ゴミをポイ捨てしない』とか、そういう誰でも昔から知ってた基本的なルールって実は子供より大人のほうが、大人になるにつれて守らなくなる。あのときとは違って今はこう考えている、という部分を大事にしちゃうようになるのが大人だと思うんです。
『昔はガキだったから、急に女の子に勢いで告白しちゃったけど、今は先に告るんじゃなくて最初に仲良くなろう』とか、大人になってから得た知見を優先しちゃいがちですが、それを大事にしないというか。うまく言えないのですが、小中学生のときに思っていたことを思い出して、『今の自分は間違ってる』って考えるようにしています(笑)」
天才を実感した「炎炎ノ消防隊」大久保篤の世界
さて、多種多様な作品を手がけた土屋氏に、「天才」を実感した瞬間を尋ねたところ、「めちゃくちゃいっぱいあるんで1個に絞れない」としつつも、「炎炎ノ消防隊」の大久保篤のエピソードを披露してくれた。
「『炎炎ノ消防隊』って、ざっくり言うとみんなが“太陽の神様”を信仰している、違う地球が舞台の話なんです。とあるお話で、お母さんが子供に対して『これ以上言うことを聞かないと、地下に連れてっちゃうよ!』みたいな叱り方をして子供が泣くシーンがあります。太陽を崇めている世界で、暗いところや太陽の光が届かない場所が怖いっていう価値観が子供たちの中にあるから、こうした脅し文句が成立する。
これって、その世界独自のリアルがないと出てこないセリフですよね。『おへそを隠さないと雷様に取られちゃうよ』みたいな、親がちょっと脅しを込めて子供を叱るって現実ではよくあることで、それをファンタジーにスライドさせるというやり方ですが、それをすっと出してきたときに、すごいな!と思ったことを思い出しました。
同時に、ファンタジーを描く人ってこれができないといけないという教訓として受け止めました。大久保さんはずっとその世界のことを考えているからでしょうけど、本当にさらっと出すんですよ。だから、ファンタジーの世界だけど、その人の中ではちゃんと『出来上がっている』。おそらく、マンガに描かれていないところまで考えられている。ファンタジーを1つの現実として描いているのを目の当たりにしたときに、改めてマンガ家ってすごいなと思いました」
そんな土屋氏にも、恒例の意地悪な質問をぶつけてみた。これまでの編集者仕事で失敗だったと思うことは?
「新人の頃、ベテランでかなり上の作家さんとお仕事をしたときに、前の打ち合わせで僕が指摘したことが直ってなかったのですが、『面白いです』って言っちゃった。その日はよかったんですが、後々作家さんにバレて『あのとき、嘘つきましたよね』と叱られたことがありました。相手が怖かったり、時間がなかったりで、『ダメです』とは言えなかったのですが、めちゃくちゃ怒られました(笑)。編集としては絶対しちゃいけないという意味でも、編集者らしい失敗でしたね』
野望は初版100万部
特に編集者にとって「その場しのぎ」は致命傷のようだ。時は流れ、編集者歴12年、押しも押されぬ中堅編集者となった現在の土屋氏の野望は、「初版100万部」。
「作品の絶対数も増えて大変な時代ですが、少年マンガっていっぱい売れなきゃいけないジャンルだと思ってるので、初版100万部の作品を作ってみたいです。もちろん、部数だけがすべてではないのですが、野望としては。もちろん、200でも300でもいいんですけど(笑)」
外から見れば、十分すぎるほど人気作を手がけてきたように思える土屋氏の夢は、天井知らずだ。そしてこんな土屋氏をもってしても、「ヒットする作品の条件」は謎だという。
「いくつか思うところはあって、1つは『個性の強いキャラがいっぱい出ていること』。キャラが弱くて売れるマンガってないと思う。あとは僕の中では、新しさとメジャーが一緒になっていることだと思います。さらにその新しさが、作家さんがやりたいこと、作家さんの中から出てきたものだとなおよいですよね。だから一言で言うと、『作家さんがやりたい新しいことをメジャーに描いているもの』じゃないかなと。斬新と言われて売れている作品でも、分解してみるとすごくメジャーなことをやっていたりするので」
確かに、マンガに限らず自分の好きな作品を思い返してみたところ、「懐かしいのに新しい」という感覚が蘇ることに驚いた。
「逆に王道って言われているものでも、よく読んでみると新しさか作家さんのフェチが入っていると思う。新しいこととメジャーなこと、どちらかだけで大ヒットすることは難しい気がしています」
編集者の心得は自己開示と「感情のストックを」
少年マンガにかける熱く純粋な気持ちと、冷静な分析能力。2つを併せ持つ土屋氏が思う「編集者の心得」の1つは、やはり「自己開示」。
「編集者になってみてわかったのですが、本当に、なんでもマンガのネタになる。月並みですが、いろんなことを経験してそれを話せる人がいいような気がします。ただこれ、海外旅行しろとか起業しろとか大きいこと、立派なことをしろという意味じゃなくて、なんでもいいんです。バイトして1日でやめたっていいし、実家に住んでいる方はお皿洗いして家事を手伝うとか、小さいことでもいいのでいろいろ経験してくださいという意味です。
さらに、体験したときの感情の話ができるといいですよね。『動物園で象さんを見ました。大きかったです』じゃなくて、象を見てこう思いましたとか、見ている子供が意外とニコニコしているだけじゃなくて怖がっている子もいるのに驚いたとか。経験するだけじゃなくて、そこで思ったことを話せたほうがいいと思います」
経験がネタになるのは作家の専売特許だと思われがちだが、編集者の場合も鬼に金棒だ。
「感情のストックもあったほうがいいですよね。打ち合わせでも、ここでキャラクター2人が喧嘩しているのは、中学生が些細なことで喧嘩しているのと感情は一緒ですよね、みたいな話をよくします。ファンタジーで、自分よりも弱かった奴がドラゴンを倒しちゃったときの気持ちって、期末試験で馬鹿にしていたやつに抜かれるのと一緒ですよね、となると途端にリアルに描ける、みたいな。そういう感情の連想や変換ができたほうが、描写のもとになる。いろんな感情のストックを、作家さんの脳みそだけじゃなくて編集もちょっとでも手伝えると、共有できる感情の数が増えるという意味でいいと思います。つまりは、いろんなことをしていろいろ思っておくのがいいんじゃないかな」
土屋氏が子供の頃、マンガをたくさん読んでも人とは感想や感情を共有せず、1人の世界で完結していたことを考えると、この変化には隔世の感がある。時が積み重なり、熟したということだ。
「確かに、言われてみれば(笑)。本当は聞いてほしいのかもしれない。僕、『空気が読めない』とか『しゃしゃってる(しゃしゃり出ている)』って思われるのがすごい嫌なんですよ。なので、あえて外に出て目立ったりもしたくないんですけど、本当はすごく話したいのかもしれないです」
土屋萌(ツチヤメグム)
1987年、神奈川県出身。2012年に講談社に入社し、週刊少年マガジン編集部に配属される。主な担当作品に、金城宗幸・藤村緋ニ「神さまの言うとおり」、鈴木央「七つの大罪」、荒川弘・田中芳樹「アルスラーン戦記」、大久保篤「炎炎ノ消防隊」、猪ノ谷言葉「ランウェイで笑って」、金城宗幸・ノ村優介「ブルーロック」、裏那圭・晏童秀吉「ガチアクタ」など多数。
(コミックナタリー)
 ERR_MNG
ERR_MNG