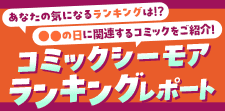ネタバレ・感想あり【合本版 第一部】本好きの下剋上(全3巻)のレビュー




 (4.9)
21件
(4.9)
21件





(5)
18件





(4)
3件





(3)
0件





(2)
0件





(1)
0件
 ERR_MNG
ERR_MNG