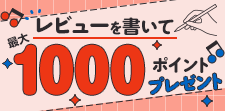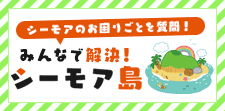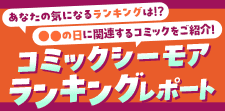ネタバレ・感想あり新編 鳥島漂着物語 18世紀庶民の無人島体験のレビュー




 (5.0)
1件
(5.0)
1件





(5)
1件





(4)
0件





(3)
0件





(2)
0件





(1)
0件
 ERR_MNG
ERR_MNG