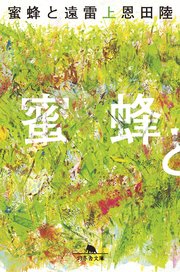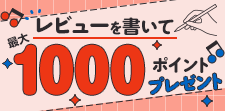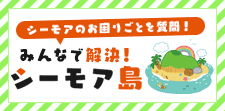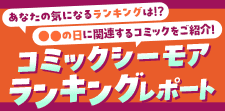言葉が音楽のように弾けて押し寄せて波打つ





圧倒的な言葉数で、畳み掛けるような(英語スピーチのような)三連続表現や、効果的な言い換えが頻繁になされる。どれだけの音楽関連の語を我が物にし自在に操ってるんだろうかと驚嘆する。豊富な音楽知識が駆使されながら、会話が自然でリアル。しかし描かれているのは天才達であり、あり得ないレベルの才能の競演。巡り合せ。著者の要所要所の音楽評論を読まされているかの分析的用語遣いに、音楽物の話を作るに当たっての相当なこだわりを感じ、尚且つ専門用語でけむに巻かないエンタメ要素充実、一般の読者目線を忘れない。登場人物達が考え感じ取り影響し合う天才群像。彼らがコンクールを通じて更なる進化を遂げ、立ち止まっていた者の脱皮?の姿が描かれる。それを目撃する興奮がよく伝わる。作者自身の考えや思いを登場人物達にあらゆる角度から言わせた感じ。その思いや表現に納得がいくものだから、ストーリーはドキュメンタリーのよう。
コンクール物というと音楽物の名作漫画「ピアノの森」を思い出さないわけにはいかない。恐らく両作者互いに読んだだろう、と思わせる。
今年11月、モデルの浜松国際ピアノコンクール(3年おき開催)はコロナで中止となった。俄然興味が高まったのに。
その代わりに読む気持ちで本作の季節にもダブらせて読んだ。
まだ下巻の途中。追記予定。
以下追記。
本選の場面はYouTubeでラフ2を聴きながら(ここ辻井伸行氏。この曲は生で聴いてないので、読んだらコンサートに行きたくなった。次いで角野隼人氏グランプリ動画も初めて聴いて想像力の材料にさせて貰った)読んだ。他の曲も聴いたが同時に読むのはこの曲が私には適していた。
結果よりもプロセス、みたいな感じで最後は大フィナーレという過剰演出がなくていい。が、途中、材料多めのあれもこれもの、こってりメニューを感じた。だから、スルッと終わって却って私は読後のもたれ感をなくしてくれたこの行方の示し方、歓迎。
羽音が戻ってきて終了。
それにしてもマサル、弾きながらあれだけ考えるとは、いくら天才肌でも、小説は創作物であると再認識。練習時間確保が難しかったはずの風間塵もしかり。
栄伝亜夜に至っては、「進化」が語られた割には、この数日間の成長は、他のコンテスタント等の描写に割かれた分、感じにくかった。
 いいね
いいね
-
 マンボー さん
マンボー さん(男性/50代) 総レビュー数:2462件
-
 アヲアラシ さん
アヲアラシ さん(女性/-) 総レビュー数:100件
-
 みう さん
みう さん(-/-) 総レビュー数:207件
-
 MW さん
MW さん(女性/-) 総レビュー数:3184件
-
 romance2 さん
romance2 さん(女性/60代~) 総レビュー数:1852件
 ERR_MNG
ERR_MNG