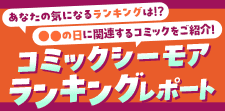ネタバレ・感想ありおひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中! 【連載版】のレビュー




 (4.6)
4564件
(4.6)
4564件





(5)
3347件





(4)
853件





(3)
258件





(2)
71件





(1)
35件
 ERR_MNG
ERR_MNG