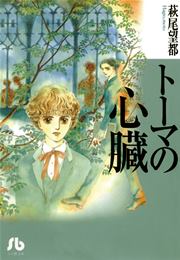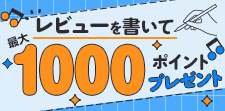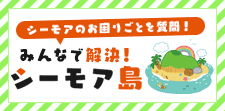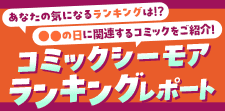彼がぼくを愛さなければならないのだ





トーマはユーリに遺書を書いて死んだ。彼はユーリの関心を、愛を、乞うた。ユーリは茶番と言いながら、自らトーマという「よい種」にひかれる自分の感情に気づいていた。一方「わるい種」は、信仰という踏み絵にかけてユーリを屈服させていた。ユーリが進路を決意する流れに、苦しみの先にある彼の答えとはそれなのか、と私は愕然とする。
愛せるか愛せないかではなく、愛していた。そして憎み避けて否定した。
トーマは、悪魔の招待の実態まではわからなくても、ユーリの苦悩を見ていた。見つめていたから。遺書は続く。「今、彼は死んでいるも同然だ。/そして彼を生かすために/ぼくはからだが打ちくずれるのなんか なんとも思わない」
少年愛漫画のパイオニア、今隆盛誇る BLの萌芽はこの辺りからと言えるだろう。(竹宮惠子先生の「風と木の詩」の発表年は本作の数年後。) 男子校寮生活という、女性読者層の嗜好の大票田の今日の一大ジャンルの隆盛は、此処から全てが始まったと私は思っている。(11月のギムナジウムがあったか!追記)
後世の作家が足許に及ばぬ説き伏せ方、淡い夢を見ているような筆致に敬服。ファンタジックなドイツの男子校物語が研ぎ澄まされた先生の言葉で紡がれて、詩情豊かに彼らの日々が表現されていく。萩尾先生の世界は安易な追随を許さず、ふわふわ別世界に連れ出し、なぜだか妙に生き生きしたリアルも感じる不思議。
心臓の音、これはしかし私には伝わらなかった。トーマは心臓を差し出し、ユーリは自らの選択に一個の結論を求めた。それは彼がトーマの望み通りとなったことを意味するのだろうか。
感覚的にこの世界観を認識し、彼らのロジックを登場人物の思考によって納得する。言葉が飛び出していて元気で、萩尾先生の言葉と憂いある絵で物語が動く。エーリクが何度もこのストーリーを救う。オスカーは、彼なりに働いているのだけれども、ユーリをフォローはしているのだけれども、エーリクの出現が彼らの世界には決定打だった。トーマが心の重石を置いたとすれば、やはり、エーリクがユーリを軽くしたと私は思う。翼を引きちぎ「られ」たのではなかった。望んで飛び込んだ、という苦悩、代償。彼がユーリを飛び立たせることになったと思える。しかしそれは大空ではなく、内省深める道へ。私はやはり、つけ込んだサイフリートが軽く済んでいる事に複雑な気分だ。
 いいね
いいね
-
 rsmcan1676 さん
rsmcan1676 さん(-/-) 総レビュー数:36件
-
 lviv さん
lviv さん(-/-) 総レビュー数:3172件
-
 みう さん
みう さん(-/-) 総レビュー数:217件
-
 romance2 さん
romance2 さん(女性/60代~) 総レビュー数:1852件
-
 MW さん
MW さん(女性/-) 総レビュー数:3278件
 ERR_MNG
ERR_MNG