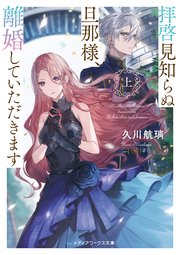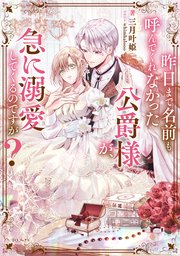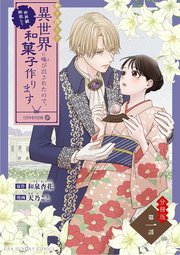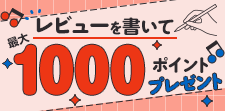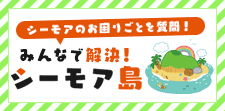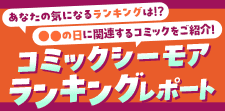レビュー
今月(11月1日~11月30日)
レビュー数0件
いいねGET4件
シーモア島
 ベストアンサー0件
ベストアンサー0件
 いいね0件
いいね0件
投稿レビュー
-
-
-
-
-
聖女の姉ですが、宰相閣下は無能な妹より私がお好きなようですよ?
学びの意味



 2024年10月24日異世界に転生した主人公が「前世の知識を使って」等というとき、活用されるのは日常生活に即したものだったりします。それも大切な知識です。しかし本作で主人公が活用するのは、私たちが受験のためにと学校で学ぶ知識です。よく、学校で学ぶのは「私」の将来のためだといわれます。それもほんとうです。しかし、もっと大切なのは学んだ知識は「私たち」の間違いに気づかせ、自分だけでなく、社会や大切な人を守るための武器となり、盾となるということです。
2024年10月24日異世界に転生した主人公が「前世の知識を使って」等というとき、活用されるのは日常生活に即したものだったりします。それも大切な知識です。しかし本作で主人公が活用するのは、私たちが受験のためにと学校で学ぶ知識です。よく、学校で学ぶのは「私」の将来のためだといわれます。それもほんとうです。しかし、もっと大切なのは学んだ知識は「私たち」の間違いに気づかせ、自分だけでなく、社会や大切な人を守るための武器となり、盾となるということです。
表面化する様々な問題は気付きがなければ解決には至らず、問題の経過と根本にある原因への推測には知識が必要です。そして多くの人が知識を身に付けることで多様な視点が生まれ、各々の角度から事象をとらえ、誰かが問題に気づく可能性が高まる。さらに未来について予測ができる。残念ながら「私たち」は時として間違う。しかし、誰かが間違いを指摘できれば修正は可能です。それは専門家だけにまかせておいては十分に機能しません。
また、知識なくして考察を深めることはできず、知識の豊富さが思考の深さに比例します。だからどれだけネット上に情報が溢れ、AI が発展しようとも私たちが学ぶことの重要性は変わらない。人は考える葦であるといいますが、考えるためには知識が必要だということです。そんな当たり前なことについて改めて考えるきっかけとなりました。
主人公の性格はちょっと…なんですが、知性と知識を活用して問題を解決していく姿は爽快でした。タイトルは損しているように思います。 -
-
 ERR_MNG
ERR_MNG