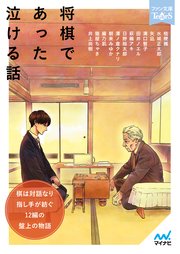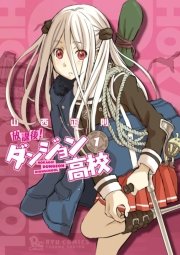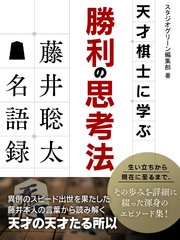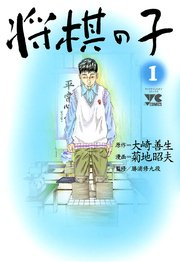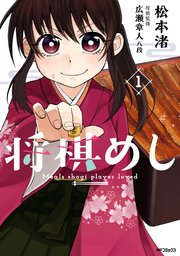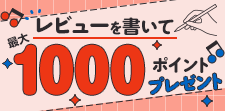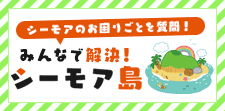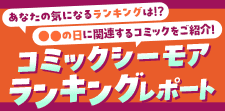フォロー
0
フォロワー
0
総レビュー数
7
いいねGET
6
いいね
0
レビュー
今月(11月1日~11月30日)
レビュー数0件
いいねGET0件
シーモア島
 ベストアンサー0件
ベストアンサー0件
 いいね0件
いいね0件
投稿レビュー
-
「藤井聡太の師匠」にとどまらない奥行き




 2023年6月16日杉本先生は一般棋戦準優勝や、故原田先生「48歳の抵抗」を想起させる昇級など、超一流とは客観的に言えないまでも(失礼)マイノリティの振り飛車党としては御三家(藤井猛、鈴木大、久保先生)に並ぶ、また故村山聖先生をして「正統派の振り飛車は杉本さんだけ」と言わしめたほどの棋士。
2023年6月16日杉本先生は一般棋戦準優勝や、故原田先生「48歳の抵抗」を想起させる昇級など、超一流とは客観的に言えないまでも(失礼)マイノリティの振り飛車党としては御三家(藤井猛、鈴木大、久保先生)に並ぶ、また故村山聖先生をして「正統派の振り飛車は杉本さんだけ」と言わしめたほどの棋士。
インタビュー記事や動画、単発のエッセイはずっと拝読拝見していましたが、ここまで文才がおありとは、恐縮ながら目からウロコが落ちるおもいでした。
とにかく軽快で、粘りの棋風なのに文章が捌けまくっている。
いわば、先崎先生の歩調、故河口老師の手厚さ(観察眼)、北野さんのエモさ、大川さんの取材力、ごとげんさんの真摯さ、なんなら三象子、陣太鼓、銀遊子、倉島さんなどまで思い起こすような多様多彩な角度。
主観と客観を軽妙に飛び交う、現役棋士ならではの視座もたいへんおもしろく拝読しました。名著すぎます。ペンクラブ大賞、わたしが審査員ならまちがいなく一推しです。 -
-
-
-
作者の将棋愛がすごい




 2017年1月31日主人公が女性棋士でタイトルホルダー、というのは荒唐無稽までいかずとも現時点ではファンタジーに近いが、女流棋士や奨励会員では将棋界の「めし的あるある」(タイトル戦、順位戦など)が描きづらいので、ここは設定として素直に受け入れたい。
2017年1月31日主人公が女性棋士でタイトルホルダー、というのは荒唐無稽までいかずとも現時点ではファンタジーに近いが、女流棋士や奨励会員では将棋界の「めし的あるある」(タイトル戦、順位戦など)が描きづらいので、ここは設定として素直に受け入れたい。
さて、「将棋めし」というタイトルではあるが、「将棋(と)めし」ではなく、めしはあくまで棋士や棋界を語るうえでの味つけ、ダシとして使われている印象。むしろ女性棋士・女流棋士問題をはじめ、作者の徹底した将棋愛がひしひしと伝わってくるので、純粋なグルメ漫画として読みたい人間や棋界にまったく興味がない層には少々肩透かし感があるかもしれない。
ひとことで言っちゃえば「作者が将棋のことを書きたくて書きたくてしょうがなくて、でもそれ単体だと連載できなさそうだからめしを絡めたのではないかしら」という作品。
ただし、将棋もめしも好きだ、というわたしはたいへんおもしろく読めました。棋士のエピソードなど小ネタの宝庫でもあるので、何度も読み返せる多角的、多面的な漫画だとおもいます。
 ERR_MNG
ERR_MNG