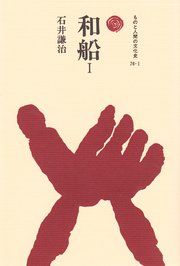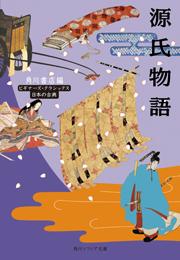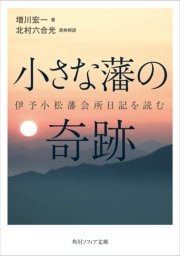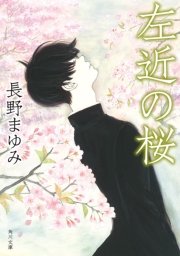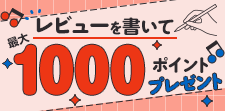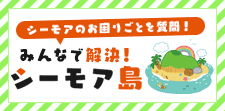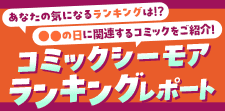レビュー
今月(11月1日~11月30日)
レビュー数0件
いいねGET0件
シーモア島
 ベストアンサー0件
ベストアンサー0件
 いいね3件
いいね3件
投稿レビュー
-
快作! 今川氏真のイメージが変わった。




 2025年4月20日今川氏真。私の脳裏に真っ先に浮かぶのは『信長の忍び』に出てくる蹴鞠バカ息子……だったのだけど、この作品の氏真さんは美しい!特に蹴鞠姿がめちゃくちゃ良い。この作品でも従来のイメージ通り「蹴鞠好きで、戦国大名としてはダメダメ」なのだけど、鞠職人五助の目線で描かれる氏真は、なんとも美しく哀しい。よくぞこんな物語を作ってくださったと感動するし、幾花にいろさんの絵も良い、上手い。今後もこの作家の歴史物を読みたい。ただ蘊蓄好きの個人としては、せっかく鞠職人という珍しい素材を扱うのだからその世界についてもうちょっと知りたかった気もする。蹴鞠についてもルールとか。
2025年4月20日今川氏真。私の脳裏に真っ先に浮かぶのは『信長の忍び』に出てくる蹴鞠バカ息子……だったのだけど、この作品の氏真さんは美しい!特に蹴鞠姿がめちゃくちゃ良い。この作品でも従来のイメージ通り「蹴鞠好きで、戦国大名としてはダメダメ」なのだけど、鞠職人五助の目線で描かれる氏真は、なんとも美しく哀しい。よくぞこんな物語を作ってくださったと感動するし、幾花にいろさんの絵も良い、上手い。今後もこの作家の歴史物を読みたい。ただ蘊蓄好きの個人としては、せっかく鞠職人という珍しい素材を扱うのだからその世界についてもうちょっと知りたかった気もする。蹴鞠についてもルールとか。
読後には、高々と蹴り上げられた鞠を見上げる時、視界いっぱいに広がる空のような清しさと寂しさが残る。地べたを奪い合う戦国武者たちとはまったく相容れないからこそ、氏真さんは氏真さんとしてかっこいいのだ、そう思うようになった。 -
続きが読みたい




 2024年7月4日子どもたちの天真爛漫さと、旅で出会う大人たちの懐の深さ。風景描写も上手いなぁ。作者さんの取材記もなかなか良いです。子供だけの抜け参りなんてありえない、と思うかもしれませんが、実際あったようです。何かの本で目にしたことがあります。おはなしは途中までですが、いちと十さまは伊勢までたどり着き、さらに無事江戸まで帰りつき、おまけに犬五郎も家へ帰れたと信じております。うーん、でも続き読みたいなあ。
2024年7月4日子どもたちの天真爛漫さと、旅で出会う大人たちの懐の深さ。風景描写も上手いなぁ。作者さんの取材記もなかなか良いです。子供だけの抜け参りなんてありえない、と思うかもしれませんが、実際あったようです。何かの本で目にしたことがあります。おはなしは途中までですが、いちと十さまは伊勢までたどり着き、さらに無事江戸まで帰りつき、おまけに犬五郎も家へ帰れたと信じております。うーん、でも続き読みたいなあ。 いいね
0件
いいね
0件 -
これぞ、まさに〈江戸〉だとおもう




 2024年6月29日江戸人が描いた江戸=浮世絵の中から今の世に生まれてきたかのような珠玉の作品集。わたしはこういうのが江戸らしいと思うんですよね。粋で清しく軽やかで…。杉浦日向子さんがこの路線の大先達。わたしも大ファンな訳ですが、漫画はまったく電子化されてないので、常々さみしいと感じておりました。この作家さんに巡り合えてよかった!絵柄は浮世絵っぽい(というかそのもの)なのに違和感を感じないのは、よくこなれているからなのでしょうね。ご自身の血肉になるまで江戸文化を愛しているんだろうとおもいました。シンプルなようでこだわりは深い。時代ごとに変化する髪型(男髷も時代と職業で変わる)、特に感心したのは着物の柄、100%じゃないけど手描きです。これトーンだったら台無しなんだよね。ひさしぶりに超イイ江戸もの漫画読めて幸せです。ものすごいストーリーとかエモさとかではないけど、私は粋とか俳味と呼んでいい魅力じゃないかとおもう。
2024年6月29日江戸人が描いた江戸=浮世絵の中から今の世に生まれてきたかのような珠玉の作品集。わたしはこういうのが江戸らしいと思うんですよね。粋で清しく軽やかで…。杉浦日向子さんがこの路線の大先達。わたしも大ファンな訳ですが、漫画はまったく電子化されてないので、常々さみしいと感じておりました。この作家さんに巡り合えてよかった!絵柄は浮世絵っぽい(というかそのもの)なのに違和感を感じないのは、よくこなれているからなのでしょうね。ご自身の血肉になるまで江戸文化を愛しているんだろうとおもいました。シンプルなようでこだわりは深い。時代ごとに変化する髪型(男髷も時代と職業で変わる)、特に感心したのは着物の柄、100%じゃないけど手描きです。これトーンだったら台無しなんだよね。ひさしぶりに超イイ江戸もの漫画読めて幸せです。ものすごいストーリーとかエモさとかではないけど、私は粋とか俳味と呼んでいい魅力じゃないかとおもう。 いいね
0件
いいね
0件 -
読みやすくて面白かったので一気読み




 2024年6月19日小学校中高学年でもわかりやすいように、やさしい表現で書いてくださっているので大変読みやすかったです。私は多少発掘などに興味があるのですが、新宿区市谷の遺跡から縄文人骨が十体も出たなんて、この本で初めて知ってびっくりしました。しかもミトコンドリアDNAも判定できて、さらにそのうち一体はハプロタイプがA(この本によると、ハプロタイプAはシベリアのあたりにルーツを持つ人々らしく)ビックリしました。まあこの一例だけではなんとも言えないでしょうが、様々な可能性を想像したくなります。面白い!
2024年6月19日小学校中高学年でもわかりやすいように、やさしい表現で書いてくださっているので大変読みやすかったです。私は多少発掘などに興味があるのですが、新宿区市谷の遺跡から縄文人骨が十体も出たなんて、この本で初めて知ってびっくりしました。しかもミトコンドリアDNAも判定できて、さらにそのうち一体はハプロタイプがA(この本によると、ハプロタイプAはシベリアのあたりにルーツを持つ人々らしく)ビックリしました。まあこの一例だけではなんとも言えないでしょうが、様々な可能性を想像したくなります。面白い!
私はたまたま、このミトコンドリアDNA分析をされた国立科学博物館の篠田謙一先生の『江戸の骨は語る』というご著書を数か月前に読んでいまして、こちらは文京区のキリシタン屋敷跡地から発掘された江戸時代の三体の人骨調査について書かれたもの。うち一体は江戸時代日本へ来た最後の宣教師・シドッチであろう、と結論が出て、この人骨さんも復顔と展示までされたようです。こちらのほうがミトコンドリアDNAの分析についてより詳しく書かれているのでハプロタイプとか、発掘人骨の復元・復顔などについても「もうちょっと知りたい」方は是非どうぞ。
いやあ、しかし、ホントに、なんで新宿区から縄文人骨出るかな~?不思議過ぎる。 いいね
0件
いいね
0件 -
子ども家老 元八郎がかわいい




 2024年1月12日『つらつらわらじ』の物語が始まる2年前、12歳でご家老様になった日木元八郎。
2024年1月12日『つらつらわらじ』の物語が始まる2年前、12歳でご家老様になった日木元八郎。
頑張って、転んで泣いて、起き上がったときにはちょっと成長している。微笑ましいショートストーリー。『つらつらわらじ』を読んでからこちらを読むと「ああ、殿といっしょに行きたかったよねぇ」と元八郎への共感が倍増するのでおすすめです。 いいね
0件
いいね
0件 -
短く分かりやすい解説




 2023年11月26日雑賀衆ってどういう人たちなんだろう、を調べたくて購入。雑誌に掲載された一つの記事ということで、すごーく大雑把な内容になるのはしかたないが、分かりやすくまとまっているのではないかと思う。詳しいことを知りたいなら、ここからキーワードを拾い出して調べれば良い、その足掛かりには充分なる。まったく知識のない私にも根来衆との違いなどよく理解できたし、石山本願寺、時の権力者との関係もざっくり分かった。
2023年11月26日雑賀衆ってどういう人たちなんだろう、を調べたくて購入。雑誌に掲載された一つの記事ということで、すごーく大雑把な内容になるのはしかたないが、分かりやすくまとまっているのではないかと思う。詳しいことを知りたいなら、ここからキーワードを拾い出して調べれば良い、その足掛かりには充分なる。まったく知識のない私にも根来衆との違いなどよく理解できたし、石山本願寺、時の権力者との関係もざっくり分かった。 いいね
0件
いいね
0件 -
読む前に思っていた以上に面白かった




 2023年10月17日現代においては、もはや民俗学の新研究など不可能なんじゃないかと思ってしまうほど、世の中は変化し多くのものが消えた。
2023年10月17日現代においては、もはや民俗学の新研究など不可能なんじゃないかと思ってしまうほど、世の中は変化し多くのものが消えた。
本の電子化により民俗学の本もどんどん消えているなか、この本の内容は1985年のものだが、だからこそ面白い。個人的に、民俗学的なものを肌身で感じられた或いは記憶していたギリギリの時代じゃないかとおもうのだ。もともと民俗学の本は古いほど良いとおもっている。
内容は広く浅く読みやすい。語られた歴史の裏側に消えた人々、支配者にまつろわぬ人々の住む世界を「闇」住人を「鬼」と呼び、それらを概観する。深く突っ込んだ内容ではないが、取り上げた話題は多い。興味深いものもずいぶんあった。ひとつあげると、内藤さんの「東海道五十三次呪術装置説」は初めて聞いた。検証したわけではないが面白いとおもった。
「闇」は同時に他界のことも指している。光ばかりが溢れるようになり闇が消えたからこそ人々が「闇」を求めているのだ、という小松さんの言葉はそのとおりだとおもう。多くの本が消えてゆく時勢にあって、小松さんの本が生き残っている理由でもあるだろう。 いいね
0件
いいね
0件 -
女・謙信アリかも!




 2022年12月25日まず各巻の表紙の虎さまがあまりに美しく、惹かれてしまいました。上杉謙信は女だった?という驚きの設定ながら、想像以上にガッツリ「史実(といわれるもの)」を手玉に取る堂々たるストーリー。おもしろかった~どうして大河ドラマにならないの?
2022年12月25日まず各巻の表紙の虎さまがあまりに美しく、惹かれてしまいました。上杉謙信は女だった?という驚きの設定ながら、想像以上にガッツリ「史実(といわれるもの)」を手玉に取る堂々たるストーリー。おもしろかった~どうして大河ドラマにならないの?
例えば女城主はありそうだけど、守護代とか関東管領とか「官職」はさすがに女じゃなれないだろーと思っていましたがまあまあ納得。いやむしろ、それがあったから女であることを公にはできなかったのか、謙信さんのシンボル僧兵みたいな白頭巾も女であることを隠すためか?などと、「これは案外謙信女説、アリだな」と思いました。先生、また歴史もの描いてください楽しみに待ってます。 いいね
0件
いいね
0件 -
-
三度生まれ変わった本




 2022年4月5日著者が、主に山小屋主人たちに聞いた山の実話。最初は雑誌連載、それが単行本となり、出版社を山と渓谷社に変え「新編」として復活、さらに「定本」として文庫化。四回生まれた本だ。同時に読んでいる『山の霊力』町田宗鳳(山と渓谷社)に山の神の最も古い形はオロチ信仰だとあって「なるほどなぁ」と思ったのだが、さしずめ本作も脱皮して生まれ変わる山の神、山の生命力が宿っているのではないだろうか。あとがきに「ミステリーじゃない」と言われたこともあると書かれているが、刺激的な怪談を求める人には物足りないかもしれない。しかし、毎年数多の怪談本が生まれては消える業界にあって、三度生まれ変わって(脱皮して)生き残っているこの本には、それなりの魅力と力があるのでは、と思う。
2022年4月5日著者が、主に山小屋主人たちに聞いた山の実話。最初は雑誌連載、それが単行本となり、出版社を山と渓谷社に変え「新編」として復活、さらに「定本」として文庫化。四回生まれた本だ。同時に読んでいる『山の霊力』町田宗鳳(山と渓谷社)に山の神の最も古い形はオロチ信仰だとあって「なるほどなぁ」と思ったのだが、さしずめ本作も脱皮して生まれ変わる山の神、山の生命力が宿っているのではないだろうか。あとがきに「ミステリーじゃない」と言われたこともあると書かれているが、刺激的な怪談を求める人には物足りないかもしれない。しかし、毎年数多の怪談本が生まれては消える業界にあって、三度生まれ変わって(脱皮して)生き残っているこの本には、それなりの魅力と力があるのでは、と思う。 いいね
0件
いいね
0件 -
分かりやすい入門書




 2022年3月26日敷居が高いかな、と思いながら読み始めたが、予備知識がない私にもすんなり理解できる内容だった。日本史上に現れるさまざまな海上勢力について一通り触れられている。もっと突っ込んだものを読みたい方は、巻末の文献一覧も参考になると思う。日本史上の「海賊」が、単なる「賊」ではないが、なんとなく捉えどころが無いようにおもうのは、様々な顔を持ち、その活動範囲が陸上とは比べものにならない広範にわたるからかもしれない。本書のようにその活動を概観できる本はありがたい。熊野海賊が鹿児島へ攻め入ったり、伊勢の勢力が武田氏に雇われて駿河湾・江戸湾で活躍したり、遣明船の警固などは今の東シナ海にまで及んだのだろうか。興味がそそられる。
2022年3月26日敷居が高いかな、と思いながら読み始めたが、予備知識がない私にもすんなり理解できる内容だった。日本史上に現れるさまざまな海上勢力について一通り触れられている。もっと突っ込んだものを読みたい方は、巻末の文献一覧も参考になると思う。日本史上の「海賊」が、単なる「賊」ではないが、なんとなく捉えどころが無いようにおもうのは、様々な顔を持ち、その活動範囲が陸上とは比べものにならない広範にわたるからかもしれない。本書のようにその活動を概観できる本はありがたい。熊野海賊が鹿児島へ攻め入ったり、伊勢の勢力が武田氏に雇われて駿河湾・江戸湾で活躍したり、遣明船の警固などは今の東シナ海にまで及んだのだろうか。興味がそそられる。 いいね
0件
いいね
0件 -
美しい物語




 2022年3月20日原作は未読だが、これはこれとして近藤ようこでなければ描けない作品だとおもう。郎女が俤人を追い求め、当麻曼荼羅を作り上げる筋立てを経糸に、彼女を取り巻く人々(生者・死者)を緯糸に、織り上げた美しい曼荼羅。そこに描き出された世界は彼女の魂の清らかさ、豊かさに見える。これを読んだら久しぶりに当麻曼荼羅(本当は浄土変相図とかいうらしい)を拝見したくなった。もう何十年も前に當麻寺で拝観し、惚れた。折口信夫の原作は昭和14年というが、執筆中はまだこれが綴れ織りであると判明していなかったのだろうと想像する。絵画なのか、織物なのか、染物なのかすら以前は謎だったらしい。そんな謎めいた存在性が原作の源泉になったのでは、と思う。読後、色々検索して、本作で主人公は単に「郎女」と呼ばれているが、伝説では「中将姫」だったと気づいてしまった。私くらいのおばばだと中将湯の箱に描かれたお姫様の顔がすぐ思い浮かぶ。そのギャップに、ちょっと感動が薄れてしまったが、本作は間違いなく名作。
2022年3月20日原作は未読だが、これはこれとして近藤ようこでなければ描けない作品だとおもう。郎女が俤人を追い求め、当麻曼荼羅を作り上げる筋立てを経糸に、彼女を取り巻く人々(生者・死者)を緯糸に、織り上げた美しい曼荼羅。そこに描き出された世界は彼女の魂の清らかさ、豊かさに見える。これを読んだら久しぶりに当麻曼荼羅(本当は浄土変相図とかいうらしい)を拝見したくなった。もう何十年も前に當麻寺で拝観し、惚れた。折口信夫の原作は昭和14年というが、執筆中はまだこれが綴れ織りであると判明していなかったのだろうと想像する。絵画なのか、織物なのか、染物なのかすら以前は謎だったらしい。そんな謎めいた存在性が原作の源泉になったのでは、と思う。読後、色々検索して、本作で主人公は単に「郎女」と呼ばれているが、伝説では「中将姫」だったと気づいてしまった。私くらいのおばばだと中将湯の箱に描かれたお姫様の顔がすぐ思い浮かぶ。そのギャップに、ちょっと感動が薄れてしまったが、本作は間違いなく名作。 -
怪談話ではありません、気持ち良い本です。




 2022年3月5日出版社・ヤマケイさんは『山怪』シリーズとか、山の不思議なお話を集めた本を多く出しておられるので、その筋なのかと思うと、ちょっと違う。たしかに著者が「異界」に、その住人に出会ったあれこれを語っている不思議なお話なのだが、それは紛れもなく著者の個人的実体験であり「現実」だからなのだろう。著者の言う「異界」は我々が住むこの三次元的現実と重なっている。シャーマニックな能力を持たない一般人でも、実は無意識ではこれらの「異界」を体験しているのではないかと思う。読みながら明るく広やかな感覚に包まれた。きっと著者の人柄が、そんな方なのだろう。
2022年3月5日出版社・ヤマケイさんは『山怪』シリーズとか、山の不思議なお話を集めた本を多く出しておられるので、その筋なのかと思うと、ちょっと違う。たしかに著者が「異界」に、その住人に出会ったあれこれを語っている不思議なお話なのだが、それは紛れもなく著者の個人的実体験であり「現実」だからなのだろう。著者の言う「異界」は我々が住むこの三次元的現実と重なっている。シャーマニックな能力を持たない一般人でも、実は無意識ではこれらの「異界」を体験しているのではないかと思う。読みながら明るく広やかな感覚に包まれた。きっと著者の人柄が、そんな方なのだろう。 いいね
0件
いいね
0件 -
江戸藩邸というテーマがこんなに面白いとは




 2022年3月3日著者・氏家幹人氏の最初の本だそうな。曰く、その後の自分の興味がほとんど入っている、とのことだが、確かにそう見える。「江戸藩邸」なんて堅苦しくて面白くなさそう、と早合点してはいけない。江戸藩邸は各藩の大使館のような存在で、軍事要塞的性格も持っている。秘密の江戸のディープスポットだ。その内側で繰り広げられる人間臭い有象無象が、氏家流に語られる。各章のテーマはバラバラのように見えるのだが、全体を通して、江戸藩邸が江戸時代260年の間にどう変化し、どのような役割を演じたかが緩やかに見えてくる。各藩の藩主たちが江戸に住み、交流し、なにがしか「江戸」を(勤番藩士たちも)領国に持ち帰る。参勤交代なんて壮大な無駄にも思えるけど、この積み重ねが案外、時代を日本という国を、熟成させていったのではないか、などとも思える。
2022年3月3日著者・氏家幹人氏の最初の本だそうな。曰く、その後の自分の興味がほとんど入っている、とのことだが、確かにそう見える。「江戸藩邸」なんて堅苦しくて面白くなさそう、と早合点してはいけない。江戸藩邸は各藩の大使館のような存在で、軍事要塞的性格も持っている。秘密の江戸のディープスポットだ。その内側で繰り広げられる人間臭い有象無象が、氏家流に語られる。各章のテーマはバラバラのように見えるのだが、全体を通して、江戸藩邸が江戸時代260年の間にどう変化し、どのような役割を演じたかが緩やかに見えてくる。各藩の藩主たちが江戸に住み、交流し、なにがしか「江戸」を(勤番藩士たちも)領国に持ち帰る。参勤交代なんて壮大な無駄にも思えるけど、この積み重ねが案外、時代を日本という国を、熟成させていったのではないか、などとも思える。
 いいね
0件
いいね
0件 -
人が生き抜こうとする力に心を揺さぶられる




 2022年2月2日江戸時代、伊豆鳥島に漂着した後、本土へ帰還した船乗りたちの実話。第一部では享保・元文期の漂流譚を中心に、第二部では天明・寛政期の漂流譚を中心に据えているが、おそらく鳥島へのほとんど全部(記録が残るもの)の漂流について触れられている。まずはその数の多さと壮絶さに驚かされた。広大な太平洋の中にポツンと置かれた絶海の孤島へ漂着する確率はどれほどのものなのだろう。漂流者は九死に一生を得て鳥島へたどり着いたが、そこは木も生えない活火山。無人島で水もなく、見渡す限り大きな白い鳥に埋め尽くされている。すでに多くの場合船も破損している。たまたま漂流してきた船に助けられるという稀有な例もあるが、ほとんどは自力で船を設え脱出し帰還している。その勇気と生命力には感嘆するほかない。同時代人たちも同様だったらしく、多くの口述書が「漂流記」として残されているようだ。筆者は研究者として、それらの「漂流記」を丹念に追い、実像を描こうと努めている。本書は明治初期の漂着事例をもって終わるが、その後鳥島で起きた数々の出来事にも思いを馳せる時、なんだか鳥島に頭を下げたいような気分になる。「恩愛深キ鳥島」流木で一から船を作り、ようやく脱出した天明・寛政期の漂流者たちが、遠ざかる島に抱いた思いに胸が詰まる。
2022年2月2日江戸時代、伊豆鳥島に漂着した後、本土へ帰還した船乗りたちの実話。第一部では享保・元文期の漂流譚を中心に、第二部では天明・寛政期の漂流譚を中心に据えているが、おそらく鳥島へのほとんど全部(記録が残るもの)の漂流について触れられている。まずはその数の多さと壮絶さに驚かされた。広大な太平洋の中にポツンと置かれた絶海の孤島へ漂着する確率はどれほどのものなのだろう。漂流者は九死に一生を得て鳥島へたどり着いたが、そこは木も生えない活火山。無人島で水もなく、見渡す限り大きな白い鳥に埋め尽くされている。すでに多くの場合船も破損している。たまたま漂流してきた船に助けられるという稀有な例もあるが、ほとんどは自力で船を設え脱出し帰還している。その勇気と生命力には感嘆するほかない。同時代人たちも同様だったらしく、多くの口述書が「漂流記」として残されているようだ。筆者は研究者として、それらの「漂流記」を丹念に追い、実像を描こうと努めている。本書は明治初期の漂着事例をもって終わるが、その後鳥島で起きた数々の出来事にも思いを馳せる時、なんだか鳥島に頭を下げたいような気分になる。「恩愛深キ鳥島」流木で一から船を作り、ようやく脱出した天明・寛政期の漂流者たちが、遠ざかる島に抱いた思いに胸が詰まる。 いいね
0件
いいね
0件 -
類書のワンランク上




 2021年12月26日読んでみて期待以上だった。著者名がはっきり「安藤優一郎」となっていたので買った本。お江戸の雑学的な読み物は多いけれど、著者「〇〇の会」などという無責任なやり方で、編集として著名な学者さんが名を貸しているものがほとんど。各章を分担して書いているのだろうけど、章ごとに重複や整合しない部分があったり、見識の差が歴然としていたり、どっかで読んだ話そっくりだったり、たいていがっかりする。短い文章であっても、案外文章の背後に潜む学識のボリュームは分かってしまう(短いからこそか)。様々な切り口で多数の著書がある安藤氏ならでは、安心して楽しめる内容になっている。
2021年12月26日読んでみて期待以上だった。著者名がはっきり「安藤優一郎」となっていたので買った本。お江戸の雑学的な読み物は多いけれど、著者「〇〇の会」などという無責任なやり方で、編集として著名な学者さんが名を貸しているものがほとんど。各章を分担して書いているのだろうけど、章ごとに重複や整合しない部分があったり、見識の差が歴然としていたり、どっかで読んだ話そっくりだったり、たいていがっかりする。短い文章であっても、案外文章の背後に潜む学識のボリュームは分かってしまう(短いからこそか)。様々な切り口で多数の著書がある安藤氏ならでは、安心して楽しめる内容になっている。
びっくりしたのは本文が横書きだったこと。個人的には「日本語の本は縦書きでしょ」派だけど、固定レイアウトで浮世絵などの画像も多い本書においては読みやすく(PCで読みました)、正解といえるかもしれない。 いいね
0件
いいね
0件 -
内容は星五つ、でも文字が小さすぎる




 2021年12月20日本の内容に対して星五つ。『ものと人間の文化史』シリーズがシーモアで買えると知って感動。さっそく購入しましたが、とにかく文字が小さくて読みづらい。購入前に試し読みしたのですが、図版部分しか閲覧できず、本文の状態を確認できませんでした。せめて目次くらい見られたら良かったのですが。元の(紙の)本が文字小さめでぎっしりだから仕方ないのは分かっちゃいるが、PCアプリでもブラウザでも、色々調整してみても、とにかく文字が小さすぎる。若い人は平気なのかも、ですが。もう一度言いたい、文字が小さすぎる。余白をトリミングできないものか、法政大学さん。
2021年12月20日本の内容に対して星五つ。『ものと人間の文化史』シリーズがシーモアで買えると知って感動。さっそく購入しましたが、とにかく文字が小さくて読みづらい。購入前に試し読みしたのですが、図版部分しか閲覧できず、本文の状態を確認できませんでした。せめて目次くらい見られたら良かったのですが。元の(紙の)本が文字小さめでぎっしりだから仕方ないのは分かっちゃいるが、PCアプリでもブラウザでも、色々調整してみても、とにかく文字が小さすぎる。若い人は平気なのかも、ですが。もう一度言いたい、文字が小さすぎる。余白をトリミングできないものか、法政大学さん。
シーモアさんにお願い。以前より改良されてましたが、さらにもう一押し! PCアプリ、全画面表示できるようにしてください。全画面のまま拡大できるようにもして欲しい。(ブラウザだと全画面にしても画質が悪すぎ)拡大率ももう少し小刻みだと嬉しいです。(125%で表示すると、文字が一段だけ切れる。たぶん120ならいける)
でも結論としては「こういう本はやっぱり紙だな」です。 いいね
0件
いいね
0件 -
『おくのほそ道』 編集は至れり尽くせり




 2021年8月25日日本の代表的古典文学を、誰でも、とにかく、ハードル低くく楽しむ。――ことができる本です。まさにビギナーズ・クラシックス。歌枕だの歴史の教養など無い者には大変ありがたく楽しんで読むことができましたし、至れり尽くせりだからこそ知り得たことも多かったです。ただ、やはり味わいは少し落ちるかもしれません。「それは言わぬが……」と思うくらい饒舌すぎるところも(おそらく編集の方も悩まれたと思いますが)。訳や解説を理解してから、原文を通読・音読するのがお勧め。
2021年8月25日日本の代表的古典文学を、誰でも、とにかく、ハードル低くく楽しむ。――ことができる本です。まさにビギナーズ・クラシックス。歌枕だの歴史の教養など無い者には大変ありがたく楽しんで読むことができましたし、至れり尽くせりだからこそ知り得たことも多かったです。ただ、やはり味わいは少し落ちるかもしれません。「それは言わぬが……」と思うくらい饒舌すぎるところも(おそらく編集の方も悩まれたと思いますが)。訳や解説を理解してから、原文を通読・音読するのがお勧め。
でも、こういうシリーズが出るようになったんだ……と感無量。ありがとうございます。
 いいね
0件
いいね
0件 -
-
興味深い史料、本当の江戸時代がここにある




 2021年4月12日一般に、江戸期の史料はたくさん出版されているけど、この本のように地方の、小藩や庶民のくらしについて記したものはあまり無いように思う。小藩ゆえの苦労や実情、小藩だからこそ『会所日記』という公文書(と言って良いのかな?)に細かく記され垣間見える庶民のくらし。それらは私が「江戸時代」だと思っていたイメージとはずいぶん違った。歴史に興味のある方には、ぜひお勧め。
2021年4月12日一般に、江戸期の史料はたくさん出版されているけど、この本のように地方の、小藩や庶民のくらしについて記したものはあまり無いように思う。小藩ゆえの苦労や実情、小藩だからこそ『会所日記』という公文書(と言って良いのかな?)に細かく記され垣間見える庶民のくらし。それらは私が「江戸時代」だと思っていたイメージとはずいぶん違った。歴史に興味のある方には、ぜひお勧め。 いいね
0件
いいね
0件 -
美しい幻想絵画の連作




 2021年1月3日長野まゆみさんの作品を初めて読みました。1,2巻は12編の、3巻は4編の物語が入っています。それぞれが味わいの違う美しい幻想絵画だな、と思います。著者は美大卒ということで、さもありなん、でしょうか。私が一番興味を持つのは、桜蔵という男の子を通して、著者が何を「女」と表現しようとしているのか、というところです。連作ですが、お話に整合性はあまりなく、ストーリーよりもイメージへと読み手を引きずり込む。皿の上で全てを混ぜて再構築する。それは黄泉の国のイザナミのようにも、子宮のようにも思えます。そんなふうに自分の内側で遊んでしまう作品です。好みは分かれそうですが、私はとても良いと思います。
2021年1月3日長野まゆみさんの作品を初めて読みました。1,2巻は12編の、3巻は4編の物語が入っています。それぞれが味わいの違う美しい幻想絵画だな、と思います。著者は美大卒ということで、さもありなん、でしょうか。私が一番興味を持つのは、桜蔵という男の子を通して、著者が何を「女」と表現しようとしているのか、というところです。連作ですが、お話に整合性はあまりなく、ストーリーよりもイメージへと読み手を引きずり込む。皿の上で全てを混ぜて再構築する。それは黄泉の国のイザナミのようにも、子宮のようにも思えます。そんなふうに自分の内側で遊んでしまう作品です。好みは分かれそうですが、私はとても良いと思います。 -
紙の本は字が小さすぎる




 2020年12月18日このシリーズ、電子化待ってました。紙の本を持っているのですが、私には字が小さすぎます。電子書籍の辞典て慣れるまで使い勝手が悪いと思うのですが、本を開かないのでは意味が無いので。試し読みで確認しただけですが、普通の電子書籍の辞典の使い方です。同シリーズの『情景ことば』も電子化お願いします❗
2020年12月18日このシリーズ、電子化待ってました。紙の本を持っているのですが、私には字が小さすぎます。電子書籍の辞典て慣れるまで使い勝手が悪いと思うのですが、本を開かないのでは意味が無いので。試し読みで確認しただけですが、普通の電子書籍の辞典の使い方です。同シリーズの『情景ことば』も電子化お願いします❗ いいね
0件
いいね
0件
 ERR_MNG
ERR_MNG

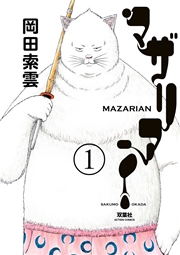
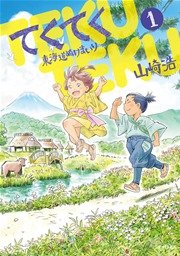
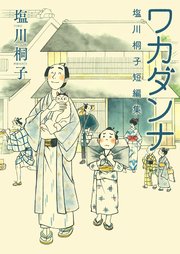
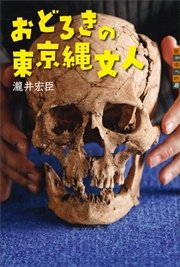
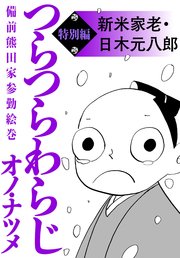
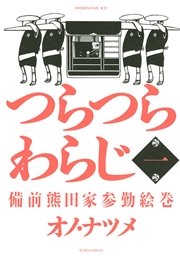
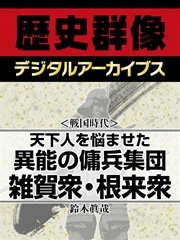
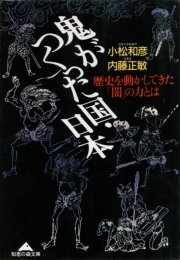
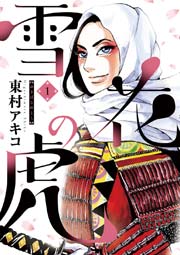
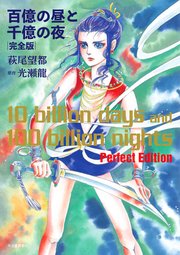
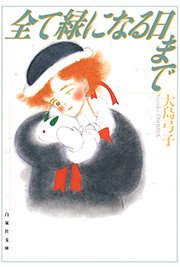

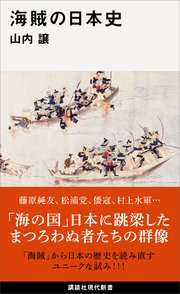
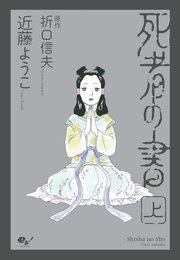
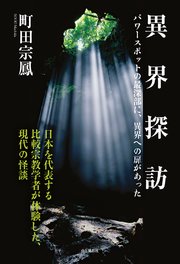
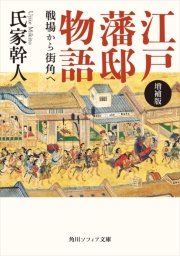
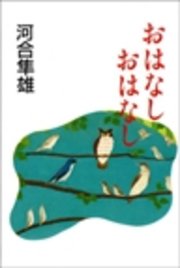

![[ビジュアル版] 江戸の《新》常識](http://cmoa.akamaized.net/data/image/title/title_1101224746/VOLUME/111012247460001.jpg)