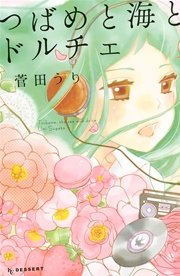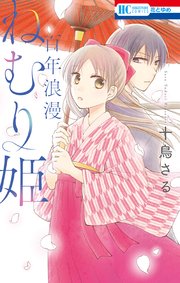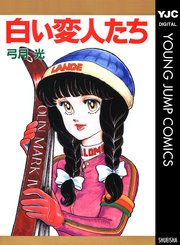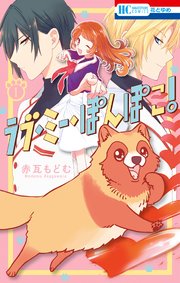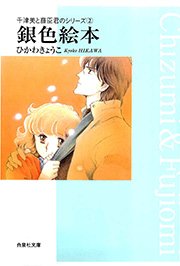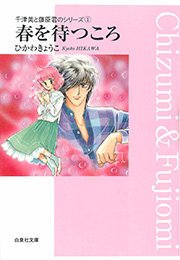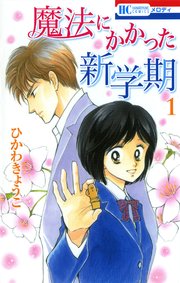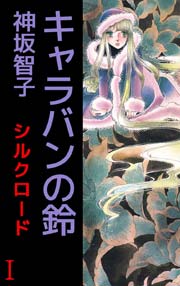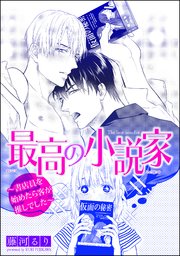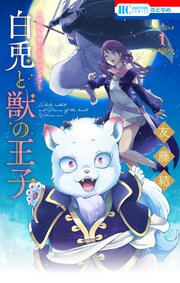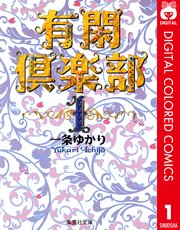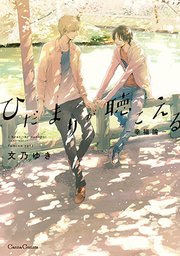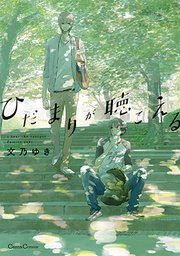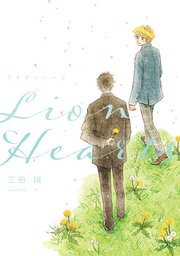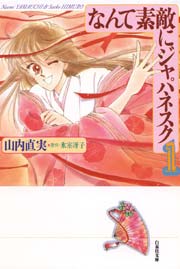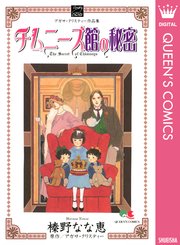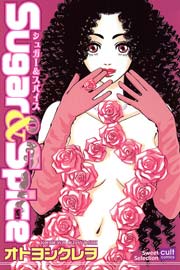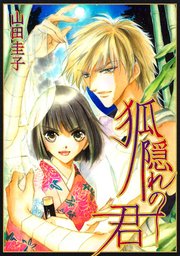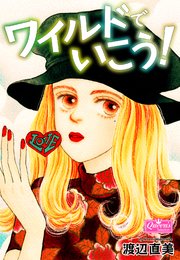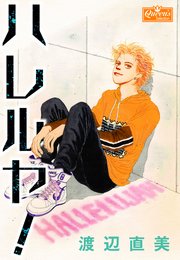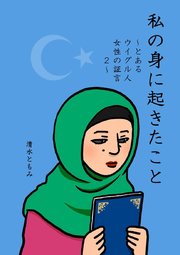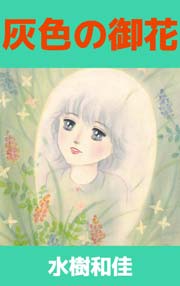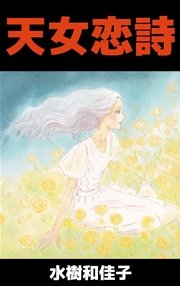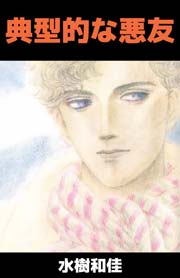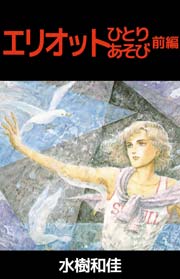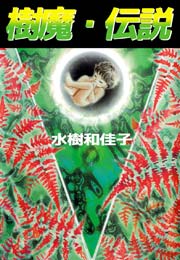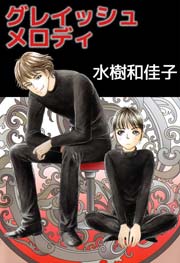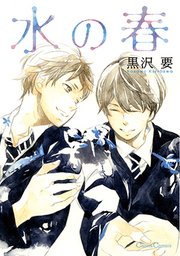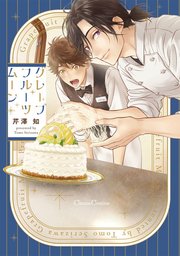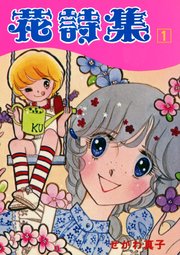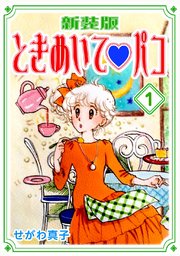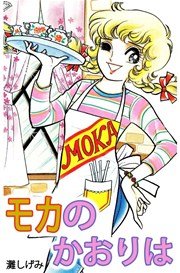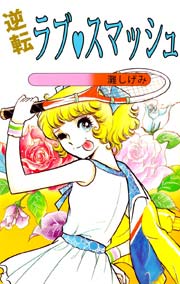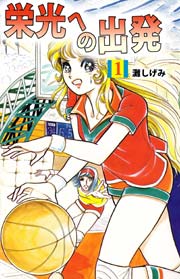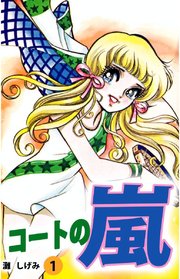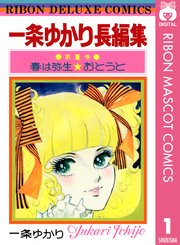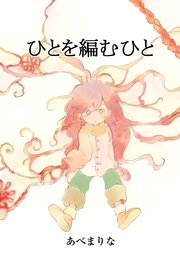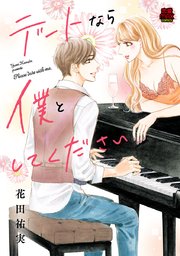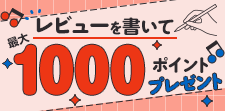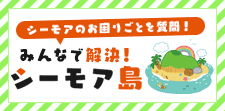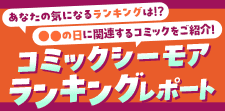レビュー
今月(11月1日~11月30日)
レビュー数0件
いいねGET26件
シーモア島
 ベストアンサー134件
ベストアンサー134件
 いいね11291件
いいね11291件
投稿レビュー
-
映写技師とそのまわりの人間関係、事件




 2025年1月5日「もぎり」君の登場の仕方は訳ありだったし、記憶喪失も闇があるかもしれないと身構えた。
2025年1月5日「もぎり」君の登場の仕方は訳ありだったし、記憶喪失も闇があるかもしれないと身構えた。
しかしさらさらと日常が過ぎていく。拾ったもぎりとの生活はフィクションらしいあざと展開に思えたが、町の人々との交流場面やイベントの企画と実行などリアル味が増していくと、むしろ十和のこだわりなどにもクセが感じ取れこの人物ならその拾い者すら、さもありなんというエピソードと随所で思えてくる。
穏やかな日々を破りに来る2巻巻末、続く3巻への緊張が3巻構成の、意味を成す。十和まわりの今はどうしてるんだ?、生きてるのか死んでるのかというような出奔した責任を手放しているその人物の、どうしてる?が描かれる。紺との日々。
此処でやっと冒頭のもぎりにやっとのことで通じることが出来た。
ストーリーはヒューマン要素で固められているが、映画のミニ知識も読んでいて興味を誘った。特にあとがきでの、フィルム論、なるほど。
最後の最後まで読んで楽しめた。
リトルダンサーのエピソード(内容はよかったが)、このサイズ感の話にしては大きかった。
途中で尺の短縮を図ることになったのだろうか? -
-
身が引き締まる職人世界の恐さ厳しさ




 2024年12月29日前半はちょっとしたすごみを時代背景と共に体験感覚で読んでいた。後半、気の荒さ、血気盛んな職人魂を喧嘩っ早さの描写を通じて体感した気がした。
2024年12月29日前半はちょっとしたすごみを時代背景と共に体験感覚で読んでいた。後半、気の荒さ、血気盛んな職人魂を喧嘩っ早さの描写を通じて体感した気がした。
仕事には男も女もない、そこも描きたかったのだろう、甘えがなくてピンと姿勢真っ直ぐの職人のカシラは威勢がいいが、下の者は性別に理由を求めるところの描写に、いいようのないやるせなさも感じた。
細部の描写に圧倒される。職人の描写だからと言ってしまえばそうなのだが、職人の仕事が絵を通じて伝わらなかったら説得力もなにもなかっただろう。
ごくら町の人々の仕事ぶりは特異なひとつの町のことなのではなく、こういう町をひとつ採り上げてみた、といった風情。
頭の下がる職人ぶりで、仕事を進めるも、きっとみんなもそうだったんだよ、と、いわれてる気がしてしまった。
割引を利用して買ったがそれで良かったと思う。シーモア(島)で紹介されてから長いことチャンスを待っていた。機会を得られてよかった。 -
やっぱりすごすぎる。此が一冊のコミックス




 2024年12月24日変幻自在に日常をスナップよろしく描き留めて、何気ない会話のなかに亀裂と崩壊を進める要因と辛うじて危険から守る何かを残す。
2024年12月24日変幻自在に日常をスナップよろしく描き留めて、何気ない会話のなかに亀裂と崩壊を進める要因と辛うじて危険から守る何かを残す。
危ういバランスの中に絆と血の違いがあり、この作品はお母さんが徹底して頑固に強い。意地なのか、過去への彼女なりのこだわりなのか?
中学生主人公が、早く大人になっているところもあるし幼さを残すところもある。卜部君は難しい立ち位置だけど、このストーリーの中では一番がんばるべき存在と思うし、実際活躍したけれど、何故かビジュアルにインパクトを持たせない。作者的に彼を頼っていないのか。そこが読んでいて、私は、展開が宙ぶらりんと、感じてしまうところでもあるのだ。
しかし岩館先生の力量ゆえに、毎度の突き放した終わりかたへの不満はない。むしろやってくれたなとさえ。こうして1巻出来上がってしまうのがすごすぎる。これは最終話まで読んで評するべき作品。 -
じわじわと領域を広げていく、ほのぼの恋愛




 2024年12月24日和谷君は一歩間違うと、もさい部類に入りそうでギリギリ頑張ってる感じ。出席簿の関係から「あ」と「わ」は遠い。クラスで何となく過ごす友だちの範疇に遠い。でも、気にしないで日々彼の挙動に関心を持ち続け、毎週話しかけにバイト先へ。うーん、なにげにスーパー積極的。
2024年12月24日和谷君は一歩間違うと、もさい部類に入りそうでギリギリ頑張ってる感じ。出席簿の関係から「あ」と「わ」は遠い。クラスで何となく過ごす友だちの範疇に遠い。でも、気にしないで日々彼の挙動に関心を持ち続け、毎週話しかけにバイト先へ。うーん、なにげにスーパー積極的。
この女の子のキャラなくては二人の進展はなかった。そこをぶれずに描ききり、変に途中からウジウジさせずにいたところが凄く成功したと思っている。
逆に和谷君はそんな少女漫画の感情推移。なんでぼくを?ぼくなんか!あんなキラキラ女子が相手にするわけがない、期待しちゃいけない!!などと、みたことのある景色。
少しずつ距離が縮まる関係性、その微妙な勿体ぶりがとても効果的に働き、焦れを呼ぶ。
そこを楽しませてもらった。
和谷君は前髪が重すぎる(だから✕✕なのだ、の理屈付けが、まかり通ってしまう)のが、そしてだから余り目を見せないところが、「陰」を薄~く感じさせる作戦なのだろうが、少し陽が関わっても最終話までキャラの一貫性も頑張ったようだ。私はもう少し自信をつけたいきいきした姿を見たかった気がする。 -
恐ろしく薄気味悪い展開、前向き中学生活躍




 2024年12月18日シーモア(島)でお勧めあり読みに来た。映画スタンドバイミーを思い起こすが、違う。組織的地域的犯罪に仕立てられたが操縦ミスではなかったか。
2024年12月18日シーモア(島)でお勧めあり読みに来た。映画スタンドバイミーを思い起こすが、違う。組織的地域的犯罪に仕立てられたが操縦ミスではなかったか。
敵が多い、誰が敵か味方か、という環境設定には役立ったかもしれないが。しかしそれも、読者目くらましの為の演出上の小細工が効果を高め損ねた。
ストーリーはスピード感溢れる展開と、中学生4人のたくましさと幼さの不均衡を上手く活用されて面白かった。
森、動物、鉄塔の冒険を好奇心や友情の中に上手く嵌めてあり、とてつもない犯罪のダークさとのかみ合わせにはミスマッチ感。犯罪のスケールの割に小粒な器の骨格、ところどころ無理な印象も。
しかし私の男性向け漫画に抱く苦手な要素は本作では1個だけ、血生臭さのみ。
中学生にしては余りにハードな経験ではあったろうが、この「ひと夏の大冒険」などと言った簡単な総括がしにくい希有な事件のサバイバーとしての成長もチラ見せで、凄惨な話の割にはサラリとした感触の、冒険がお話の根っこにある作り話である前提を強調していて読みにくさが無い。 -
お勧めに乗せられ読んでみたら新世界だった




 2024年12月15日シーモア(島)でお勧めをいただいて日頃読まないジャンルである青年マンガ日常系の本作(短編集であった!)に来てみた。
2024年12月15日シーモア(島)でお勧めをいただいて日頃読まないジャンルである青年マンガ日常系の本作(短編集であった!)に来てみた。
私には新世界の感覚だが、描いてある題材は普段の身の回り。しかし着地点判らないなりに厳しい状況。経済的に。家庭環境的に。
家族もかなりよくあるパターンに収まってない。
ひろこが笑い、最後は大きく声を上げて大笑いするシーンは良かった。じいさん、いい仕事した。
また、この先生の話の締め括らせ方が、締め括られてないところにユニークさが。
「ゴーグル」で新人賞応募作とあとがきに。
あとがきを読むとまた楽しめる。 -
-
-
-
目新しさに惹かれて




 2024年11月20日記憶を乗っ取るように取り払われてイコール死んだも同然の「バグ」となる人間。それを食い止めるべく結成されてる正義の組織。前線で戦う人間とそれぞれのパートナーである動物たち。
2024年11月20日記憶を乗っ取るように取り払われてイコール死んだも同然の「バグ」となる人間。それを食い止めるべく結成されてる正義の組織。前線で戦う人間とそれぞれのパートナーである動物たち。
着眼点が面白くてやって来た。読み進めるうち、仕組みや各キャラの読み手への理解させ不足が目についた。
コウガは健気だし、主人公東斗との結びつきの強さは軸としてちゃんと感じられたが、それ以外はくいっ散らかしだ。この短さだから、なのだろうか?
いやそうとばかりも思えない。
ディープダイブも、観念的世界のビジュアル化で、チャレンジングなシーンとは思うが、そこをもう少しわからせた方が纏まりが出たように思う。
仲間意識、バディとの共感、人々を救い出すという正義感その他、いろいろが散ら張りすぎたように思う。バグの正体?も観念的世界の中で見せてくるのが、読み手への説得力不足と感じた。ましてや悪の黒幕的な彼に関してはただの思わせぶり演出かと。その割に何もかも煙に巻いて第5巻読了。
続きを書く布石が打たれたが、迷ってしまう。 いいね
0件
いいね
0件 -
犬も食わないのを見ながらたのしくなる作品




 2024年11月20日本当に本作はためこう先生が?、と驚く。作風が!
2024年11月20日本当に本作はためこう先生が?、と驚く。作風が!
作品中何度か、ヤマ無しオチ無しの作品のスタイルについて、居直ったかのようにこれで行くのだ、と語っていてそんなにこわばらずとも充分これで楽しめてるから気にしないでくださいと思った。
美少年を出してくる。イヤラシさはない。美少年達が華やかにストーリー展開していく。妖しくはなく、キラキラで明るいところをひたすら見せてくる。よく考えると訳わからないキャラが、廻りを固めてくる。そこを使って話が如何様にも展開できそうであっても、あくまで主役はめぐるクンとわこチャン。それでいいと思った。物足りなさは私には無かった。
めぐるクンがあまりにも献身的なのでこういう人は居るはずがないとの実在感の少なさが余計に作品の価値を高めた気もする。
わこちゃんが絶やすことのない推し活、いかに形にして彼を少しでも多くの人が魅力を判ってもらえるようにしているか、長年の彼女からの献身も(趣味を兼ねてるが)描かれる。
互いの駆け引き無しの自然に相手を想いやり合う姿が気持ちよい。
それでいいのだ、という形の中で、二人はごく当たり前に一緒に過ごし共有する時間を重ねていて素敵だ。
こういう話は穏やかに読んで微笑ましい彼らを眺めてそれで充分。
なお、コマの中の余白の大きさが気になる。字をもう少し外郭の際まで大きくするかコマを小さめにして欲しい。絵のダイナミズムを活かしつつ、相対的に目障りとなるコマ内の広々余白なぞで絵を潰さずに、文字の存在を大切にして欲しいと思うのだが!? いいね
0件
いいね
0件 -
今度こそ




 2024年11月16日人生やり直しはきかないけれど、転生物はその思いの半分を肩代わりしてくれる。前世の悔いを、現世でリベンジして少しスッキリ、という、未解決事件の解決が出来た感じか。
2024年11月16日人生やり直しはきかないけれど、転生物はその思いの半分を肩代わりしてくれる。前世の悔いを、現世でリベンジして少しスッキリ、という、未解決事件の解決が出来た感じか。
前世の差し挟み方、現世の人間関係の置き方にサラリとした感じの良さがあって、今を生きてる姿に心地良く頑張ってるキャラを楽しく眺められる。
すごくユニークなわけでもないのに、少し新鮮な印象なのは何故なのだろう。芸能人とマネージャー、この組み合わせはBLではザクザクあるのに?
大賞エントリー作品ということで、久々に投票したので。サイドストーリーを除く全既刊分は2巻。2巻まで読了した。わざとらしくいやらしい長期化のための姑息な引き延ばしも特段感じさせずに読ませたのは大きい。
ベッドシーンはこのぐらいまでなら作品レビューが出来る(逆を言わせてもらえば、作品レビューしづらくて断念してる濃厚シーンBLの多いこと!)。
ビジュアル的に踏み込みすぎず二人の気持ち優先での描写がいいと思った。
絵には最近の傾向が強くて個性もう少し、という気がしている。イベント(BIF)の戦略会議シーンが入ってきたことはとても良かった。正直ダンスのレッスンや忙しさの描写だけでは物足りないと思っていた。 -
ニナが切り拓く自分の運命、影響する諸国




 2024年11月14日嫌いじゃない、こういう話。ズルズルと先へ先へと読み続け最新刊15巻まで来た。
2024年11月14日嫌いじゃない、こういう話。ズルズルと先へ先へと読み続け最新刊15巻まで来た。
無料分の次にクーポンを使い、使い果たしたら定価で何巻も!
長編はもう手を付けないつもりでいたのだが、面白くて止まらなかった。
数奇な運命といってしまえば他人の力が大きいが、この話は本人の力と行動をストーリー展開の主軸に。王国設定が敵味方の線引きの方向感を変えるキャラ達によって柔軟に変化していく。
まだたくさん続くのだろうか?アニメ化などあったことから先が見えない状態だ。
私としては遠くない内にこの興味をそがれることなく最後まで早く読み終わりたい。 -
次々と息をつかせぬ展開ダークファンタジー




 2024年11月11日面白いが明るくないため読み進めるとさっぱりとはしない。
2024年11月11日面白いが明るくないため読み進めるとさっぱりとはしない。
しかし魅力的な創作でやっぱり大作だ。竹宮惠子先生の代表作のひとつだ。
ティオキアの取り憑かれぶりが辛い。
ユーディカの弟が思慮の足りないキャラを担当してかき回すのも少々苛つく。
忠臣カウスの主君愛がすごい。
結局大物ではないのにストーリーを回したキャラ達によって、主人公格の3人プラスひとりが目一杯火の粉を被った。ゲドの魔薬の時の奮闘もありながらのリカピのストーリー上の処遇に胸痛む。
絵が細部まで表そうとするものに意味を込めてるように感じて、ただの背景で終わってなかった。
宇宙にまで発想を広げたが、とある国々の歴史物。
大胆なストーリー展開と、翻弄されている人間達を良く描いたものだと思う。
もう第1巻から長編漫画を読み始めるような体調ではない為悩んだが、読み切って晴れ晴れとしている気分もある。1982年より連載された全8巻。 -
読んでるのか観てるのか眺めてるのか何を?




 2024年11月4日直前まで読んでいた藤子・F・不二雄先生の「T・P ぼん」のあとがきに導かれてやって来た。大好きだった石ノ森章太郎先生原作アニメの009を読んでみたいけれどなんとなく機会が無く今日に至る。こっちの書名を知って飛び乗ってきた。
2024年11月4日直前まで読んでいた藤子・F・不二雄先生の「T・P ぼん」のあとがきに導かれてやって来た。大好きだった石ノ森章太郎先生原作アニメの009を読んでみたいけれどなんとなく機会が無く今日に至る。こっちの書名を知って飛び乗ってきた。
時間を自由に往き来するまんが。何を描いてるのか、もだが、どう描きたいのか?、問いかけもすることになる作品だった。
恐竜、鯉のぼり、…。
コマまんががあるかと思えば、1頁1コマの絵も。精緻な描き分けと、お馴染みのデフォルメのキャラの協働。(ギョロ目ひとつが大きすぎる、と、何度も感じてしまう。)
取り敢えず、頭の中を読もうとするのではなくて、作者が生み出してきたものをそのまま受け取る作業。
セリフの無いコマが連続する。
これは石ノ森章太郎先生作品を相当読み込んでこないと、辿り着けない気がしてきた。
全2巻。手塚治虫先生の雑誌に掲載されたという。前衛的、抽象的?。なのに具体的でもあり説明的でもある。写実的表現と、漫画的削ぎ落としとが入り乱れている。
取り敢えず眺めてる。考える前に読んでる。
恐竜それぞれを、図鑑の頁を開くが如く観察しては、意図を図りかねて唸っている。
そうか童話か!童話…ね。でも、そうなの?
鯉のぼりはそうだね。
本当につかみどころがありません。
自由とは?石ノ森先生の自由論。表現の世界の前線に居る方としての考え方。それが、傍らで原稿を破く者を、何かにいろいろと変えて象徴させて考察させられる。
読み手を選んでいるようなフシがあり、漫画読みが値踏みされてる感覚。突き放しているようで、内面解説もしている。一般大衆に迎合してないのは明らかであり、分かり易さを期待しない方がいい。ある意味お互いが試しあいをおこない、私には力量が足りなかった。貝殻ヒレヨウラクの音を聞くシーンは先生の繊細な感性が私の感覚に訴えるものがあって、だから石ノ森先生先生作品がビジュアル的にも、私に印象付けてくるのはそういうところなのか、と、合点がいった。
秋が来て冬が来る。経験・インプットは大事。
ジュンとは、先生にとってのまんがそのものであり、子どもであり、ツールであり、表現手段であり、源泉、etc.そんな感じだろうか?
少女漫画では、ポエムと絵の2,3頁物が昔流行ったが、その石ノ森先生版にも見える。そもそも少女漫画好みの絵。
コミカルなものもあるが、大体は寂寥感に圧倒される。 -
さすが面白い!やはり傑作なのだと感じる!




 2024年10月31日大漫画家は読んでいてクセがなく伝わり易く痛快でもあり、人間的臭みもだしながら理想も感じてしまういろいろ詰まったストーリーで飽きさせない!
2024年10月31日大漫画家は読んでいてクセがなく伝わり易く痛快でもあり、人間的臭みもだしながら理想も感じてしまういろいろ詰まったストーリーで飽きさせない!
川崎市藤子・F・不二雄ミュージアムに2023年5月に行ったとき、先生の作品をもっと読みたいと、心底現地で感じた思いが蘇る。実にエンターテイメント色に溢れかえっていて、読み手を愉しませようとの気持ちが伝わってくるし、少しでもいい物を世に送り出したいとの、先生の創作の姿勢が素晴らしい。
本作は御本人登場回もある! 「少し不思議」な世界で、歴史、宗教、戦い、自然災害、小さなエアポケットに嵌まった理不尽な死や無念の死を救う、目立たないけれどもやり甲斐のあるタイムパトロールのお仕事。その彼らの扱うツールの面白さもさることながら、時空を越えて縦横無尽に駆け回るダイナミックさ、発想の面白さ!
無名の市井の人々を掬い上げて、世界史の視点がグッと複眼的になる。と同時に、軽い世界地理と世界史の一断面への知的好奇心がくすぐられる。職務遂行による達成感と、人類の隅っこへのささやかな貢献、とを味わえて、ヒーロー感覚もちょっぴり理解。
まだ途中だが書いておきたくなった。
残り巻について後述の予定。
ストーリーだけでも、絵の分かり易さだけでも、本作はそれぞれ既に星6か星7に思う。カラー頁ふんだん。新装決定版と二種類あり。初出てんとう虫コミックススペシャルや小学一年生誌だそうだが大人が読んでもこたえる出来なので大丈夫。【訂正:1巻目542頁少年ワールド誌1978/8月号~。】各話30頁台で14話。
2巻目384頁コミックトム誌1980/5月号~。各話30頁台で10話。西欧の捕鯨問題は根が深いし罪深い。2巻目は大人にこそ啓発的なトピック。
3巻目398頁同誌1984/6~1986/7月号。11話。昔シュリーマンの伝記に感動したものだ!ヒッタイト!あと十字軍の話もよい。
それにしても発想力?、空想力?、創造性?が豊か。夢いっぱいで、大胆で冒険心をくすぐり、好奇心がもっと刺激される。
柔軟な展開に、奇想天外な解決というかコトの顛末、自由自在の時間コントロールのパトロール隊員のあり方、その縦横無尽さに恐れ入るし登場人物達の神出鬼没ぶりに、作品て限界というものは勝手に人間が作るだけで、実は勝手に敷いてしまう作家次第なのだと実感する。素晴らしい明るさが感じられてなんだか先生の作家性自体に“すごくホ(フォ!?)ッと”する。 いいね
0件
いいね
0件 -
空港及び関連施設、周辺環境ガイドブック?




 2024年10月26日空港愛が詰まった漫画。その趣味どっぷりだと楽しいと思うが、話13回に至るまで余りドラマ仕立ては強くないため(話は最終話まで全53話)、主人公桐谷の上司竹内課長の強引さ、上司として横暴が過ぎると思ってしまう私は一歩引いて読んだ。そんな上司につくことになった桐谷の悲哀を面白おかしく描いた趣向なのだろうとは思うが。職務内であろうとすれすれで強制力が仕事外にも及んでいる感じ。でもそこにも、どれだけ空港にフォーカスさせたいのか作り手の熱意も感じるし途中出場の鉄道派がかき回すことでより竹内のクセや桐谷の巻き込まれ具合を眺める展開に。タイトルは「雲の上より」とあるがどちらからというと「地上から」要素強し。主人公達の企業の事業内容が不透明で、かつ、仕事の連想がしにくい。その上で「評価」とは、一体なに?読み手にはそこもわかりにくい。出張を名目に次から次へと空港を紹介していくので雑誌連載形式で読んでいれば今回はどこかな?どうなのかな?といった関心は持てるかと思う。まとめて読むのは私にはきついものがあった。
2024年10月26日空港愛が詰まった漫画。その趣味どっぷりだと楽しいと思うが、話13回に至るまで余りドラマ仕立ては強くないため(話は最終話まで全53話)、主人公桐谷の上司竹内課長の強引さ、上司として横暴が過ぎると思ってしまう私は一歩引いて読んだ。そんな上司につくことになった桐谷の悲哀を面白おかしく描いた趣向なのだろうとは思うが。職務内であろうとすれすれで強制力が仕事外にも及んでいる感じ。でもそこにも、どれだけ空港にフォーカスさせたいのか作り手の熱意も感じるし途中出場の鉄道派がかき回すことでより竹内のクセや桐谷の巻き込まれ具合を眺める展開に。タイトルは「雲の上より」とあるがどちらからというと「地上から」要素強し。主人公達の企業の事業内容が不透明で、かつ、仕事の連想がしにくい。その上で「評価」とは、一体なに?読み手にはそこもわかりにくい。出張を名目に次から次へと空港を紹介していくので雑誌連載形式で読んでいれば今回はどこかな?どうなのかな?といった関心は持てるかと思う。まとめて読むのは私にはきついものがあった。
左右開きで読むのをおすすめする。やはり飛行機や飛行場の雰囲気が横開きで堪能できるかと思う。
女性キャラに品があるのは良かった。青年漫画にありがちな女子の肉感がないところが嬉しいのだ。
隅から隅まで空港を見て回ることなどほぼないだけにそういう好奇心をものすごく満たしてくれる作品。途中出場キャラもみなアクが強すぎるくらいに強いが、作りが極端なところが乗れるかどうか。たとえば、時田さん、わたしは読んでいて、「時田さん、時田さんよぉ~」と感じてしまったり。大屋課長もわたしてきにはヤレヤレ、だ…。
でも、各キャラの濃さこそが本作品の色付けをしているため、それを否定してはこの作品の見どころをを読めていけないと思う。空港と会話…。最後まで桐谷よろしく、一介の読み手の私もすっかり彼ら独特のリズムに、振り回され続けたのであった。
全7巻。 -
全くもって頭が上げられません。最敬礼です




 2024年10月16日凄く面白くて爆笑の話が盛り沢山の中に言いたいことがさらりと微かに入り、なのに、嫌味の欠片も感じさせない軽妙さ。楽しく、いつの間にか読むと社会を見るのにも“為にもなる”エッセーコミック。ほんの少~しチクッと突いてくる農家を振り回す畜産・農政・観光客への嘆き節、痛みや辛さもあるはずなのにポジティブで根明(ネアカ)なトーンでの苦労話の散りばめ方が、読んでいてたくましさや力強さを感じさせて実に格好いい。所謂自然の厳しさ、脅威も、スケールのまるで違う北海道という大きな世界の開拓のものすごさがそれでいて伝わる伝わる。そして生き物相手の悲しい事や、昼夜分かたずの世話に於ける悲哀でしんみりしたり、生きていくということはそれを前線で切り拓いている人たちあってのことだと痛感。全く頭が上げられなくなる。何だか知らなさすぎたことが恥ずかしくなってくる。自分は消費という末端で、表面的理解しかしてこなかった、と、よくわかる。農業高校編も引き込まれたし生徒や教師、教育環境に圧倒された。読み応えバッチリ、まだ完読まで数巻残すがその前に、途中で感動を伝えたくなってしまった。
2024年10月16日凄く面白くて爆笑の話が盛り沢山の中に言いたいことがさらりと微かに入り、なのに、嫌味の欠片も感じさせない軽妙さ。楽しく、いつの間にか読むと社会を見るのにも“為にもなる”エッセーコミック。ほんの少~しチクッと突いてくる農家を振り回す畜産・農政・観光客への嘆き節、痛みや辛さもあるはずなのにポジティブで根明(ネアカ)なトーンでの苦労話の散りばめ方が、読んでいてたくましさや力強さを感じさせて実に格好いい。所謂自然の厳しさ、脅威も、スケールのまるで違う北海道という大きな世界の開拓のものすごさがそれでいて伝わる伝わる。そして生き物相手の悲しい事や、昼夜分かたずの世話に於ける悲哀でしんみりしたり、生きていくということはそれを前線で切り拓いている人たちあってのことだと痛感。全く頭が上げられなくなる。何だか知らなさすぎたことが恥ずかしくなってくる。自分は消費という末端で、表面的理解しかしてこなかった、と、よくわかる。農業高校編も引き込まれたし生徒や教師、教育環境に圧倒された。読み応えバッチリ、まだ完読まで数巻残すがその前に、途中で感動を伝えたくなってしまった。
子どもの教育にも(十代からの)もしかしたらとても素晴らしい副教材となるのでは?
少なくとも都市部に住む子ども達はこの書籍で何かが変わるかもしれない、そんな期待も抱かせる好著。食糧自給率の観点も草の根から皆が自覚的になるかも!そして実に深い。実は深いトピック数々あるのだ。防風林…。また、きれい事だけで済まされないのが生きているということなのだろう。そして生産調整、廃棄…。農業クラブ全国大会なんてなんかインターハイ?大文化祭?みたいで!
撮影での全焼エピに絶句。羊肉調達が!?飼料もだし、依存度が大きな課題だと思った。
私は荒川先生の著名な漫画作品を、日頃別の漫画畑に居ながらもこの耳にも轟いてる名声でかねがね読みたかったが、時間等種々勘案し本作から読ませていただいた。それも大いにアリかと思った。
(やっぱり超人的なおかただと読むほどに思う…。)
とにかく心から本書一読を勧める。ストーリー漫画ではないためいつでも何処でもこまぎれに読める。
2006年vol.8ウンポコ誌~2009年vol17同誌、同誌休刊後、2巻目からは同じ新書館内移籍し2009年9月号ウィングス誌~2023年8月号同誌。
最新第8巻迄読了! -
-
愛と羽ばたくフィギュアスケート漫画




 2024年10月14日こういうスポーツ漫画だったのね!、と改めて全編を読んでこの作品が描かれた時代性を大いに感じ取りながら、少し泥臭く、しかし同時に爽やかも柔軟に追求するフィギュアスケートの世界を楽しんだ。
2024年10月14日こういうスポーツ漫画だったのね!、と改めて全編を読んでこの作品が描かれた時代性を大いに感じ取りながら、少し泥臭く、しかし同時に爽やかも柔軟に追求するフィギュアスケートの世界を楽しんだ。
因縁や血、宿命の対決、憎しみとかライバル意識。狭いムラ社会のようなフィギュアスケート界で、いつの間にかみんなが繋がっていく。
綺麗で華やかな舞台裏の悲喜交々…。
いろいろ無理設定も、当時なら不思議はない。何しろ、当時は女性の和服も珍しくはなかったし、根性論で頑張ればなんとかなるという発想も強かったのも、読んで違和感皆無。そんな時代背景に、強烈な家庭環境対比。あらゆる意味でドラマチック設定を狙った感があり、それでいて難しそうなこじれを収束へ向けていく、力づくのストーリー。
しかし、次へ次へと読ませて明日への希望へ。
あちこち塞がっているかに見えた先が、競い合いながら、また、支え合いながら、羽ばたく所を見つけていく。
フィギュアスケートの採点ルールからコンパルソリーがなくなり隔世の感あるも、トリプルートリプルについて、時代の幕開けも感じ取った。
主人公はフラフラしているかのようでいて、彼女なりのロジックは理解できる。
足元やジャンプ場面、少し物足りなさはあったが、フィギュアスケートが出来る環境確保は並大抵ではなかったのだろうと思うと、そんな時代にこういう漫画があったこと、それだけでも凄いことだと感じてしまった。
誠に狭い中で好きだ何だとやっていているが、一日中フィギュアスケートの事ばかりの練習漬けの彼ら、他に何も無いのだからしかたがなかったろう。
シングルスケーターには無理だろうと思われる技の習得(エキシビションではリフトさえ!?)や、いきなりの大舞台抜擢での活躍や、朝練のものすごさの学業との両立困難さの不思議だとか、いろいろあったけれども、それでも大いに楽しかった。
男性の雰囲気、ストーリー上では似せる必要性は当たり前にあったものの、それでも漫画全体としてのビジュアルは損していた、とは思った。 -
やり足りずにおわったことは忘れられない。




 2024年10月6日雄大な絵を「岳」サイズで楽しむには横読みがマスト。
2024年10月6日雄大な絵を「岳」サイズで楽しむには横読みがマスト。
シェルパ族頭のアン・ブルバほか、の話。
登山家たちを惹きつけ、執念の対象とも執着の頂ともいえる世界の最高峰エベレスト。恐い位に皆が挑み続ける姿が、登らない私の眼には痛々しいというか、魔の吸引力を持つ存在に映る。
51頁「南西壁」41頁「裸足の壁」。
モンブランのドリュ北壁-30頁「Part1.遭難」30頁「Part2.時よ止まれ」。失くしたと思っていた魂が、その契機に蘇る。
36頁「遠い頂」、ここにもエベレストに魅せられた男が。「はるかなヒマラヤにそびえる世界最高の頂にあこがれ」!。でも、本当の登頂の成果は私が思うに、シェルパのかたがたのものでもあって、かつて観た登山記録的映画「K2」に於いてはカメラマンの功績もあると思った。
38頁「ザイル」-アルプス北壁。そこに山があるから、なる登山理由(クライマー心理)はよく聞くけれど「そこに命(人生)そかけた理由を知るため」の言葉にも、なるほどと感じた。
42頁「ヒマラヤの虎」はアン・ブルバの話ふたたび。
41頁「吹雪」は日本の北アルプスが舞台。理由に圧倒される。「美しいから」。すごく胸に響いてきた、と、あとでそこが胸に刺さってえぐってきた。
30頁「Part1.最終キャンプ」、30頁「Part2.北西壁の5人」はK2が舞台。
全375頁。
話の中には、「*この物語はフィクションです」の断り書きが見つからない話もある。
こうも「岳人」集だと
話がひとつながりでないと読み疲れることはある。山で一応ちゃんとまとまりがあるのに、気持ちが切れやすい。しかしその分、登山にとりつかれている男たちの短編ドラマが濃い。
正に壁を伝い登り、細く危険なルートを命掛けで踏み入れていく緊張感一杯。
やりすぎの失敗は忘れても、やり足りず終わったことは忘れられない、この言葉は一般的にも深い意味が感じられることばであるのに、本書の中ではその意味をもっとリアルにかみしめてしまうところがあった。
絵は男性向け特有の線と強烈さがあり、少女・女性向け漫画好きな私には、妙な擬態語もあって、更にキャラ達の発想にはついて行けない独特の理屈もある。けれどもそうした「臭さ」もひっくるめて、このクライマー達の世界が色濃く描かれており、読み終えると、読まなければ体感し得なかったような追体験感覚があって、トリップしてきた気分となる。
第6回(1982年度)講談社漫画賞少年部門受賞作品。 -
特装版に気づかず通常版買って、追加購入…




 2024年9月17日(割引期間ということでこちらも購入しました。)
2024年9月17日(割引期間ということでこちらも購入しました。)
通常版購入前に、二択と知っていれば特装版を選択したかったと後の祭りで思ったが、存在自体知らなかった。読者には特装版もあるのだということ、どんな違いがあるのかということなど、供給側から前広に伝えておいて欲しかった思いは強い。仮に特装版のことを通常版購入段階知っていたとしても、通常版購入時では特装版がどんな内容なのかを知らず、内容検討出来るほど材料も無く、結局手を出さなかった可能性もあるのだが。
そもそも10巻台に達する頃から少し話の進みが遅くなったと感じて、暫く急いで買い足す気持ちが薄れてはいた。そこへシーモア(島)で13巻の頃から進展があるとの口コミを摑んで購読再開することにしたのだが、買っちゃってから、え?特装版あったとは!?、という経緯。特装版の方がいい…という声も聞こえて胸中フクザツだった。
それでも、お安い期間中に耳寄り島情報をもたらして下さった方のおかげで、この特装版、身軽に動けた。定価で通常版と特装版両方は無理だった。
小冊子が、踏み込んだシーンで頁数を割いて二人の仲の深まりを示すので、二人の成り行きを特に気にする人には本編より満足度高いかと思う。
立花ターンもある。私には多少芝居がかった演出に感じた。
価格のことはあったが、小冊子部分が付加価値と考えると、他の諸問題について考察を深められる訳ではなく、もう少し肉付け材料あっても、との気持ちもある。
さすが少女漫画、蘭の肉付きがずっと読み進めてきた読者の想定を変に崩さず描いてくれたようで安心した。 -
「魔法使いの娘」続編の本作が洗練されてる




 2024年9月14日俗にシリーズ化は最初の作品のインパクトよりイマイチになる、というのが此には当てはまらない。むしろ洗練されてる。小さくあちこちばら撒いているエピソードの欠片、これらの出し方も上手いし、それらを拾い上げさせて最後まで連れて行ってくれるつもりなのだろう。やはり構成力というのか、語りの引きの強さが頁を捲る手に汗?握らせる。
2024年9月14日俗にシリーズ化は最初の作品のインパクトよりイマイチになる、というのが此には当てはまらない。むしろ洗練されてる。小さくあちこちばら撒いているエピソードの欠片、これらの出し方も上手いし、それらを拾い上げさせて最後まで連れて行ってくれるつもりなのだろう。やはり構成力というのか、語りの引きの強さが頁を捲る手に汗?握らせる。
視える人には視える、見えない人には見えない、その怖さ。そして「魔法使いの娘」の時の親子編の一区切り、あれからどうなっただろう?とのこちら読み手の疑問に時折小出しで打ってくる思わせぶり戦略に私は見事に弄ばれる。とある話では、ある決定要素を最後までかわしながら、最後近くになり、ここ、そこ、と切り札のように見せて来ていい緊張感で引っ張ってもらった。その1話完結的な部分をメインに置きながらも、同時並行的に「魔法使いの娘」の続き物としての興味をそそるように、「アレ?この人は?」「いやもしかして!?」、こちらの疑いが次第に膨らんだところで「おめぇには関係ねぇ話だ」とJr.に言わせる、それが逆説っぽくて匂わせてる!なんと鮮やかな煙の巻き方なのだろう。そして初音にそのタイミングで「(今は)会わない」と言わせる絶妙なオチ。見事に次回以降に私の心はついて行ってしまう。
まだ読了まで時間かかると思うが、一旦レビュー書かざるを得ないほど手応えを感じている。
しかし初音が指原莉乃(サッシー)さんに見えることがあるのは私だけ?
残りを読んだら後日追記。
「手伝ってあげたら?」と自分では席から立ち上がろうともしない男が女の子に軽く言うシーン、少し前まであったあった!これは既視感強い。世の中への婉曲メッセージ?
166頁(170/212)の「個建て」は、「戸建て」なのでは?
狐が化けるというのは幼いときに自分の祖母も話していた。占いも信じないような人だったけれど、子供の頃夕暮れ時の帰り道、後ろをついてくるように歩く女の子が居て、気になってまた振り返ったら狐が道端へ走って行ったと言っていた。
作品ではいろいろ化けたり化かされたり。それらの世界がすぐ傍にある設定。
「逐電」とは、逃げて行方をくらますこと、と初めて知った。
兵吾、とてもいい奴になって初音に都合よくなりすぎてなんだか可哀想。運命か?
2010年4月号~2017年2月号、付属小冊子。Wings誌。
30話にスペクタクルな感じの最終話で計31話。前後編物は1話でカウント。 -
怖すぎないオカルティックストーリー




 2024年9月11日父親が非常に珍しい職業に就いてる為、まわりに占い師と思われていることに乗っかり本当の所を秘密にしながら、なんとか平穏に暮らしたい主人公。親の職業故に様々なトラブルをに巻き込まれる娘として、また当人も親の能力みたいなものを受け継ぐ運命にあるが、複雑な家庭事情が横たわる。
2024年9月11日父親が非常に珍しい職業に就いてる為、まわりに占い師と思われていることに乗っかり本当の所を秘密にしながら、なんとか平穏に暮らしたい主人公。親の職業故に様々なトラブルをに巻き込まれる娘として、また当人も親の能力みたいなものを受け継ぐ運命にあるが、複雑な家庭事情が横たわる。
セールにて全巻買い込みまだ完読していないが、勿論読破のつもり。続編のほうも直後の別の機会に手を伸ばしていて最後まで一気買い、楽しみにしている。
第16話の最後のコマの描き方にゾゾ~ッとして、途中だがレビュー書きに来た。
那州先生はやはり才気走った漫画をお描きになる。それなのに大上段に構えた勿体ぶりがなくて、むしろある程度脱力の雰囲気でもって、オカルティックな展開に主人公が仕方なく付き合っている様子の構成によって、保たれる明るさ。反面、主人公の普通(でありたい)の日常を、その傍らによく居るまたは出没してくる“それら”が関わってくることで侵されている不気味さ。
続巻のレビューも追記予定。
18話(前後編形式)は冒頭から那州先生のこれまでの白めの感じを、変えてきた。それまでは背景を余り描き入れずあっさり人物だけのコマが多かったのに、冒頭から随分ベタ?多用で全体黒っぽい印象。
途中出場の超ホーリーパワーの持ち主、面白い。
少し唐突気味登場の人形関連の草壁さん関連エピソード辺りが、判りにくかった。また、秘密の多い無山、本部の登場も唐突感はあった。
しかし、親子編を区切らせ、そして次第に結びつきが強まっていく初音と兵吾との関係、次に繫げられる余地を残しつつ大胆な終了で全8巻楽しませてもらった。
2002年7月号~2009年12月号 (ウィングス)
33話、最終話で計34話と各巻おまけマンガ付き。 -
【無料】ウィングス35周年記念 ウィングス・コミックスSELECTION
多種類大量頁の試し読み出来て楽しいです!



 2024年9月3日百姓貴族という作品に以前から興味があったので、今回来ました。
2024年9月3日百姓貴族という作品に以前から興味があったので、今回来ました。
農家畜産家の方々に頭が上がりません。
引き続き、他に収録された別の漫画家先生方の作品を読んで、追記する予定です(星の数の変更可能性もアリ)。
まだ数作品目なのですがファンタジー味強い作品が多い印象です。各先生方の個性豊かな絵柄で、作品が似たようなのばっかりになってないのも、この種の詰め合わせとしてはひと作品毎に目先が変わって楽しめます。
好奇心が湧いて調べた「パーム」(獸木野生先生←伸たまき先生改メ)が現在43巻配信中と知り、長編っぷりにちょっと怯んでます。未完…。
12作品415頁、創刊時から1980年代まで。
次vol2に行く。13作品529頁、1990年代から2000年代まで。
vol2の方には前から機会あれば読みたいと思っていた「魔法使いの娘」が入っていると知りました。嬉しい。
久世番子先生の「暴れん坊本屋さん」もある。少し前購入済み、全3巻既読で笑わせてもらいましたし、ちょっとしたリアルさが良かった。
「プリンセス プリンセス」面白そうだ。 -
-
各話キュートな超ショート(平均8頁未満)集




 2024年9月2日全3巻表題作関連だけ。全65話プラス各巻に描き下ろし。男子高校生と男性教師ラブ。既に#4から周囲の温かい目とサポートに支えられている当人達の恋路が、もどかしくも微笑ましく読ませる。真っ直ぐだけど互いに鈍なふたり。其処が可愛らしいところ。各話ほぼ一桁で終わってる頁が多い構成という驚異的ショートストーリーの集合体にもかかわらず、小さなエピソードの積み重ねで小さな一歩ずつを進む二人の関係は次第に互いに確信に向かう。各話に籠められた相手への秘めたる想いや謙虚な迄の双方の受け取り方(勘違いの類)が読み手の心を焦らし掴んでくる。遠慮のさまもまたよい。大人の分別もクーッとなる。この短さでそんなに当方にアピールしてくるとは(消化だけの流され回の間延びがほぼない)、かわいらしい頁数なのにすごいと思う。
2024年9月2日全3巻表題作関連だけ。全65話プラス各巻に描き下ろし。男子高校生と男性教師ラブ。既に#4から周囲の温かい目とサポートに支えられている当人達の恋路が、もどかしくも微笑ましく読ませる。真っ直ぐだけど互いに鈍なふたり。其処が可愛らしいところ。各話ほぼ一桁で終わってる頁が多い構成という驚異的ショートストーリーの集合体にもかかわらず、小さなエピソードの積み重ねで小さな一歩ずつを進む二人の関係は次第に互いに確信に向かう。各話に籠められた相手への秘めたる想いや謙虚な迄の双方の受け取り方(勘違いの類)が読み手の心を焦らし掴んでくる。遠慮のさまもまたよい。大人の分別もクーッとなる。この短さでそんなに当方にアピールしてくるとは(消化だけの流され回の間延びがほぼない)、かわいらしい頁数なのにすごいと思う。
主人公紘斗の目が大きすぎると感じることがたまにあったのが残念。可愛らしさの強調かもしれないが、童顔の上に少し乙女な心を持っているキャラを踏まえると、無意識のあざとい演出を勘繰ってしまう。 -
西暦2184年頃人工合成人間ジョーカーがいた




 2024年8月31日人口合成人間の設定その他を受け入れられれば、先の読めないストーリー展開に乗って、ジョーカーの特殊な人生と、ジョーカーに惚れた六道の人生の交錯点の閃光を最終巻第8巻まで、固唾を呑んで見届けようと思うだろう。
2024年8月31日人口合成人間の設定その他を受け入れられれば、先の読めないストーリー展開に乗って、ジョーカーの特殊な人生と、ジョーカーに惚れた六道の人生の交錯点の閃光を最終巻第8巻まで、固唾を呑んで見届けようと思うだろう。
始まりから最後まで、作品はSFとして未来の世界にあって、しかし中の人間達は今とあまり変わりがない生活をし、感情の機微も現代の我々と同じように持ち合わせ、特に機械だらけでもなく、六道は昭和的なアパートに、富裕層はクラシックな洋館風邸宅に住む。
しかし特捜司法官という特殊な任務で日々超人的働きをしているジョーカーらには、非情な現実がある。
六道とのロマンスは人間臭く、六道の日々は切なさが増すし、巻を追うに従い深まるふたりの間柄にある種の緊張は常につきまとう。
スパイスとして恋愛があるのではなく、ふたりの出会いがあっての、ジョーカーの定められた生き方、それに向き合わなければならない六道のやるせなさが描かれている。
しかしアクション物であり、流血シーン多い。人が殺される事が必ずあるようなサスペンス劇場の事件の犯人の捕り物に関わるドラマの裏筋を走る劇みたいに、真相は時に警察を置き去りにして、特捜司法官の手の内で片付けられ、事件一つ一つ一応決着はしていくのだ。巨大な敵との最終決着まで、事件相互が絡み合いながら。
敵の陣営の実態的な大きさが不透明だった。また、究極倒さなければならぬ相手が終盤に至って当初の目的を見失った為に、対立構造は手段の問題ではなくなり、戦う対象がコンピュータに移ったことは、私には作品のゴールポスト変化に感じた。
全8巻。初期は劇画調、段々線が変わっていく。
絵柄が13年間で変わっていくのはある程度仕方がなかったかもしれないが、第6巻106/228の顔アップはもう少しそれまでと一貫性を強く持たせて欲しかった。
六道の同僚のキャラが普通に楽しませてくれる。
利用者コミュニティであるシーモア島で本作品の存在を知った。感謝! -
何処となく寂しかった亮に月が射しかける光




 2024年8月20日可惜夜と書いて「あたらよ」と読む。明けるのが惜しい夜のこと。夜に出歩くことを意味する夜行(やこう)と重ねて、タイトル「あたらやこう」。
2024年8月20日可惜夜と書いて「あたらよ」と読む。明けるのが惜しい夜のこと。夜に出歩くことを意味する夜行(やこう)と重ねて、タイトル「あたらやこう」。
月の夜、主人公亮のもとに使者暁が来た。この世に未練無かった彼は、暁と最後の時間を不夜城の都会で精一杯楽しむ。一見古めかしく華やかな装束の住人と美しい品々などがあるらしいけれど、向こうは不思議な世界、そこでの暁の立場は微妙…。
幻想的で細かいタッチでその世界が描かれてすごいと思った。
タイトルのベースの「可惜夜」も知らなかった言葉だが、堆朱(朱漆を何度も重ねて厚くしそれに模様を彫刻した物)、花氈(美しい模様の織り込まれている毛氈)などもググッてしまった。なるほどあちらの世界の環境が如何なるものかが窺われる。毛氈なら雛祭りの緋毛氈しか知らなかった私は、幻想的で古めかしいようなその世界に当たり前にあるらしいそうした品物に囲まれる亮が想像出来なかった。暁との時間を楽しむ姿は、時間の過ぎるのがいつの間にか惜しくなるのがこの世を惜しむことにも繋がる構図として、儚くも美しい想い出として残すような、とても綺麗な絵を見ているみたいだった。
特別編は幻想無し。主人公の女の子は彼に光を見出していた。
story1:44頁、
story2:42頁、
story3:50頁、
特別編:34頁。 -
思わせぶりな意味深導入部で一気に引き込む




 2024年8月20日本編を持っていてこっちは必要ないのにわざわざ読みに来てしまった。
2024年8月20日本編を持っていてこっちは必要ないのにわざわざ読みに来てしまった。
高校生、夢や希望がこの先いっぱいあると外からは誰もが思いがち。
しかしその実内側に抱えているものが決して小さくない人も居る、ということを、そんな眩しいばかりの日を送っている訳ではない人も世の中には居ることを、もしもあの時知っていれば、との想いが物語を動かす。
半分ミステリアスな始まりから、やはり普通に終わったりしない超常現象的な要素を持つ話なのだが、改めてスターターブックとして本書を読んでみると、日常で何度もあるささやかだけれどその先の事を変えてしまう分岐点、もしも違う選択をしていたら?との思い返しが、忘れられない運命を形作ってしまう、未来からの苦い思い。過ぎてきた日々へ、やり直したい後悔や仲間の救済願望を映して、強い推進力のあるストーリーになった。
高野苺先生のはっきりした絵が、個々の高校生達の毎日をごく自然な日々として描く中に、誰しもとても身近な同級生にあったら抱くであろう想いの強さを重ねて印象を強くしていく。そして、彼はなぜ?と、その過去を受け止めた現在の仲間たちの姿が平行してあり、ある一時期のことが皆の心に影を残しながら今を生きているという前提で紡がれる。
その平行の状態は、それだけではなかったが。
若くから瑞々しい漫画で沢山の読者を牽引したお力が端々から見える作品。これ程上手いのに、クリエイターにとって良好な環境のキープというのは、大変なことだとつくづく痛感する。 -
この先が読めない、読みたい。読ませてよ~




 2024年8月19日8巻以降相当の43-45話。田中さん、笙野、朱里ちゃん、それぞれが自分の相手と向かい合ってお付き合い開始。
2024年8月19日8巻以降相当の43-45話。田中さん、笙野、朱里ちゃん、それぞれが自分の相手と向かい合ってお付き合い開始。
皆自分の事情があって今がある。
笙野の両親のありよう、昭和には居た居た! 家のことをキチンとやらなくては外に出るな、と言い出す夫に、経済的自立が出来ずに妻は泣き寝入り的に従わなくてはならないケース。
相手の望みをキチンと訊く前に自分の考えを押しつけて平然としてる人間があちこちに棲息してた。喫煙者が大手を振るって非喫煙者に不健康を強いるだとか、公然と女子は学歴あると可愛くないと声高に言って従順を強いるとか、私の時代には自分を主張したりする女性は「怖い」などと揶揄された。
少しずつはその生き辛さはなくなったが、年号が変わってもなかなか変化はしなかった。男性もまた、私の時代は女に負けたら恥ずかしいと思え、などというアホみたいな男子教育をされた頃から、少しずつ男はなになにであらねばならぬの呪縛を解き放たれてきたものの、女子の領域視されたところからは弾かれていた。
小さなことが集まれば確かに幸せの理由となることは納得出来る反面、キャラ達が生きてきたこれまで蓄積的に形成されてしまった価値観はすぐ変えられない。でも作品は、ベリーダンスを中央に置いて、皆がきっかけを経て少しずつ硬い殻を壊していく。そのプロセス、そのときどきにそれぞれやってることが正しいことだったかどうか今はまだ判らないなりに、選んでみた事を兎に角進めている。自分の選択に曲がりなりにも各人肯いての行動だ。
本作は本当にいろいろ考えさせられる。これまで自分を形成してきたもの、これから自分が見る世界。
そして登場人物達のこの先は、芦原先生に見せていただきたかった。
46話以降が読めないのが悔しいし悲しいし今でも胸が痛い。読み手は直接間接の原因をどうしたって考えない訳にはいかない。お疲れになってしまった…。先生に煩わせる必要のないところに先生お一人のエネルギーが多大に浪費された。消耗し、本来注がれるべき続きの部分から結末までに至る漫画制作への余力を殺いでしまった。作品や先生への理解度が深かったら、作品弄りへの不毛な試みなど生まれる余地も減ったのに。赤ペンを入れる作業はハタが思うほど楽ではないのに、独りだけに任せた挙げ句…。文法違う畑で苦労させられている人を思いやるのは、させるよう追い込んだ側の責任なのに。味方居なかったのか。 -
頻繁に笑わされたが、どこか不憫さを誘う




 2024年8月17日裏目裏目に出て、それで当人の思いもよらぬ方向にどんどん話が膨らんでいく。口下手な女の子の巻き込まれ事件のスケールは遂にメディアにまで!
2024年8月17日裏目裏目に出て、それで当人の思いもよらぬ方向にどんどん話が膨らんでいく。口下手な女の子の巻き込まれ事件のスケールは遂にメディアにまで!
でも、皆に悪意はないので読んでいて面白さが勝手に出来上がっている感じ。
という、止めたいのに止まらぬ流れに、彼女は最後の最後は乗ってしまうが、その最後まで見事に付き添う加原クンにも不憫さがある。
思惑の擦れ違いばかりを見せつけられながら、結局は幸せを周囲にもたらしていくのだから、凄いことは凄い、そんな連鎖的な現象の目(中心地)に小結りぼんは居る。
目つきがギャグ漫画なのに、おかしみをもたらしながら当人は真面目、加原クンの空回りがストーリーの笑いに加担しているのに、もはや悲哀まで読み手の私は感じてしまう。
二人のやりとりは外形としては進展している体ながら、実態は加原クンの「やっとそこ?」の認知で始まったばかり(笑)。でも此処からスタートだ!
これは加原クンの努力が今後報われることを応援したくなる。1巻完結。 -
主人公みつみが目一杯高校生活を謳歌する




 2024年8月17日最新巻10巻まで読了。結構あっちこっちホロリと泣かされた。それでいて高校生達の日々の頑張りにエネルギーチャージもさせてもらった。うまく行くことばかりじゃない人間関係の中で、考えたり伝え合ったり行動したり、読んでいてキャラ達が生き生きしている。みつみの回りのキャラの心境も描かれるので多面的に物語を読んでいけて、彼等の毎日へ、善し悪しでは捌ききれない人間模様の絡みがいい。
2024年8月17日最新巻10巻まで読了。結構あっちこっちホロリと泣かされた。それでいて高校生達の日々の頑張りにエネルギーチャージもさせてもらった。うまく行くことばかりじゃない人間関係の中で、考えたり伝え合ったり行動したり、読んでいてキャラ達が生き生きしている。みつみの回りのキャラの心境も描かれるので多面的に物語を読んでいけて、彼等の毎日へ、善し悪しでは捌ききれない人間模様の絡みがいい。
身近に何人も都内難関高からそこに、というケースが居るが、彼等もちゃんと真っ黒ではない高校生活してたのでリアリティ無しとは感じなかった。
読み物探しでかなり前に本作を最初に見かけてから作品調査の折、既に高松先生のお身内のことは知っていた。それでも今回やっと読むことになり10巻巻末に来て先生の言葉によって感じたことは、どうしたらいいか判らない無力な読み手にしか過ぎない自分を自覚させられ、ビックリするほどもっと衝撃が強かった。作品を通じて感じ取ってきていたモデル珠洲市への親近感が、地震により起きてしまっている「現実」で大変なことになった…、ずっと大きな存在感に変わった。 -
幕末動乱から薩摩藩視点で




 2024年8月16日現状最新巻第4巻まで読了。「だんドーン」の語も本編中に出てきた。
2024年8月16日現状最新巻第4巻まで読了。「だんドーン」の語も本編中に出てきた。
ハコヅメが面白かった為に、また、本作の始まりにかけての泰三子先生ご自身の出来事とその後の編集の方との日々のことを読んでから、本作への期待は最高潮だった。
堅苦しさを外すことが主眼だったのか、生臭みや敵味方の出し抜き合いなどの激しさを緩和した感のあった助走状態の初期に比べて、次第に時代故の情勢の揺れが容赦なく登場人物達の強烈な短く太い人生描写になっていて、4巻に至っては私には読んでいてキツかった。更に混迷を深める維新前夜の日本を、いくらコメディと謳っていても実は流血不可避のエピソードを乗り越えて読み続けるか自信が無くなっている。読者層が青年向けであるからして内容に下ネタがこれ程あって受け入れられているのだろうが、実にその方面の題材がストーリーに結構大きく振られていること、そのことで、レビュー書くのに私は躊躇いも小さくなかった。
タカの存在も泰三子先生の創作力のお力と思うものの、多賀者、犬丸と家族エピなど考えるとウーム…複雑な印象。
川路の出番が相対的に薄まり、説明色強めになっているところも、単純に川路とその極周辺の川路から見た景色をもっと見たい私には何かが燻る。
まだこれからだと思いたい。が、同時に、横道に逸れた印象が強ければ次巻は柱はなんなのか、という意味では早くも正念場なのではないのかとの思いも強くしている。
星の数は故に暫定です。 -
お弁当が…!!




 2024年8月16日1995年12月全5巻。第1巻45頁、第2巻42頁、第3巻40頁、第4巻38頁、第5巻40頁。
2024年8月16日1995年12月全5巻。第1巻45頁、第2巻42頁、第3巻40頁、第4巻38頁、第5巻40頁。
主人公の頑張りは相手に届いているように見えないけれどもそうでもないのがミソな話。第4巻は松木君ちょっとヘタレ。こそこそしてるのでもなし、かといってサクサク関係が進むのでもなし、不器用に相手に向き合う二人のプロセスの二人そのものよりも環境描写に味があると感じた。
好きな娘にお弁当作りして落として結婚にこぎ着けた後輩を知っている。ちょうど1990年代には、男の子から女の子に対しても有効な手段ではあったのだ。
しかし本作品、数々のお弁当の結末のほうはなんだかほろ苦い。結果オーライとはいえ、お弁当に籠めた想いが行き場がなくて、読んでいてやりきれなかった。
高校生で作家デビューといえば(敬称略すみません)、新井素子、島本理生、綿矢りさ、羽田圭介と古くから数えきれず、中2でデビューの鈴木るりか、外数名を考えると、存在自体は知られており、本作の主人公が決して荒唐無稽ではないところが絶妙に興味深い設定となっている。
学校放課後や通学路の光景、部活を眺めるところなど高校生らしさを見せながら、若くしてプロ意識をしっかりと抱くのも素敵なこと。少女漫画界では十代デビューが昔からあり得るだけに、作品世界の見せてくれるものが単なる学園恋愛物に留まらなかったことが、私の眼には、甘えてばかりの状態を見せつけられない構成に対して好ましく感じ取れた。それが、高評価とさせていただいた理由。 -
りぼんの騎士からの系譜、萩尾氏の創作技法




 2024年8月15日講義やインタビューを基にしている頁が多い事から、本書は先生の生の語り口そのままに著されており、読んでいてそこに私も聴衆の一人となったような気分になれる。少女漫画を愛好する者として、先生の見立てによる少女漫画の系譜の概説は本当に愉しかったし、先生の少女漫画観を知れて良かった。少女のロマンを漫画という特異な表現技法で仮想現実化、それも少年漫画よりも枠をはみ出たコマ割りを駆使しての心理表現と外見上の事実描写の多重性。大人になっても少女の心に戻って読む読み物。作り手が描きたい物と世に送り出す出版社の編集側との思惑のズレ。内容には正に解説者諸氏の言うところのインサイダーとしての視点もあり、熱心ないち漫画読者としての俯瞰的視点もまたあり。読んでいてフムフムと何度もど真ん中の話に冷静に首肯。それでいて萩尾先生の創作の裏側の工夫や葛藤、アイディアの降りるのを待つところ、頁数調整の話、天才の人となり?が窺えてそれも良かった。
2024年8月15日講義やインタビューを基にしている頁が多い事から、本書は先生の生の語り口そのままに著されており、読んでいてそこに私も聴衆の一人となったような気分になれる。少女漫画を愛好する者として、先生の見立てによる少女漫画の系譜の概説は本当に愉しかったし、先生の少女漫画観を知れて良かった。少女のロマンを漫画という特異な表現技法で仮想現実化、それも少年漫画よりも枠をはみ出たコマ割りを駆使しての心理表現と外見上の事実描写の多重性。大人になっても少女の心に戻って読む読み物。作り手が描きたい物と世に送り出す出版社の編集側との思惑のズレ。内容には正に解説者諸氏の言うところのインサイダーとしての視点もあり、熱心ないち漫画読者としての俯瞰的視点もまたあり。読んでいてフムフムと何度もど真ん中の話に冷静に首肯。それでいて萩尾先生の創作の裏側の工夫や葛藤、アイディアの降りるのを待つところ、頁数調整の話、天才の人となり?が窺えてそれも良かった。
「作品に対して持っているイメージが非常に強い場合には、映像化の依頼があっても引き受けることはできません。」としながらのイグアナの娘の話も面白かった。
少女漫画に特徴的な恋愛物の多さについて王道の分析をされながら、一方講義後半部、極めて実験的というか他の作家はあまりしないユニークな手段で描かれた、ご自身の数作品の制作舞台裏のような細やかな解説は、先生の際立って確立された少女漫画界での特別さを感じさせて、読んでいて興奮してしまった。女性漫画家人生が編集との相性次第なのは良く聞くが、良好な関係を築けていることを感じ取らせるのも良かった。
インタビュー内の萩尾先生の自由な言葉の数々に、矢内氏との間柄が良いこと、また萩尾先生へ敬意を隠さない姿勢を感じさせて気持ちよく読んだ。
42%過去のペンネーム誤植の件胸が痛んだ。
実は「少女の少女による少女の為の」の、本書の骨子的な矢内氏の言葉には、私は引っ掛かりを覚えないでもない。言いたいことは判る、がしかし、この言い切りには極端さのリスクを感じている。無論少女の心の持ち主の読者がメインターゲットのジャンルであることは核として間違いないし、そうあり続けて欲しい。私には少年漫画の過度のバトルや強い線が苦手だから。それでも少女漫画の境界はやや曖昧さが欲しい。でなければならぬ、というのではなく、描き手読み手は門戸開放、少女の為のだけ残して。 -
オクテ女子にやってきた最高の恋愛とその先




 2024年8月15日ご都合主義的な展開など感じさせないで実は女の子が抱く願望をうまく拾い上げており、温かくて順調な関係進化を見せてもらう。会社が異なるが取引先なのも年齢設定も趣味に理解ある設定もとても活用されていて、そこが面白さを出してると感じる。彼の申し出に不自然さがでない筈はないのに、彼ならアリと思わせるのは、漫画あるあるの設定だからかも。それでも彼の執着の小出し描写効いてる。あんなに何もかもある彼が?というところに魅力を持たせているけれど、虫オタク友だちの背景を挟んできているので、取って付け感よりも性格描写に膨らみを感じた。
2024年8月15日ご都合主義的な展開など感じさせないで実は女の子が抱く願望をうまく拾い上げており、温かくて順調な関係進化を見せてもらう。会社が異なるが取引先なのも年齢設定も趣味に理解ある設定もとても活用されていて、そこが面白さを出してると感じる。彼の申し出に不自然さがでない筈はないのに、彼ならアリと思わせるのは、漫画あるあるの設定だからかも。それでも彼の執着の小出し描写効いてる。あんなに何もかもある彼が?というところに魅力を持たせているけれど、虫オタク友だちの背景を挟んできているので、取って付け感よりも性格描写に膨らみを感じた。
当初は一生独り身と考えていた主人公なだけに恋愛描写も控えめだったが、巻が進むにつれ段々ベッドシーンも進んできており、現状7巻まで読了したがこの先悩む。それが嫌というのではないのだが、ここから引き延ばされてもという気持ち。
世間からはかなりなハイスペに入る甥っ子がもっと年の差婚なので今どきの男女の年齢に特別感減ってきているが、妙齢だが恋愛要素が無かったこれまでと打って変わって突然青春到来の女の子の悩みと、亜蓮の真摯な姿勢のリアルには微笑ましさを覚えてしょうがない。 -
初々しい彼女が可愛らしい真面目なカップル




 2024年8月15日21話から24話を割引期間中に単話購入。他は巻買いしている(既刊7巻。7巻まで読了した)。
2024年8月15日21話から24話を割引期間中に単話購入。他は巻買いしている(既刊7巻。7巻まで読了した)。
話の流れは王子様的ハイスペな彼が主人公にのめり込むという、少女・女性向け漫画にあるあるパターンだが、もうひとつのパターンであるところの彼が割と年下という要素が組み込まれてる。当初のお試し関係からの発展は、気持ちに気づいていくプロセスに萌えたっぷり。優しく前向きに育み、面倒くさいグダグダ多いとは言えないから、彼ののめり込みぶりは読み手のこちらの爽快な快感を誘う。少しずつ歩みを進めるふたりに可愛らしさを覚えつい応援気分になる。
亜蓮くんのスーツ姿はスッと丁寧に立ち姿とかを描いていて、イケメンポジション裏付けはOK。
但し普通の女の子が王子様と、的な配置はなかなか作品としての印象付けが難しい。「どうして」の点には工夫がされているが、感情には理屈がそもそも要らないこととそこまで相手にはまり込んできてる状況とのバランスは、もっと私には見たいところ。 -
考古学者キートンにはドナウ河発掘の夢が♪




 2024年8月3日オプ(保険調査員)を副業とする男、平賀=キートン・太一。かつてとある組織の教官(マスター)だったこともある程の特殊スキルを持つのに、外見からは想像がつかない。回りの人間関係とその配置で第1巻は、彼の秘密を少しずつ解いていくように読み進められてワクワク、アクションも人間ドラマも入り飽きることない。シーモア(島)で絶賛されていたので手に取り評判に違わずの面白さを感じ第2巻まで入手読了。価格が張る為全巻一気買いは出来ない。幸いどれも1話から2話程度で纏まっている。少しずつ買い進めるつもり。今の処それだけの価値を感じている。冒頭から圧倒される海外の景色は写真等既に豊富になった資料を基に描けるだろうが、エンタメ性に溢れ、それぞれの国や地域の感じが出ているので、世界を股にかけるスケールを堪能。世界各地の人々の多様な感じは其処迄感じ取れたわけではなかったが、第2巻の病、アレクセイエフ(辛かった)のエピは国を跨いだ政治に振り回された感じを味わいつつ、背後の事情として、巧みな人間ドラマが素晴らしい。
2024年8月3日オプ(保険調査員)を副業とする男、平賀=キートン・太一。かつてとある組織の教官(マスター)だったこともある程の特殊スキルを持つのに、外見からは想像がつかない。回りの人間関係とその配置で第1巻は、彼の秘密を少しずつ解いていくように読み進められてワクワク、アクションも人間ドラマも入り飽きることない。シーモア(島)で絶賛されていたので手に取り評判に違わずの面白さを感じ第2巻まで入手読了。価格が張る為全巻一気買いは出来ない。幸いどれも1話から2話程度で纏まっている。少しずつ買い進めるつもり。今の処それだけの価値を感じている。冒頭から圧倒される海外の景色は写真等既に豊富になった資料を基に描けるだろうが、エンタメ性に溢れ、それぞれの国や地域の感じが出ているので、世界を股にかけるスケールを堪能。世界各地の人々の多様な感じは其処迄感じ取れたわけではなかったが、第2巻の病、アレクセイエフ(辛かった)のエピは国を跨いだ政治に振り回された感じを味わいつつ、背後の事情として、巧みな人間ドラマが素晴らしい。
全般的に、会話よりも説明的なコマがどちらかと言えば多い印象が私には少々残念。
薔薇色の人生、屋根の下の巴里の2話が、キートンのオプとしての大活躍とは違うエピソードなのだが、作品の魅力というよりもキートンの考古学者人生というほうを感じさせて、私にはこっちに惹きつけられた。
あと10巻割引になる機会も探しながら、体力続く限り少しずつ買い進めて読破したい。(付記-「年年歳歳 花相似たり 歳歳年年 人同じからず」の詩を大河TV「光る君へ」で扱い、自分には今が読む最適の時と勝手に感じてしまった。)
…あれ?、ロイズ保険組合の裏書人って保険会社各社の裏にいるのでは?
ver.4-CHAP.5「秘めたる宝」、いろいろ納得が(私は)行かなかった。その次のも、やりたかったことは判るが、作品内人間関係上の無理を感じている。
北アイルランド問題は連日胸の痛む国際ニュースを当時読んでいただけに、今日ここを読んで改めて思いを馳せてしまった。
英国メインの話も多い事から、私の関心ある中東間の対立のことも英国との関わり切り口で採り上げられていて手応えがある。私の最大関心領域である国際政治テーマのエピはどれも惹かれる。
vol.6終わりの方からごくたまにオトナ場面描写が…。あとvol.7chap.5はえっ?。vol.8バルセロナ再訪したくなる。東独矢張り行っておきたかった。6-7星! -
私の婚約者を奪った男爵令嬢がなぜか懐いてきます~麗しの令嬢♂のはかりごと~【単話版】
トンデモ展開が振り切っていて楽しませる



 2024年8月2日1話だけでも随分面白かったが、4話5話が輪をかけてあらぬ方向に進み、決着方法にも捻りが効いて最後まで普通に終わらなかった。例の人の登場には戸惑ったが、あくまで役に徹しているところが首尾一貫とも、考えられ、それもいいかも、と納得させられた。
2024年8月2日1話だけでも随分面白かったが、4話5話が輪をかけてあらぬ方向に進み、決着方法にも捻りが効いて最後まで普通に終わらなかった。例の人の登場には戸惑ったが、あくまで役に徹しているところが首尾一貫とも、考えられ、それもいいかも、と納得させられた。
試合の勝負、ついておらず挑み続けて…というのはアリなのか?
話の面白さで隠れていたが、一途で純粋に思いを寄せる姿と、ぞんざいな対象に取り繕いもせずに見せる姿、プレゼント選びの好対照などが描かれてなかなかグッとくる。更にどんな些細な会話やエピソードも大事にする彼(?)の、主人公スカーレットに対する接し方は、外見とは別に情の深さが窺い知れて良かった。
それにしても幼児期のこととはいえ、スカーレットの記憶は…
第1話53頁、第2話23頁、第3話34頁、第4割27頁、第5話18頁、第6話45頁。6話完結。 -
思春期読切短編集5作品を全4巻でいい感じ




 2024年8月2日表題作31頁、「アズユーライキット」30ページ、「かわいいなんて言わないで」32頁、「君に染まるころ」30頁ー同時収録「No longer」16頁。
2024年8月2日表題作31頁、「アズユーライキット」30ページ、「かわいいなんて言わないで」32頁、「君に染まるころ」30頁ー同時収録「No longer」16頁。
定番学園物少女漫画の路線で、ツボを押さえたストーリー展開、それなのにどこかにフレッシュな実力を感じる漫画家だと思った。こちら読む者の共感を得やすい主人公の想い、相手の行動へのリアクションなど、見ていて読み終わりに読み手がホッとする迄の持っていき方が手堅い。
十代終わりに一時期だけ赤面症に陥った自分にはそこまでの悩みではなかったけれども、心情が充分手に取れる。この1巻目だけを読んだ方が多いように思われるが、他の巻も主人公の引け目や戸惑いや素直になれないところなど描写巧みで引き込まれる。
ただ、男子に踏み越えてきて欲しい女子の手前勝手な願望が、少々の強引さを伴いかなり彼らは大胆不敵に主人公達を翻弄、なかなかそこまで馴れ馴れしく来れないのが、世の中の現実ではないかとは思った。
また、言ってしまったことは取り返しがつかない。よく心にもないことを言ってしまったと詫びるストーリーが古今東西有るけれど、受け取った相手の心の衝撃に無頓着、かつ、詫びることで簡単に修復する話が多いのは、読んでるこちらが安易だと感じることがある。ま、しかし本作は、リカバリー場面でリスクを背負っている点で、バランスを感じた。
1巻の単行本となりそうな物を手頃に読める企画からか4巻に分かれているため、星数を話毎に考えてみると、表題作4、第2巻3、第3巻3、第4巻の2作品それぞれ4で、最終的に総合4へ。
手書き文字が詰まっていて読みにくい所が少しある。 -
女の子のロマンチック思考に応えてくれる?




 2024年7月28日相手が同じテンションでいてくれるなんて事、その方が難しい。憧れ、理想、夢のシチュエーション、絵に描いたような彼の一挙一動、期待する方が無駄、と思うのだが、そこは主人公を並外れた恋愛脳の持ち主とした設定で走り通す。一方彼は当初そんな子には付き合いきれない感を打ち出すも、積極攻勢に詰められていく。関心が動かされて…。
2024年7月28日相手が同じテンションでいてくれるなんて事、その方が難しい。憧れ、理想、夢のシチュエーション、絵に描いたような彼の一挙一動、期待する方が無駄、と思うのだが、そこは主人公を並外れた恋愛脳の持ち主とした設定で走り通す。一方彼は当初そんな子には付き合いきれない感を打ち出すも、積極攻勢に詰められていく。関心が動かされて…。
気づいてもらうのを待ってるばかりで受身多くて相手のほうから好きを言わせるストーリーより、私はこういうパターンの方が何倍も好き。相手に言わせる周到さ我が身可愛さの姿勢に、寧ろ女の子の傲慢さとか(勇気の無さが後ろに有ったとしても)を見てしまう。もちろん、堂々と言葉にして申し込む行動を男の子にしてもらえたら女の子は嬉しい。そこは判る。
けれども、こういう、女の子から構ったり、強すぎないアピールや、素直に願望を口にすること、ずるさがなくて捨て身な頑張りが素敵だと私は感じる。男の子にしたってノックされて心に来るものがある、という様な描写が来て、あぁ良かったね~、と応援気分が上がるのだ。
冒頭の田島君を認識するところと、そのきっかけのエピソードのたじま君の存在は、話がそうなるかもしれないとのこちらの予想そのままで、多少の物足りなさは有った。
人物の絵、特に主人公の顔の造作が相当アッサリなのは作風なのだと認識していたが、却って平凡で普遍的な日常感が出てると思った。高校生のバイトやバイク通学、校内行事の後の校外での打ち上げ、校内カップルの行動などを無理なく彼らの毎日に溶け込ませる効果はあったと感じる。
2巻以降のストーリー展開は先述の通りややありがちな傾向ありながらも、ロマンチックの反対を行っていたかのような田島君が1巻から3巻に至るまで、主人公の嗜好を合わせてくる歩みを楽しめたのは良かった。判らないながらも、少しは彼女への理解に努める姿勢が、そのまま突っぱねていた様な無粋さ無骨さを抜け出して、彼女の世界に来てくれた優しさとなってくる。無意識なプライベートスペース侵蝕感もいいけれど、彼女の希望に沿ってみようとするところが読んでいて、彼の変化になんとも言えない気持ちになる。 いいね
0件
いいね
0件 -
想い出の恋vs.今から始める恋




 2024年7月25日本作で音楽は添え物的。それでも入口はいつも音楽。
2024年7月25日本作で音楽は添え物的。それでも入口はいつも音楽。
再会した彼は前とは違っていた。普通に何かが無くても年月が人を変える、そういうことは結構世の中ありそうなのに、彼には他にも何かがあった…。主人公が空白期間のことはほじくらずに接していると、彼のほうは突き放すようでもあり、何かと関わりが出来てしまう近さもあり、なんだかんだと結局惹かれてしまう自分を自覚。引き摺って過ごしたその後と、未練との闘い、面影を見つけてしまう自分を持て余す感覚、人を好きになったときのいろいろ揺れる気持ち、よく出ていて身につまされる。
主人公の心情の採り上げ方は、読んでいて恐らく読み手の共感力に相当訴えるものがあるだろうなぁと思った。
主人公の知らない彼のことがまだ多くて(今後発売されるであろう)続巻への興味を繋ぐ。
ライブハウスのシーンはもっと欲しいと思ったが。
あと、ピアノ弾く手の指の絵が、少し違う気がする。ここまで既刊分2巻の読了。 -
もう引けない、わかってて止められない




 2024年7月25日超短編BL。
2024年7月25日超短編BL。
恋愛は頭でするのではない(実際は脳であっても)から、感情が存在してしまう以上、何をも自分を押し留められない。年齢差(1つ目)?立場の違い(2つ目)?家庭(3つ目)?それら全てが自分に警告を発していても、踏み越えてしまう。
そんな本質を描いて、一見冷ややかに見える彼らはその内側では実は熱く燃える何かがあるのだと匂わせる。そして身体は正直であると。
あれは過ちであったのか始まりであったのか。読み手の想像で物語のその先は続けられていく。
代表作のひとつ「キス」では主人公のピアノの先生は、主人公にほとんど見せないセクシュアルな影が過去の一時期として描かれることによって、先生のそうした一面を裏に貼り付けて造形されていた。
本作の店長も、その実何を秘めているかわかりゃしない。マツモトトモ先生の巧妙な構成でストーリーは意外な方向へ皮が剥け始めて、店長の魅力に嵌まった主人公はもう引けないところにいるのだ。
二人は止まらないだろう、との暗示を私は思った。構って構われての関係の冒頭を思い返すと…。
ずるさでかわす店長、そう泳がせているのは主人公の巧みな(接客に通じる)誘い言葉、形では逃げの余地を作られているので安心して(?)、渋々(であるかのように)乗る姿を、予感した。 -
面白さ再び




 2024年7月25日既刊2巻にして現在レビュー件数70余件、これは、8年くらい前に本作の前のシリーズ「アシガール」で私がレビューをいっちょ書いておいて面白い作品だってたくさんの人に分かって貰いたい、と思ったときのレビュー件数と多分同じくらいの数。でもあの時は既にかなりの巻数が世に出ていた。
2024年7月25日既刊2巻にして現在レビュー件数70余件、これは、8年くらい前に本作の前のシリーズ「アシガール」で私がレビューをいっちょ書いておいて面白い作品だってたくさんの人に分かって貰いたい、と思ったときのレビュー件数と多分同じくらいの数。でもあの時は既にかなりの巻数が世に出ていた。
それを思うと、アシガールの面白さがこの続編への期待値をこうまで押し上げていることは感慨深い。
タイムマシンものはSFでは使い古された感あるにもかかわらず、面白さをまだまだ追求できる余地があることは、今でも充分新鮮なSFジャンルの立派なツールなのだなと感じる。実際今回もドラえもんの手で、今度は主人公の月(「たま」の身代わり)が新たな目くらまし(?)を繰り出すのが、あぁ血は争えんと、可笑しかった。
速川家の皆さん(唯の方様以外)の登場も楽しいし、新キャラ、特にたまの有能なお付きの二人の暗躍にも期待がかかる。楽しい作品をいつも森本先生ありがとうです。 -
-
歌、曲作り、手探りの道探し




 2024年7月25日出逢いの妙があるはずでそれこそが3人の始まりなのだが、偶然の作られ方や三人其れ其れの環境設定に何となく強引さとドラマ用に盛り立てあげられた印象は残った。
2024年7月25日出逢いの妙があるはずでそれこそが3人の始まりなのだが、偶然の作られ方や三人其れ其れの環境設定に何となく強引さとドラマ用に盛り立てあげられた印象は残った。
音の出ない漫画で音楽を表現することに興味があって来た。聴いてる側の反応メインに描かれ、それも見せ方だなと思うものの、彼らの音楽に対する直接の雰囲気はあまり良く感じ取れなかった。
ユマの有名人ぶりと、実はクラブとかは学校には秘密というのが結びつかない。一方、栞の当初の謎っぷりに比較して次第に分かってくる家庭環境は、別の意味でギャップ。三人の化学反応は今後続きをいつか描きたい作り手の想いもあるのか、これからもっと、という期待感でストップ。実はいろいろ進んだようでいながら、解決したとは言い切れないいろいろが、読後もどかしい。
しかし、それぞれ自分の「壁」に苦しみながら、夢や勢いでなんとか進む姿は、今を生きてる若者という感じがして、めげずに道を求めている彼らの未来の成功を応援せずにはいられない。それくらい、自分達の音楽表現にこだわり、自分達の発信スタイルを探し、この組み合わせ(3人の)で行こうとする結束力、そこはとても良かった。
主人公のトレーニング自体は理解するが、彼女の取組の動機?、継続するだけの意思(意地)の強さについて、もっと何か欲しかった。
168頁+おまけ4コマ漫画3頁。 いいね
0件
いいね
0件 -
気鋭の漫画家の作劇巧者ぶり、いい形で開花




 2024年7月25日表題作は前中後編と巻末おまけで、108+5頁、同時収録「科学者と幸せな薬」26頁(2015年)、「待宵の月」14頁(2017年)。
2024年7月25日表題作は前中後編と巻末おまけで、108+5頁、同時収録「科学者と幸せな薬」26頁(2015年)、「待宵の月」14頁(2017年)。
いずれも捻りがあって、しかもそのためだけにストーリーが徒に回っているわけではなく、起伏に無理がなくてダレもない。表題作の、眠りから目覚めさせるマジックが二重に仕掛けられているのは、読み終わってみればニヤリ、だが、「科学者と幸せな薬」には完全にやられた。作者あとがきの「ミスリード」、実にお見事で。「待宵の月」では14頁しかないことが読んでいる最中には少しも障害ではなく、あとになってから実は語っている内容は豊かでありながら、話の種明かしのなんともいえない上手さに、本書3回目のノックアウト。
絵も少女漫画的に満足しているし、3作品が被りあわない為、広がりのある作品集となった。
私も「ボクと姉の結婚」からやって来たのだが、このストーリー作りの上手さは、土台がオーソドックスでもこれだけのことが展開できるのだよという確かな腕を見せつけてるのと同じ、十鳥さる先生にはこれからも末永く活躍されて欲しい。 いいね
0件
いいね
0件 -
少女漫画誌で異彩を放っていた弓月先生作品




 2024年7月24日男女間の感覚がほかの少女漫画と違った面白さがあるので、弓月光先生の作品は印象的だった。「白い変人たち」のみ一部既読の記憶あるも全部は読んでなかった。週刊マーガレット誌掲載1977年20,21,22号。計102頁。同時収録は「アマゾネス・サンバ」同誌1982年33号51頁、「負けるな!ヒーロー」同誌1980年36号43頁。
2024年7月24日男女間の感覚がほかの少女漫画と違った面白さがあるので、弓月光先生の作品は印象的だった。「白い変人たち」のみ一部既読の記憶あるも全部は読んでなかった。週刊マーガレット誌掲載1977年20,21,22号。計102頁。同時収録は「アマゾネス・サンバ」同誌1982年33号51頁、「負けるな!ヒーロー」同誌1980年36号43頁。
私は3作品とも終わり方が気に入っている。とかく少女漫画のエンディングは割と紋切り型といおうか、暗黙の永遠の陳腐さがあって作品の個性を潰しているのだが、本書の場合はそんな読後感の画一的甘ったるさを揃えてきていない。そのサラリとした、そっと置かれていった後味が良い。
弓月先生作品にはちょっとエッチな感じがよく有って、それが「アマゾネス・サンバ」に出ていた。
「白い変人たち」はスキー、「負けるな!ヒーロー」は野球で、いずれもロマンス絡むも、部活を巡る青春物。「白い変人たち」は主人公の頑張りのオチがクスッとなる。「負けるな!ヒーロー」では女の子の一歩も二歩も前に出る感じが良い。引っ込み思案で奥手で地味な女の子で、などといった、これまた少女漫画世界でパターン化された女の子でないところが、私は良いと思っている。
絵は目に特徴のある弓月先生画風で、男の子は少年ぽさが残り過ぎなのが少し惜しいのだが、女の子の身体の線が少しなまめかしくそれでいて肉感特別には強くなくで、弓月先生の描く女の子の微妙な女の子っぽさが良い。
「アマゾネスサンバ」はスケールが大きい話で、細かいことを考えなければミステリアスな秘境での冒険活劇で、頁数にしてはエピソード満載してる娯楽作品。男の子サイドから描いている「負けるな!ヒーロー」の女の子は作者の理想が多分に混ざっているように感じてしまうところはある。それでも、そんな子も世の中もしかしたらいるのかもしれないな、とは思う。 -
おもしろ可笑しい化獣の世界、狸を中心に




 2024年7月19日笑える漫画で愉しいひとときを過ごすことが出来て、素敵な気分転換となった。コメディ強い中で、狸の糞の生態が出て来たりして、私も気になって検索して狸を調べたりしていたからそういう描写に感心。狸は狸に、狐は狐に見えるのもすごい。キャラそれぞれのアクがストーリーをてんでに色づけて、賑やかなようでそれだけではない身内的な情を見せてくる。正体は全員が判ってないのも巧い展開。
2024年7月19日笑える漫画で愉しいひとときを過ごすことが出来て、素敵な気分転換となった。コメディ強い中で、狸の糞の生態が出て来たりして、私も気になって検索して狸を調べたりしていたからそういう描写に感心。狸は狸に、狐は狐に見えるのもすごい。キャラそれぞれのアクがストーリーをてんでに色づけて、賑やかなようでそれだけではない身内的な情を見せてくる。正体は全員が判ってないのも巧い展開。
笑いを取りに来るシーンはまた少女漫画としては振り切っている。コックリさんのハートの綴りのフェイントは堂々だし、ボトル(ウィスキーなどではない)で、芋(焼酎ではない)で、生(ビールではない)で、というスナックのシーンでかわした絵に笑う。
楽しく読んでいつの間にか最終巻5巻に来ていた。続巻出せるようにしたと赤瓦先生は書き綴っていらっしゃるので、気長に待つことにする。
「兄友」未読なのだが、雰囲気いかにも少女漫画と見ている。これは俄然比較対照先として興味が湧いた。
本作は笑いばかりが先行、主人公はドタバタの真ん中にいつも居て、恋愛のほうは少しも進んだとは言えない。反発から理解へ変わっていったくらい。
憎めないキャラ達がそのうち決着を付けていくのをやはり見届けたい気持ちなのだ。 -
口に出さなくても伝わるものを受け取る力




 2024年7月19日文庫版の千津美と藤臣君のシリーズの2巻目。話としてはシリーズ1巻目にあった6話の続きの3話分(7~9)が収録され、シリーズ以外の収録は無し。ララ誌の人気シリーズとして続いた作品の後半部分のこちらは、各話の頁数が多い。最多頁数の「銀色絵本」がタイトルに。
2024年7月19日文庫版の千津美と藤臣君のシリーズの2巻目。話としてはシリーズ1巻目にあった6話の続きの3話分(7~9)が収録され、シリーズ以外の収録は無し。ララ誌の人気シリーズとして続いた作品の後半部分のこちらは、各話の頁数が多い。最多頁数の「銀色絵本」がタイトルに。
丁寧な作品作りがとても伝わる。
これまでのお馴染みの登場人物も居れば、新たな敵役?も加わり、今や異なる大学に通う二人の人間関係の広がりや、藤臣君の過去のことも触れられて、千津美と藤臣君の揺るぎなさが更に深まるという感じ。一匹狼的存在だった藤臣君のいいところに気づいていたとの自負を持つ自信家の存在が、この9話目の主な揺さぶりどころ。
1~6話内もそうだったが、不良が町のチンピラまがいと化して、出会い頭的に悪さをしており、間接的には奴らは誰かに繋がるというもの。チンピラが絡んでくるというのは今ではまず聞かないが、過去の経験を語ってくれた後輩も昔居て、当時は今より体感治安は良くなかった部分は確かにある。男性同士の暴力による解決?、も、漫画だけの話ではなかった。全く歓迎するような事ではないが、絵空事ばかりということではないイメージ。
このカップルの好ましかった点は、いちいち説明をしなくても通じる二人の感じの良さだろう。
とかく言葉にすがるというか、言葉を求めすぎる恋愛物が多い。それはそれで、口にしなくても判るだろ、的なものを乗り越えて、敢えて口にすることも感動のドラマがあることは承知している。しかし、口のうまさで口説かれても薄っぺらさを覚えるのも一面、また事実なのである。藤臣君の言葉数の少なさと、表情の乏しさを逆に魅力とし、反面無理解な周囲が無闇に怖がる、というキャラ設定はストーリー中過去の対立相手の再会で役立ったが、私は、藤臣君が秘めている優しさを千津美が理解するほどにまで、二人の心の結びつきを深めた描写が良かったと感じた。もうひとエピソード欲しかったくらい。ただし、終始自己卑下が強い主人公、当時は少女漫画ではお馴染みな性格ではあっても、シリーズ物の中で何回もやられると、しかも過剰演出とも取れるシーンを何度も見せつけられると、私は飽食気味。
全288頁。
パステル気分(1982年ララ8~10月号)80頁。
銀杏並木から(1981年ララ10月号大増刊)16頁。
銀色絵本(1984年12月号、1985年1~5月号)177頁。 -
「エイプリル・マジック」に再会して嬉しい




 2024年7月18日同時収録「エイプリル・マジック」のみ千津美と藤臣君のシリーズ外。まさかこんな風に再読出来るとは思いもよらず、喜んでいる。本誌ララ1980年4月号で読んだときの掘り出し物感は当時とても強かった。育生の待つ出会いのことを知る女史の語り部風の配置が絶妙。このおつかいに出す感じから、もう既にあの作品に再び巡り会えていることを、軽い興奮を持って迎えていた。そして、間違いないと育生が確証を積み上げる緊張感が堪らない。今読んでも際立つうまさ面白さをたたえていると思う。
2024年7月18日同時収録「エイプリル・マジック」のみ千津美と藤臣君のシリーズ外。まさかこんな風に再読出来るとは思いもよらず、喜んでいる。本誌ララ1980年4月号で読んだときの掘り出し物感は当時とても強かった。育生の待つ出会いのことを知る女史の語り部風の配置が絶妙。このおつかいに出す感じから、もう既にあの作品に再び巡り会えていることを、軽い興奮を持って迎えていた。そして、間違いないと育生が確証を積み上げる緊張感が堪らない。今読んでも際立つうまさ面白さをたたえていると思う。
尚、千津美と藤臣君のシリーズは、次の2(銀色絵本)もある。それ程の人気シリーズを、デビュー作(秋風ゆれて)で打って出ているひかわきょうこ先生の実力には舌を巻くしかない。しかも掲載誌は実力者揃いのララ!
秋風ゆれて(1979年2月大増刊)
春のひとかけら(同年5月号)
トライアングル・トラブル(同年10月号)
春を待つこころ(1980年2月号)
パラソル・エッセイ(同年6月号)
スイートカラーの風の中(1981年6・7月号)
主人公千津美はドジな子設定だが、その描写があまりにも演出し過ぎていて私には共感部分は多くない。掲載当時の少女漫画の路線ではあるものの、元々迂闊な印象や軽率な振る舞いを思わせるそういうキャラの主人公は、私は余り歓迎できない。
しかも何となくそれがまかり通って、よくもまあ他の親友達と同じ進路に行けたり、バイトもやれているなと、現実感薄い。
しかし、「スイートカラーの風の中」辺りでも見せる、ストーリーの複線化がごちゃつかないで読み手のこちらを引っ張り込めるような、各キャラを立たせている構成さすが。
出世作のこのシリーズなかりせば、後続の他の魅力的な作品群も自由に豊かに描ききれなかったかも、と思うと、こうした典型少女漫画で先生が足元固めを果たされていたことを、今さらながら大した新人さんだったんだろうと驚嘆する。
ひかわきょうこ先生はこのあと、異世界物、西部劇、時代物、オカルト物と、あらゆる領域に手を伸ばされてどれも魅力の作品群を成し、ご活躍ぶりはとどまるところを知らない。ストーリー進行もうまいし、語りも巧み、絵の構図の工夫もときどき目先が変わっていいし、男の子をどう描けば女子受けするかもよくわかってらっしゃる。
絵柄云々は私には問題ない。その時代時代には合っていたものなら構わないし、また、流行の絵柄ではなく我が道というのでも構わない。全286頁 -
埴輪戦隊スペースファイブが活躍する学園物




 2024年7月18日全5巻。MELO DY誌2017年2月号~2022年2月号連載。2巻で区切りがつくせいか5巻完結と認識されていない読者も居たようだ。
2024年7月18日全5巻。MELO DY誌2017年2月号~2022年2月号連載。2巻で区切りがつくせいか5巻完結と認識されていない読者も居たようだ。
諸説ある古代文字を、宇宙と結びつけ、縄文ニッポンから現代日本に連なる人のつながりを思わせる。不思議な現象に果敢に立ち向かって学園の危機や化け物や恨み生き霊の類を退治する、一種のヒーロー物。そこにうっすら恋愛事情も乗せてくる。
「とにかく明るいオカルト研究部」が五人のベースみたいなものとなり、その存在が話をユニークに展開させる。「視える」という体質は私には無縁だが、このテの話は苦手なほう。それなのに、「とにかく明るい」ので、おどろおどろしくもなく、気色悪い怪物も現れず、ちょっと変な化け物がおどかしてくるだけ。頼もしい五人の戦士達が、格闘技一切無しに、埴輪ーズ達の知恵を得て、得意技で応戦。
実は、あっさりした感じがしてしまうのだが、ダークな感じを逆に抑えたことで気軽で愉しく読める読み物となった。
絵の角度、コマの切り取り方、文字の解釈、いろいろ面白い。但し、柱での補足説明もあり、少々の理屈っぽさは滲み出てしまった。
しかし各戦士の戦いぶりはサマになっていたし、一人一人考えを巡らしながらチームワークもピシッと見せて、部活としてのありようや教師間の人間関係、チラと主人公一ノ宮琴美や阿雲雅巳の親子出演も見せるなど、複層的構造で散漫にならず、さすが。
4.4位で4星にしようかと当初考えたものの、引きつけるイントロやユニークな展開力はやはりひかわ先生のお力を強く感じ、4.5~4.6辺りの5星としたい。
ちょ~っとバックが、白っぽい印象多かったかも。 -
為政者の野心、民草、信仰、理不尽な犠牲




 2024年7月15日存亡や消滅、野心や略奪、殺戮。横暴に振り回され領土拡張欲に泣く境界線上の民。世界史の中で正当化された事柄も、前線では難民が行き先を求めてさすらう。時空を前後して話が飛び回る壮大なSFファンタジー。「王女の首飾り」に参った!清らか!。
2024年7月15日存亡や消滅、野心や略奪、殺戮。横暴に振り回され領土拡張欲に泣く境界線上の民。世界史の中で正当化された事柄も、前線では難民が行き先を求めてさすらう。時空を前後して話が飛び回る壮大なSFファンタジー。「王女の首飾り」に参った!清らか!。
行きたかったけれど行けないので、漫画で想像を膨らませて読めるのがいい。中央アジア大好きな人必見。因習(結婚などの)も興味深い。
見開き2頁ひとコマ多く横読みすべし。全6巻、1巻当たり平均437頁(空頁含む)。あすかコミックスDX版ベースなので、白泉社版と編まれ方構成微妙に異なるようだ。
以下括弧内は破などゆめコミックス初出西暦年。はるかなるシルクロード(81)シルクロード(81)天翔ける馬(81)シルクロード.キャラバンの鈴(81)天のはごろも(84)風とビードロ(82)風の子守唄(ララバイ)(82)風のメモリアル(82)イシククル天の幻影(シリーズ外)(82)/ゾマのまつり(4作)(85)-ゾマ神の嗤う夜,ロンドンの花吹雪,ゾマの祭り,イエチャブ.ツォの月、星の巡礼(?)星の刻印(?)バンボレットの谷(83)バルマンの鉄柱(83)宇宙ゆく帆船(83)砂漠幻想(86)/姫君の塔(84)ペキネンシス50万年(83)青いビビ.ハヌィム(84)カラ.キタイの娘(84)金の髪 金の繭(86)タシクルガン伝説(86)白い神々の伝説(86)テイサの記憶(88)黒水城(カラホト)の魔女(86)波斯の井戸-カレーズ-(90 )青い柘榴(87)綿の城パムッカーレ(88)/巻き毛のカムシン(86)カシュガル緑の王宮(86)ヘディンの手帳(87)ソグディアナの娘(87)ヤグノブの谷(87)ウイグルの砂(87)雪の朝-ホワイトカングリー(88)サーハスの鏡(88)王女の首飾り(88)百合の咲く谷(88)白鳥伝説(?)湖面の月(89)/聖者の湖イシククル(86)赤い山 白い神(89)天より降りて(?)金と銀の盃(?)欠けたもの満ちるもの(89)マルゥの空ツヴィは砂色(89)金目のツヴィ(89)天と地の神(90)永遠を見る娘(90)そしてカレーズ(90)カレーズ-星の井戸(?)カレーズ-ペルシャ(?)カレーズ-夢(?)カレーズ-幻映(?)/緑色の彼方へ(84?)星の落ちる谷(90)月の宴1,2(90)エンディング(90),駱駝のイブン.サウド、アッサラーム.アレイコム、風の伝説、風の輪・時の和・砂の環 -
この視点はありそうでなかった感じ




 2024年7月12日スピンオフの類は大抵本編の登場人物中の誰かが据えられてのストーリー展開となる。この作品はそこを外していてユニークで、可笑しくて、可愛らしくて、(BL)読者サービス満点。
2024年7月12日スピンオフの類は大抵本編の登場人物中の誰かが据えられてのストーリー展開となる。この作品はそこを外していてユニークで、可笑しくて、可愛らしくて、(BL)読者サービス満点。
その遊び心というか、他愛のない軽さと距離感、書店員キャラのイヤラシさのない偶然と刺激される好奇心が、本作品の面白さの身上。
実は結構前に読んだのだが、本編に新刊が出て悩んでいる折なので読み返しに来た。
初読み時点ではあっさり読了していた。本編読み返ししておらぬ内に優先的にこの書店員ver.を下調べの為に再読したのだ。そしたら、構図を新鮮に楽しませる描き方に感じ入ってしまった。
これは藤河先生にやられました! -
冒険と成長、敵対から和睦へ、守る決意へ




 2024年7月7日本編が良かったので、スピンオフは試読後即購入。面白かった。
2024年7月7日本編が良かったので、スピンオフは試読後即購入。面白かった。
王子が学んでいくさまは良く作られていたと思う。同行したラヴィとスバルとの道中のいろいろも楽しかった。生まれながらに悪者はおらず、そこには事情があることを丁寧に描いている。それでも善意の人も悪意の人もいる。獣にしても。
そんな寓意は前面に出してこない。
ハラハラわくわくの旅も、王子には切実な動機もあった。幼かった彼が一歩一歩自らの足で確かめながら前を向き続けて、一日一日が養分となって逞しい姿になったこと、親目線では安堵と喜びだろう。
サリフィのキャラ設定が、この獅子の子落とし?可愛い子には旅をさせよ、を可能としたのも、この話ではポイントだろう。
魔族の立ち位置が少々説明不足にも感じた。 -
高3生6人の冒険アクション+オカルト大傑作




 2024年7月7日移動用乗物は電車含めいろいろ出てくるが、カーチェイスや剣菱家の車のデコ、ヘリコプターが空をブンブン、剣菱家のヘリのデコ、見ていて楽しませてくれる工夫満載なのが判る。お金持ち設定なので、狭いところでチマチマやってない。世界に飛び出す。スキーリゾートも南国リゾートも舞台に。雪のシーンはリゾート地舞台であるとないとにかかわらず素敵だ。香港マフィアもKGBも噛んでくる。お金持ちのお嬢ちゃん坊ちゃん学校の中でもとびきり羨望を集めるセレブな6人、ストーリーでは何度も誘拐されたり人質になったり。でも自分達の知恵と体力で窮地脱出。財閥令嬢だから身代金目当てに巻き込まれるのではなく事後発覚ばかり。本当に楽しく読んだ。
2024年7月7日移動用乗物は電車含めいろいろ出てくるが、カーチェイスや剣菱家の車のデコ、ヘリコプターが空をブンブン、剣菱家のヘリのデコ、見ていて楽しませてくれる工夫満載なのが判る。お金持ち設定なので、狭いところでチマチマやってない。世界に飛び出す。スキーリゾートも南国リゾートも舞台に。雪のシーンはリゾート地舞台であるとないとにかかわらず素敵だ。香港マフィアもKGBも噛んでくる。お金持ちのお嬢ちゃん坊ちゃん学校の中でもとびきり羨望を集めるセレブな6人、ストーリーでは何度も誘拐されたり人質になったり。でも自分達の知恵と体力で窮地脱出。財閥令嬢だから身代金目当てに巻き込まれるのではなく事後発覚ばかり。本当に楽しく読んだ。
元々がカラー頁が多いと踏んで、カラー版を選んで大正解(私は本来全部彩色ではなく白黒仕上げの漫画の表現に魅力を感じている人間)。ベタッとした塗りではなく、淡さの備わった加減の調整された彩色が上品。
各話で組み立てられ一件毎解決しているからどこで一旦止めても続きを読みに戻りやすい。纏まりが有り、読ませどころの絵の力はすごく、それでいて細部まで行き届いた配慮を感じる背景と共に、悪い人物像の圧がパンチを持ってる。陰謀や背景となった事情が組み合わさり、ストーリーも頁数に収まってるのが不思議なほど読み応えあり。
病院から不在者投票したが折しも本日都知事選挙の日。都知事選の回の話もぶっ飛んでいて可笑しかった。
曜変天目茶碗、私も静嘉堂文庫で実物を見ている為、清四郎や贋作師の気分が判るしオチにもクスリ。
第11巻は後半が一条ゆかり先生作品を読んできている人のための企画。愉快なトリビュート付き。作品のみ読みたい人は余分に感じるか判らないが、先生ご自身の作品中のお言葉通り、無駄に見えて無駄にはなってない。各話最後に付いてるmakingや、10巻のあとがき、さらにその11巻の企画は一条ゆかり先生人となりも認識する参考となる上、舞台裏をサラリと触れているので深く作品を理解出来る楽しさがあった。
第1巻が1981年。私は悠里と違ってオカルト体質はないが、1979年夏、旅で知り合いになった男の子が「一条ゆかり知ってる?」、「『デザイナー』の?」、「有閑倶楽部って面白いのがあるから絶対読んでみてね」、と確かに私たちに言ったのだ。だから私は作品名をその時に覚えていた。リアルタイムには読まなかったが、いつか読む気で記憶したのだ。 -
2人の間に男女の関係のない4畳半生活をSFで




 2024年7月2日外付けの装置でデータの蓄積、分析をさせて活用するコンピュータのネットワーク化など、まるでこんにちのAI時代を予感させるけれど、至って昭和なお話。主人公慎平の、突如転がり込んできた早紀への抑制が実に誠実で崇高だ。
2024年7月2日外付けの装置でデータの蓄積、分析をさせて活用するコンピュータのネットワーク化など、まるでこんにちのAI時代を予感させるけれど、至って昭和なお話。主人公慎平の、突如転がり込んできた早紀への抑制が実に誠実で崇高だ。
柴田昌弘先生の作品は1.2巻は持っているはず、ラン?ソネット?主人公は女の子だった。
このフェザータッチ・オペレーションは陰謀巻き込まれもあり、時折女の子の無邪気な首のつっこみ方がうっとうしい時はある。そういうところを、特殊な背景の16歳の彼女の世間知らず、常識外れの育ち方したから、で説明しておいて、彼は最初から最後まで渾身で彼女を守り抜いてるのが、彼の一貫した美学のようである意味感心する。普通の男の子っぽさを見せつつ、なかなか出来ないことをやってのける頑張りが素晴らしい。
レビューを読んで、そんなに気に入った人が居るのならどれどれ確かめたい、と、柴田先生作品の面白さをかつて少し知っていた者として、関心そのままにやって来た。
柴田昌弘先生タッチの絵がかなり懐かしかったし、やはりいろいろ巧さが。特に町の景色だとか、山の中の研究所の雪景色だとか、楽しかった。
個別に閉じている話が幾つかあり、黒幕組織の暗躍が全体を貫く。
一応悪人達は悪人らしく動くものの、敵方のボスについてはクッキリ人物像を決めてないのか…。
なかなかオチが良かった。
それにしても、昔は、柴田先生ほか、弓月光先生、和田慎二先生、あだち充先生がいらして賑やかだったなぁ。その前には、もちろん大御所の先生方、手塚治虫先生、赤塚不二夫先生、ちばてつや先生…たくさん描き手が掲載誌を彩った時代もあったそうだし、そんな多種多様な作品群で少女漫画を読みたいものだと思ってしまう。 -
その後の二人を見たい人の続編だが…




 2024年6月30日三歩進んで二歩下がる、みたいな感じもしないでもない。(因みに私はBLらしいイチャイチャを読みたい意味では書いてない。)
2024年6月30日三歩進んで二歩下がる、みたいな感じもしないでもない。(因みに私はBLらしいイチャイチャを読みたい意味では書いてない。)
進路見つけたのは大切、それでもその飛び込み方に、太一らしさはありつつもかなりの強引さを感じる。
マヤの配置がお話の都合に見えてしまってそこも絡みが強すぎた印象。彼女の「オオカミ女」っぷりと、その後のいろいろが少々物語世界を狭くしたように思う。
航平の、忘れてた怒ること笑うこと/思い出した、は、前作と重複感はあるものの本作で強調されても、くどさは無かった。
ひだまりにしても木洩れ日にしても、木々と光の絵が清々しさと眩しすぎない惹きつけられる明るさがあって、作品の雰囲気が格段に上がる。黒白世界が、緑が見えるようで素晴らしい。
階段の水溜まりのシーンも良かった。
航平の引け目を太一が振り払う最後の行動は既に二人の関係に脆さが減った証拠に思えるのに、ここに至るまで丸1巻かかってることに、読み終わってみれば何となくの遅滞を思わされる。それにその行動に解決をお任せ過ぎる印象も。
犀おじさんとのやりとり(108/312)が深いので、動かされた。「どちらかが満足すれば/どちらかの不満を生む。」の話は前作に連なる一本の道の、本作の強い部分として印象づけた。 -
-
-
「犬上家の一族」は「人騒がせ一族」!




 2024年6月28日推理小説横溝正史作品を思わずにはいられない人物名の数々が出てきて、ほか設定や進行もいろいろとパロっているところが可笑しい!。
2024年6月28日推理小説横溝正史作品を思わずにはいられない人物名の数々が出てきて、ほか設定や進行もいろいろとパロっているところが可笑しい!。
主人公である探偵見習いの名前は金田耕子。本人(と犬上君もかな)だけは大真面目だけれどどこかずっこけてる謎解き物。
中には、雰囲気は怪しくて少し恐ろしげな様にしながら、カラッと「難事件」(!)は犯人解明に終わる幾つかのまとまったお話が数セット。そして、春秋館という環境、住人達は変キャラ。いや、いろいろな人が変キャラ。不思議と成り立ってる自由さ。
これで恋愛色も入れてきてる。
絵は昭和初期を感じさせるように見せているが、書面の発行日に昭和三十?の文字が!それは合わないかと思った。三年なら納得。
由良先生の終盤かき回しは唐突感もあった。どっちサイドかね、と。
八墓君も途中判らない…でも犬上君のほうも揺らいだし、マツ子も人物像が!?、そもそも耕子はピンチヒッターではなかったか? などなど疑問も湧きながらも、読み物としては面白く読み進められた。
古畑任三郎パロもあるし、お馴染み金田一探偵の口調を思わせるもったいつけも笑わせる。
楽しく読んだ。
「神様はじめました」番外編を読みに特装版を買わなかったら、本作を知ることはなかった。
抱き合わせ販売は、この場合私には大成功だった。 -
冒険や陰謀も少しあって楽しめる平安貴族物




 2024年6月27日明るくて前向きで、型破りの自分を気持ちよく自己肯定している主人公が、自分の男女観を少しずつ成長させながら恋愛成就する話。飽きさせない見事な展開で、貴族社会のしきたりやヒエラルキーを反映させて平安時代という現代とかけ離れた世界が生き生き描かれている。彼らの言葉が、当時の独特の用語と、現代語表現のミックスで、しかも読み手フレンドリーな用語解説が直ぐ傍にあるなど親切な作り。
2024年6月27日明るくて前向きで、型破りの自分を気持ちよく自己肯定している主人公が、自分の男女観を少しずつ成長させながら恋愛成就する話。飽きさせない見事な展開で、貴族社会のしきたりやヒエラルキーを反映させて平安時代という現代とかけ離れた世界が生き生き描かれている。彼らの言葉が、当時の独特の用語と、現代語表現のミックスで、しかも読み手フレンドリーな用語解説が直ぐ傍にあるなど親切な作り。
平安時代の華麗なる服装は男女共眺めて楽しいが、人物達が静かに居る場合の配置されてる構図そのものは、何処かの絵巻物などでの既視感が強く、十二単の見本が実際本当に少ないのだなぁと思ったし、山内先生が漫画化に当たりご苦労されんだろうな、とも思った。建物の中も外も感じがよく分かった。
吉野君(よしののきみ)、鷹男、守弥などの登場締め括りは、ちょっと尻つぼみ感があった。
冒頭、瑠璃姫がいくらお子さま設定とはいえ、思慮に欠ける振る舞いが悪目立ちし、二人の前途多難を出したかったかもしれないが、わざとらしさを感じなかったわけではない。また、融のキャラも、ストーリーの狂言回し役に使ったにしても、内大臣家大丈夫なのか?、と思わないでもない。
また、破天荒で行動派で向こう見ずな姫であっても、それは無理では?というシーンも。読者をハラハラさせるために、または、彼女のキャラにヒロイックな味付けをするためのことであっても、微妙に現実味を落とした。
歌のやり取りが素晴らしかった。
添えられた解説がまたいい感じ。
そして、彼らを縛る決まりごとなども読んでいて話の縛り事として効いていて、興味が増した。
1981年から1991年発表のジュニア小説が好評だったことから、ほぼ同時期にコミカライズされたらしいが、時代物という性格も手伝って古くささはあまりない。唯一、高彬が殴るシーンだけ、アッとはなった。
こちらは文庫版から電書化。全6巻。
人妻編、どうしようか思案中。 いいね
0件
いいね
0件 -
アガサクリスティ3作品集ギュッと煮詰めた?




 2024年6月25日表題作64頁、追憶のローズマリー67頁、ソルトクリークの秘密の夏72頁。ファッション解説4頁。
2024年6月25日表題作64頁、追憶のローズマリー67頁、ソルトクリークの秘密の夏72頁。ファッション解説4頁。
シーモア(島)で薦められているのをみて。
抜き方が巧いというのか、纏め方が巧いというのか。恐らく原作から驚異的な文字数にサイズダウンしているであろうのに(原作未読です)、変な駆け足は無かった。但し人物が大勢出てくる所は、関係者同士の関係整理しながら読み進める必要はある。
絵におとぼけがあって英国を感じる空気がある。スコットランドヤードも、登場すると、そうなのかと感じさせ、館やその外の感じもいかにも作品設定上の舞台を思わせる。
いろいろ(死体処理、疑わしき関係者達の離合集散の偶然性等々)と突っ込みたくなることがあるのに、いやいやこれで一区切り、と各話読後に蒸し返す野暮は、したくなくなる。
動機の裏のドラマや、一見そう見えなかった人の真実など、榛野先生のさり気ない描写で、こうしたジャンル特有の終盤の種明かしが読み手の私を気持ちよく裏切ってくれて、これで3作品も詰め込んだというのが信じられない!
(シーモア(島)で島民の方のお勧めにより読むに至り、要はコレは自力で見つけられないタイプの書籍。教えてくださって感謝です!) -
作法も武芸もやるよう躾けられた森育ちの娘




 2024年6月25日上下2巻構成だが番外編や蛇足的終盤を除くと実質1巻強のストーリー。主人公シャーロットの特殊な育ち方育てられ方、純粋にして逞しく、美しさに無自覚であり他人の懐に素直に入れる素直さや柔軟性がある、同僚達が誰一人敵にならない真面目で働き者で人のために働ける素敵な人柄。複雑な生育環境になりがち乍ら深い愛情でもって慈しまれて育ったことが、上巻半分以上から読み取らせる。如何せん森の奥育ちの為に人ズレしておらず、そこが危なっかしくて彼女の周囲の女性達の庇護欲を誘う。
2024年6月25日上下2巻構成だが番外編や蛇足的終盤を除くと実質1巻強のストーリー。主人公シャーロットの特殊な育ち方育てられ方、純粋にして逞しく、美しさに無自覚であり他人の懐に素直に入れる素直さや柔軟性がある、同僚達が誰一人敵にならない真面目で働き者で人のために働ける素敵な人柄。複雑な生育環境になりがち乍ら深い愛情でもって慈しまれて育ったことが、上巻半分以上から読み取らせる。如何せん森の奥育ちの為に人ズレしておらず、そこが危なっかしくて彼女の周囲の女性達の庇護欲を誘う。
ナイト登場も、主人公が恋愛の方の主人公までもなるのはゆっくり。鍛錬を怠らず、の、その積み重ねが結果をもたらす。作者があとがきで云うところの正に「努力」の結果である。森での生活でも両親はどんな場に出ても生きていけるように、という養育方針だったとみえる。だからガサツでなく、といって身の回りの自然というものをしっかり教え込んだ。そんな人物設定が、作り手の根幹にあるからこそ、ストーリーが滑らかに徐々に、彼女を取り巻く環境が彼女を一つ一つ押し上げていくことに違和感がない。よくある、ごく普通の子が突然引き立てられる、などといった出世物ではなくて、内なる輝くものは誰もが気づいてしまう状態。また、血は争えない、という出生の秘密もストーリーを盛り上げる。
特殊環境にあっても十分に通い合った親子の情のあり方や、一方で、主人公の周囲シオンやレオ、またスザンヌの家族関係など、家庭其れ其れの固有の事情も描いて、キャラ達を膨らませていく。
読んでいて、波風欲しいわけではないけれども順調な展開が多くて、どうせあれこれ番外編で付け足していったのなら、最初山場かと思ったクレールのところ、功労賞の彼女にも、もう少し報いる場面欲しかったようには思う。
「素敵な男性に愛されて結婚しておわりではなく」、との作者の考え方、読み始める前は知らなかったことだが、私も昔からその考え方なので大いに本作に貫かれた思想を読んで味わえた。
シーモア(島)で面白いと教わって読みにきた。
そう思う。
とても清潔な話で好感が持てる。
番外編でこそ本編で描けなかった隅々まで書かれている、という考え方もあろうかと思う。最近あちこちで番外編なる脇役メインのサイドストーリーが多く感じてる私は、今回数編は無くてもいいかな、と思ってしまった。 いいね
0件
いいね
0件 -
音楽と恋愛、何処までも何処までも進めると




 2024年6月21日TLらしいシーンは却ってグダグダ感と一発逆転感とが、話の進行方向をすぐ決めてしまい、本作の本質的な展開に絶対不可欠だとは思えなかった。ベッドシーンは必要であることと、TLッぽさとは別物と思っている。発表誌面の性格ということもあるだろうが。作品が主人公チナの夢を大切にするほど、和泉との関係性に影響与えるのは避けられない中で、二人の恋愛の深化は当然読みたいが、要は描き方のこと。TLがとかくに絵が雑気味なケースを見かけるだけに、本作の丁寧さ(服、楽器、解説、乗物等)、寧ろ鬱陶しい程に隙間無く埋め尽くされた細かい描き込みは驚嘆レベル。それを面倒に思う人も居るには違いない。私はこの作品に注がれた集中力をすごいと思った。
2024年6月21日TLらしいシーンは却ってグダグダ感と一発逆転感とが、話の進行方向をすぐ決めてしまい、本作の本質的な展開に絶対不可欠だとは思えなかった。ベッドシーンは必要であることと、TLッぽさとは別物と思っている。発表誌面の性格ということもあるだろうが。作品が主人公チナの夢を大切にするほど、和泉との関係性に影響与えるのは避けられない中で、二人の恋愛の深化は当然読みたいが、要は描き方のこと。TLがとかくに絵が雑気味なケースを見かけるだけに、本作の丁寧さ(服、楽器、解説、乗物等)、寧ろ鬱陶しい程に隙間無く埋め尽くされた細かい描き込みは驚嘆レベル。それを面倒に思う人も居るには違いない。私はこの作品に注がれた集中力をすごいと思った。
しかし、17巻までは6年半位前に読み放題で読んであった。それから全20巻完結を迎えるまでの続巻のスピードダウンが、読み手としての勢いを殺いで、否応でも作品の雰囲気に乗り切れぬ浦島太郎時間を設けさせられてしまった。
和泉のキャラも多少好ましい変化を感じたが、ビジュアルは中盤が良かったように思う。
この話は、安易に彼のいろいろに頼らないチナの気概、此処が素敵な所なのだと思う。そこがまたドツボで雁字搦めで突っ張って、と、人によってはかわいげが無いとでも見られるかもしれない。そこがでも私には、本作の音楽面での主人公の夢のありようとしてとても気に入った。
往々にして、彼が大金持ちだとか、社会的地位が高いとか、それを恰もシンデレラストーリーの如く、大勢の平凡な人生から抜け出す足掛かりとする、そんな相手を「利用」して話を組み立てられる事がある。玉の輿的思考の話は私には抵抗感が大きい。それを完全否定まではしないが、こうした自力でなんとかもがく姿は、本当にかっこいい。
音楽も食も、服も、この世界、というのがあったのも良い。蘊蓄も面白くて細かいところも一つ一つ読みに行って楽しめた。
私はこのヲトヨシ先生の絵柄は、好みではない。それでも、作品の魅力を大いに高めているのは、この絵柄だと感じる。 -
戦国の世に戦って生きた花、「六花」の半生




 2024年6月16日戦の場では、善人も悪人もどちらにもなり得るし、其れ其れ理屈がある。平穏を脅かす者が居て、奪い奪われが発生してしまう。死者には家族がいる。
2024年6月16日戦の場では、善人も悪人もどちらにもなり得るし、其れ其れ理屈がある。平穏を脅かす者が居て、奪い奪われが発生してしまう。死者には家族がいる。
歴史書も、書かせた人の意向が、書いた人の書物に反映される。勝者の大義名分が正当化される。逸話の誇張や史観の一方的歪み、伝聞の誤解。そんなこともよくあるから、罪人とされた人物が名君だったというエピソードが掘り起こされても驚かなかったりする。
主人公は守るために立ち上がった。まず、自分を、そして仲間を、いずれは領民を守ろうと。
少女漫画では争いを好まぬどころか、手を汚さぬ場合が多いが、本作は泣きながら不本意ながら手を染めざるを得ない状況に。
戦国時代は農民も戦に駆り立てられ、武士に使われた(足軽として)。僧兵も居た。その戦乱期の中で、外の世界を知り、自分で力をつけ、いつか多くの人の命も預かる身に。そのスケールは、どちらかというとチマチマ日常系の多い少女漫画にあっては珍しい大きさがあって小気味よかった。絵も良かった。
史実とフィクションを織り交ぜる作品は大変な突合作業あったと思われるのに、かなり自由な展開も多くて、その自由さこそが本作に面白さを足したかもしれない。数々の有名な戦いの年譜も意識しながらの、全くの創作のはめ込みに独自展開。実在した歴史上の人物達を、後世の人々の思う人物像ではない人間とすることも、各キャラに幅を与え、フィクション故の空想力を見せつけてくれた。
実は星は当初4と迷ったのだが、力作であるし、秀吉、信長、光秀の描写に「新しさ」もあり、5に。
実在したとされる忍者集団「乱波(らっぱ)」を主軸にした意欲もすごいことだなと。途中「透波(すっぱ)」(100/194)にも触れるがスマホでは「素波」との漢字表記しか出て来なかった(検索の限界か)。
全8巻(本編各巻平均186頁、各巻1頁作者ご挨拶頁とカラーイラスト数頁)、プリンセスGOLD誌2010年2月号~2013年3月号掲載。単行本化が早く2010年6月発売からで、その後コンスタントに巻を重ね、8巻完結を見越した作者あとがきを6巻辺りで読むにつけ、無理矢理な手仕舞いをさせられてない終わらせ方になっているようで喜ばしい。 -
時代劇。貧困、権力争い、お家騒動などなど




 2024年6月15日時代物をやってみようという意欲自体が素晴らしい。それらしき時代背景や、それらしき雰囲気、日本であり現代ではない、というところを描いた上で、人物がしっかりと居なければならず、取材(用語や世相など)や構想には絵を描く以前の要素は必要前提条件として、要求される力量は恐らく現代物の何倍かと。
2024年6月15日時代物をやってみようという意欲自体が素晴らしい。それらしき時代背景や、それらしき雰囲気、日本であり現代ではない、というところを描いた上で、人物がしっかりと居なければならず、取材(用語や世相など)や構想には絵を描く以前の要素は必要前提条件として、要求される力量は恐らく現代物の何倍かと。
「花始華」(はなはじめてはなさく)100頁、「狐隠れの君」100頁。プリンセスGOLD誌2007年2月号と2009年2月号、各々に掲載。また、「制作実話」として3頁の楽屋話。カラーイラストなども。
貧しい田舎育ちの女の子が主人公の話と、お姫様であるが活発な女の子が主人公の話と。先を読ませない展開でどちらも女の子が先頭切って頑張ってるが、頼れる男性に出会えたことが全てのカギだったともいえる。
その男性達、だから少女漫画に必要なものをもっているので読みやすい。
女の子の冒険心をくすぐるようなところもあり、ヒヤヒヤも多少アリで、楽しませるサービス精神を感じる。 -
走る。止まる。一番大事なものを見失わない




 2024年6月14日表題作134頁(1989年発表)、同時収録「サンド・ストーム」57頁。無茶と純粋と刹那と夢への憧れ。
2024年6月14日表題作134頁(1989年発表)、同時収録「サンド・ストーム」57頁。無茶と純粋と刹那と夢への憧れ。
一緒に先を見ること、相手を想うこと。自分の幸せと相手の幸せとの分離と、共に歩めない哀しみ。願いを形にすることがもたらすもの。楽しいだけでは生きていけない。形にすることで喪う恐れ。
今考えていることを今ちょうどリアルタイムに相手から伝えられるわけではなく、男の本心は女からは見えにくい。小さなさざ波も、二人を揺るがすほどのものではなかったにしても、物語は結末に向かって歩調を緩めない。そこに無常みたいなものを感じる。
絵は、コマの取り方も形も、白黒の感じも、なにかととてもいい。 -
心の一里塚越え、みたいな?




 2024年6月14日表題作140頁(1990年発表)、同時収録「レインダンスが聴こえる」45頁。主人公達をもやっとした状況に置いている環境の中で、彼等なりにもがく。なにか打破したいのは伝わってくるし、その悩める姿の描写に思春期的な堂々巡りも感じ取れる。同じように何回か見えない心の壁にぶつかりながらやってみたことが、綺麗な突破ではないにしても、ひとつ新たな展開を呼びこんだ形となる話。
2024年6月14日表題作140頁(1990年発表)、同時収録「レインダンスが聴こえる」45頁。主人公達をもやっとした状況に置いている環境の中で、彼等なりにもがく。なにか打破したいのは伝わってくるし、その悩める姿の描写に思春期的な堂々巡りも感じ取れる。同じように何回か見えない心の壁にぶつかりながらやってみたことが、綺麗な突破ではないにしても、ひとつ新たな展開を呼びこんだ形となる話。
表現に才能をキラキラ感じさせる。絵も、言葉の畳みかけも。
ハーレクインコミックで渡辺直美先生を初めて知った。あちらはかつて少女漫画界にいらした先生が多いため、こちらを読んでみることに。ハーレクインコミック界は技量いろいろな先生が手掛けておられるが、渡辺直美先生は確かなものを感じさせる。
この少女漫画のころ腕をふるい、着実に表現を広げられていたことがよく判る。 いいね
0件
いいね
0件 -
現実を直視せねばいけないだろう




 2024年6月13日一方的な力は、とてつもない反作用を蓄えるのではないだろうか。
2024年6月13日一方的な力は、とてつもない反作用を蓄えるのではないだろうか。
何が正しくて何が間違っているか、それは政治思想や宗教に関する限り、決めつけは不可能だ。
しかし、人をこのように扱っては天国には行けないだろう。日々安眠できているとすれば、している側は罪の意識というものが無い?何が楽しくてそんなことをおこなえるのか、胸に手を当てて恥ずかしい非人道的振る舞い。なかったことにされても、なかったことには現実ならないのだ。自分がそんなことをされたら、という考え方が出来ないものだろうか。人間はいつまでこんなことをする人間をなくせないのだろうか。 -
まんがで簡単にわかる!日本人だけが気づかない危機 日本消滅~単話版
ひとつの視座、ひとつの警告そして憂国の…



 2024年6月13日極論というものはえてして穏健な立場でありたい人を閉口させ退場させる。舌鋒鋭き主張の強さに、タジタジとなり、かなりの割合で耳を塞ぎ出しかねない。
2024年6月13日極論というものはえてして穏健な立場でありたい人を閉口させ退場させる。舌鋒鋭き主張の強さに、タジタジとなり、かなりの割合で耳を塞ぎ出しかねない。
それでいいとも思うのである。
しかし、HR等での話し合いが紛糾したような経験からすれば、議論百出の中に、自分と相容れない考えを持つ人の発言であっても、自分が気づけなかった気づきをもたらすことがある。耳を完全に塞いでいては得られない。実に様々な意見があり、硬直的ではないから成り立つ健康な議論形成。
本書は、私から見たら、走った感のある意見満載である。それでも、筆者が漫画に描かせ直してまで言いたいことの中には、それは私も同感である、というものが含まれている。
1種子法2種苗法3食糧安保4木の資源。林業保護。無作為伐採回避5巨大医薬業6放射能と原発対策7世界報道自由度ランキング8改憲論義は草案の条文一つ一つ個々見ること9子どもと薬害10有識者や学者は誰かの代弁者であることも考える、といった構成。
確かにその昔ジーンバンク構想があり、種子の管理は国家プロジェクト(世界的?)だった気がするから、危機意識は一面真っ当と思う。種苗も、5の医薬業と並び世界的巨大企業数社だけにいいように動かされているのは紛れもない。いずれの業界も、日本の企業は上位に食い込んではおらず、憂いは理解する。数十年前迄は穀物メジャーが世界を牛耳っていたことも、石油業界のセブンシスターズに通じるなんとも無力感を覚えさせられる欧米独壇場であった。しかし日本国内に於いてさえ米価コントロールの苦労、食管の財政赤字、過剰米や自主流通米問題と、長年悩み迷い過ごしてきた歴史がある。主食として食料自給率upに寄与していたが、誰もが、もちろん政治家が、いの一番に農業生産者を守る、これなくしては気候変動による食糧危機到来がもしあれば、日本の台所はもたない。食肉補助金問題は?。
が、輸入飼料に代え飼料用米の道は良い。ハウスの光熱費は石油輸入依存度の高い日本のアキレス腱、コスト削減の道があればと思う。
原発は発電コストのみならず後処理コストまでトータルでは寧ろ高くつくのはその通り。またこの辺り、日本では余り報道されなかった言及、流れとして自然ではある。7は17/27マスコミサイドにも真剣な当事者意識の必要なテーマ。
不動産投資、近隣国我が物顔だが、かの国自身は所有権を持たせず借地権というアンフェアは看過できない。 -
そう展開するのか、という独自性を感じる話




 2024年6月11日3作品収録。表題作「灰色の御花」94頁ぶ~け1978年10月号11月号、「夢追い人と桜の木」60頁りぼんデラックス1977年春号(4月)、「雪のひとひらに」31頁りぼん1976年2月号。表題作は戦争が人々にもたらしたものを戦後数年経ってもなかなか収まらない混乱期という時点で、サスペンス含みで。次の作品は「夢」と「桜」とを軸に、人の心の動きを描く。最後の作品は主人公の思惑はどうなっていくのか、というところを。
2024年6月11日3作品収録。表題作「灰色の御花」94頁ぶ~け1978年10月号11月号、「夢追い人と桜の木」60頁りぼんデラックス1977年春号(4月)、「雪のひとひらに」31頁りぼん1976年2月号。表題作は戦争が人々にもたらしたものを戦後数年経ってもなかなか収まらない混乱期という時点で、サスペンス含みで。次の作品は「夢」と「桜」とを軸に、人の心の動きを描く。最後の作品は主人公の思惑はどうなっていくのか、というところを。
「夢追い人と桜の木」の展開力は魅力的だった。フィクション特有の偶然も綺麗に織り込まれた。
「雪ひとひらに」は、多少ドラマを強く意識し過ぎた感はある。
どれも水樹先生の、言葉に対する細かくて芯を当てようとするような感覚が存在感を放つ。
それにしても、かつて愛した女性を長く忘れられない男性が、水樹先生作品にはホントに多いと思う。これはもう先生の思う理想の愛の在り方なのではと思っている。 -
初期4作品。敢えて毛色違いで広い領域見せ




 2024年6月10日いずれも70年代発表だが、僅か16頁の同時収録「冬ふうりん」に見られる日常のひとこま描写から、表題作の成り代わり物、水樹先生お得意のファンタジー入ってる「幻想銀河へ」、そして今でも漫画にもたまに扱われる心理学的素材のロマンチックコメディまで、実に多彩な初期作品集。「天女恋詩」61頁掲載誌りぼんデラックス(以下DX)1977年夏号。「幻想銀河へ」65頁りぼんDX1979年秋号。「クイニーと博士とetc.」50頁りぼんDX1977年秋号。「冬ふうりん」16頁りぼん1975年12月号。こちら初単行本化は1981年11月。
2024年6月10日いずれも70年代発表だが、僅か16頁の同時収録「冬ふうりん」に見られる日常のひとこま描写から、表題作の成り代わり物、水樹先生お得意のファンタジー入ってる「幻想銀河へ」、そして今でも漫画にもたまに扱われる心理学的素材のロマンチックコメディまで、実に多彩な初期作品集。「天女恋詩」61頁掲載誌りぼんデラックス(以下DX)1977年夏号。「幻想銀河へ」65頁りぼんDX1979年秋号。「クイニーと博士とetc.」50頁りぼんDX1977年秋号。「冬ふうりん」16頁りぼん1975年12月号。こちら初単行本化は1981年11月。
当時は普通に使われていた「ナウ」の用法が時代感。70/196 の虚空感の語は、そのときは違和感を持ちつつも作者独特の言葉表現かもと素通りしたが、116/196の虚空間に至って、いずれも虚空間にしたかったのでは?と思う。ともあれ「幻想銀河へ」は水樹先生の作風を感じる。「クイニーと~」はそれ使うのか、と感じた。70年代からの科学者が読む近未来への展望のテーマ羅列は、2024年の今見てなかなかだと感心してしまった。主人公の見抜きの力、恐るべし。 いずれの作品も随所に萩尾望都先生の影響を感じざるを得ない。相当慕ったのか、心酔に近いものを感じた。
「冬ふうりん」はこの僅かな頁で描かれた内容の豊富さに、水樹先生の技量が詰まっている。
昔の少女漫画は今ほどハピエンが多くなかったイメージがあるのだが、それを裏付けるかのように、ストーリーかキャラ造形の何処かに影がある。人が亡くなる、或いは過去に亡くなった、といった状況の織り込み。ただ、それを乗り越える望みもまた描かれる。そのため、人はそれぞれいろいろあるけれど、でも進もう、という感じ、かな。
水樹先生にはこういう作品群もあるんですよ、という詰め合わせ感覚で楽しませてもらった。 -
-
「エリオットひとりあそび」続編含む短編集




 2024年6月8日「City Birds」68頁掲載誌ぶ~けDELUXE(以外DX)1982年夏(9,10)号「典型的な悪友」63頁ぶ~け1984年3月号「雨あがり」31頁りぼん1976年4月号「オー・ボヘミアン!」32頁りぼん1976年8月号。
2024年6月8日「City Birds」68頁掲載誌ぶ~けDELUXE(以外DX)1982年夏(9,10)号「典型的な悪友」63頁ぶ~け1984年3月号「雨あがり」31頁りぼん1976年4月号「オー・ボヘミアン!」32頁りぼん1976年8月号。
単行本は1985/3/20に発行された。
終始軽快な感じで進行する話ばかりなので「エリオットひとりあそび」の続編だからといって、構える必要ナシ。
「都市も人も地球が見ていた夢の一部だったってことになるのかも」のところは、水樹先生のSF漫画を連想。かつて普通に若者は「ヤング」と呼ばれていたが、語を目にすると急に当時に引き戻される感じがする。言葉の選択、使い方にリズムやセンスがある作者だが、「パトス」には某アニメを連想。
表題作は、70年代アメリカの大学生の日常生活ぶりから入っていくが、展開は広がるし、「エリオットひとりあそび」に繋がる場面少しファンタジー匂わせか?となる。実は話としてはずっとあくまで現実を生きるエリオット、読み手は「まだ鳥?」という感覚も。
「雨あがり」は日本の家族物で、初期作品。
「オー・ボヘミアン!」も再び舞台はアメリカ。楽しく読める。 いいね
0件
いいね
0件 -
生きることが何処か苦しいあの頃の…




 2024年6月8日前後編2巻で計426頁。全て表題作。調査ではぶ~け1982年10月~83年3月号掲載の筈が、最終話の最終コマには、1970年2月25日との書き込みが。設定上のエンディングの日付と思われる。
2024年6月8日前後編2巻で計426頁。全て表題作。調査ではぶ~け1982年10月~83年3月号掲載の筈が、最終話の最終コマには、1970年2月25日との書き込みが。設定上のエンディングの日付と思われる。
ストーリーのほうは1969年アメリカの15歳の少年が主人公。こう来ると多いのが通過儀礼的な初恋…。大人ではないが子どもでもない年頃特有の感性を繊細に描く、というひとつの型は、フィクションでも読み手の遠い記憶や実体験を甘酸っぱく呼び覚ますので、又は、少年の心を垣間見させる女性側からの想像力を掻き立てるので、とてもニーズのあるジャンルと思う。主人公エリオットは、大人ぶるでもなく、実際冷めていて級友達より孤独や複雑な家庭問題を抱え、恋愛実経験値以外はちょっと大人。
舞台を米国に設定してあるのは、ベトナム戦争を扱うから。その他、ヒッピー文化や当時公開された映画幾つかにも触れて、物語の登場人物達は、誰かが誰かのことを好きという関係の中で、ベトナム戦争が影を落とす事からエリオット達も無邪気にはいられない。そういえば米国が舞台の古い少女漫画には、ベトナム戦争のことを扱うものは当時幾つか読んだことがあった。
その辺、若者の日常を黒塗りしかねない勢いで実に時代色を入れ込んでいる。
が、それと同時に、世の対照的ふわふわ少女漫画には無い苦悩もより強くて、表現されるポエム的なコマも、揺れる心情の中での深遠な自己問答。
リアルな人間を描こうとしたせいなのか、水樹先生お得意のファンタジーはほぼない。とはいえ不思議場面はほんの少しある。
踊りのシーンは素敵だ。登場するカメラマンならずとも見入ってしまいそうな絵だった。
脇役なのに、先生達のエピソードはインパクトがあった。しかしこれをエリオットに喋る関係性は、オープンなアメリカでもどうなのかとは思った。
ラウルのエピソードも、エリオットに少なからず影響を与えた大人として、胸にツンと来た。
さて、続編「典型的な悪友」に行こうと思う。 -
人類の脳が異常に巨大化したのは殺戮行為で




 2024年6月7日人類が核兵器他を戦争に何十万発と用いて、完膚なきまでに破滅的なところに追いやらんとする近未来的地球環境のその終末に対比させ、地球と似た環境を遙か昔に持ちながら別の事情により故郷の小惑星を捨てざるを得なかった異星人が、地球の命運を握る能力を持っているストーリー。水樹先生の描く終末観は人類滅亡の少し手前で、人々のストップの効かないさまや、科学の発達も好戦的な人類の暴走を抑えられない状況を示す。その異星人の目には、地球上の人類とは攻撃性が第一性格の危険な種族、と。
2024年6月7日人類が核兵器他を戦争に何十万発と用いて、完膚なきまでに破滅的なところに追いやらんとする近未来的地球環境のその終末に対比させ、地球と似た環境を遙か昔に持ちながら別の事情により故郷の小惑星を捨てざるを得なかった異星人が、地球の命運を握る能力を持っているストーリー。水樹先生の描く終末観は人類滅亡の少し手前で、人々のストップの効かないさまや、科学の発達も好戦的な人類の暴走を抑えられない状況を示す。その異星人の目には、地球上の人類とは攻撃性が第一性格の危険な種族、と。
現代でも世界各地で起こる攻撃の報道、爆撃を受けて破壊された建物など見れば、否定は出来ないーー。
主人公と、プラズマとあだ名がつけられた超人の彼、また、遠い過去に故郷の星から早々に切れてしまってた形の男の子。3人の気づきの時(覚醒の、というべきか、プラズマとの接触によって思い出す)は大きく異なる。彼等は故郷の星を脱出せざるを得なかったとき、長い年月を掛けて、地球人自ら星をダメにする寸前の好機を狙いすましていた。
しかし元は異星人といえど、その故郷への想いの継承とは別に、潜伏の長い年月の間に地球での人間関係もあったりして簡単に彼等の星にしてしまえなくなり…。
非常に遠巻きの反戦メッセージがありながら、そこまで突き進んでいくことを止められない(敵を攻撃するスイッチ(ボタン)はもはや地球規模の破壊力なのに)人類が、外の惑星の人たち(ヒューマノイド型なので)に命運を握られる。ぶ~け誌掲載だが相当ハード展開。1981年4-9月号。前後編で、表題作は318(187+131)頁。後編にはグッとくだけた「苦麗児プロポーズ」40頁(りぼんデラックス誌1978年4月(春)号)と、水樹先生の叔父様という詩人の二編の詩とそれぞれのイラストとを各2頁同時収録。
クレアボワイヤンスの活字がクレアボワイカンスとなってしまっていた。またそもそも古い書の電書化にありがちな活字に付されたルビの潰れが多くて、そこは読み辛かった。魂(アニマ)、予知能力者(プレコグニショナー)などそう読んで正しかったのか分からない。
作品発表当時のSF漫画(「月虹ーセレスの還元ー」少女漫画王道の掲載誌であることも)の世界の広がりに驚くが、それでも、水樹先生は異色のファンタジーを紡いでくださっていたのだろうという気もする。
*「セレス」は星の名前。 -
おもしろ~い!先生のファンなら必読では?




 2024年6月6日私はシーモアさんの読み放題にあった「イティ・ハーザ」で水樹和佳(子)先生を初めて知った新参者です。そのときスケールに驚愕した気持ちが忘れられずチャンスがあればまた先生の作品を読んでいこうと思っています。
2024年6月6日私はシーモアさんの読み放題にあった「イティ・ハーザ」で水樹和佳(子)先生を初めて知った新参者です。そのときスケールに驚愕した気持ちが忘れられずチャンスがあればまた先生の作品を読んでいこうと思っています。
水樹先生ファンなら本作も気に入ってる作品だろうし、恐らくイティハーザと並び立つ代表作として遇されているのでは?
先に読んだ「グレイッシュメロディ」(全1巻)は179頁。
本巻はやはり1巻完結なるも426頁と長め。SF漫画作品集。これは詰め合わせにありがちなピンキリではなく、どれも楽しめました。絵はカッチリ描かれて、宇宙空間の黒が美しいです。但し、当時のものなので活字は見えにくいところも。
「ケシの咲く惑星」71頁。ぶ~け1986年12月号。
「月子の不思議」133頁。ぶ~けせれくしょん1985年。
「樹魔」65頁。ぶ~け1979年12月号。
「伝説ー未来形ー」121頁。ぶ~け1980年5,6月号。発表当時はタイトルは「伝説」?。第12回星雲賞コミック部門(1981年)。
「墓碑銘二00七年」34頁。SF JAPAN 2000 年MILLENNIUM:00 日本SF大賞20周年記念号(徳間書店2000年4月)
尚、タイトルがそうあるように、「樹魔」と「伝説ー未来形ー」はシリーズ物となっています。
本日は米国の新有人飛行船がISSにドッキングのニュースがありましたので、いいタイミングで本書を読みました。無人探査ももちろん素晴らしいミッションをしてくるので感動してますが、「有人」飛行を前提とした宇宙を考えていたその時代に、作者独特の想像を膨らまして描かれたSF作品を読んでみると、宇宙を現実を超越した所謂宗教的な側面のコスモス観として持っていて、その見方に、作品としての輝きや作品空間のスケールを魅力的に押し広げた感じがします。
避難するように苦しみから脱出し流浪する心、地球外で生まれた子、未来的なスマートな衣住環境、終末的な出来事を経た後の明るさばかりではない未来社会、進化というもの等々、それぞれ示唆に富んだ話で楽しませてくれました。(一部ハードエンディング) -
心霊現象出てくるが不気味でなくカラリと




 2024年6月1日枝垂れ桜と幽霊の絵がよい。枝振りがそのテの組み合わせ定番の、まるでしだれ柳のように思ったが。
2024年6月1日枝垂れ桜と幽霊の絵がよい。枝振りがそのテの組み合わせ定番の、まるでしだれ柳のように思ったが。
後で、その桜が花を咲かせる絵が出てくる。そこに居る男性の後ろ姿に、後半までずっと謎だった彼の職が活かされてる。その締め方が巧み。
主人公の男の子は父親に対して微妙に入り込みすぎない距離感を、持っている。父親も、自分のことをあからさまにはしていない。その二人が共通の巻き込まれ事件みたいなものを片付ける。その過程で、二人の間にあったスッキリしなかったもののベールも剥がれていく、という次第。
かなりエピソードにこまごまぶっ込み要素があったのにうるさくない。取捨選択されたセリフやスルスルとした話の進み具合によるのだろう。
家族の形態とか、なさぬ仲に於ける家族愛など、人間の情を重すぎず温かく捉えていて、味がある。
水樹先生はもう久しく漫画を描かれていないといわれているが、こうした手さばきの良さを見せつけられるにつけ、また戻って欲しい気持ちになる。
尚、作品中に出てくる結婚式場、私も式を挙げたところなので驚いたし、少し懐かしかった。
169頁。「メロディ」誌2005年2月号、3月号、8月号、9月号掲載。 -
静かな日常。そーっと見つめる感じで終わる




 2024年5月30日全然悪くない。寧ろ読後感がいい。続けてBL読んできてこれもレビュー書いとこうと思った。
2024年5月30日全然悪くない。寧ろ読後感がいい。続けてBL読んできてこれもレビュー書いとこうと思った。
序盤のほうに、え?と思わせる思わせぶりシーンがあって警戒した。しかし穏やかで、それでいて少しの後ろめたさを関係性に負わせている展開の中では、主人公独特の翻弄の仕方であると認識。
告白してきた相手を見つめることにより、いつの間にか引き込まれていくのは、この話に付き合わされて読み進める読み手も同じ。その誘い込み方が、小さなエピソードのサラリとした存在感で徐々にはまる様になってる。ピアノのシーンの引き込まれ方など、私も2人の世界に立ち会ったようだった。あとがきによれば、下敷きにしたリストのそのピアノ曲に存在しない和音を描きたくないから譜面を確認、とある。そのこだわりはくらもちふさこ先生を連想した。
虚構の世界にあるリアリティ、まさしく、主人公が震えて聴いたものはそこにあったのだと思わせる、作家の価値観に共感する。
シーモア(島)という利用者コミュニティに、本作の紹介があったことに感謝。 -
-
勝てなかった思いがいっぱいある




 2024年5月26日勝ち負けなどではないのだけれど、そういうどうにもならない感情のあれこれ。時間もあるし、見た目では測れない相性もあるし、理屈では割り切れないものがある。
2024年5月26日勝ち負けなどではないのだけれど、そういうどうにもならない感情のあれこれ。時間もあるし、見た目では測れない相性もあるし、理屈では割り切れないものがある。
しかしだ。咲子の気づきや選択は、私には急転回に感じてしまった。想い続けてそして追いかけることにした人へのフォローのような決め方に、もう少し納得のいく描写も欲しかった。やはり思わせぶりに進行してきて、ここでそっちなのか、という小さな小さな裏切られ感。
全4巻。第1巻表紙が子どもっぽく、実際小学生のくーちゃんを使って物語を回すことが多かったから仕方がないが、そこが本作品の読み手を狭めてしまったかも。
月刊プリンセスが元の掲載誌。
第1巻昭和52年(1978)5-8月号計4話、第2巻同9月-昭和53年(1979)2月号計6話、第3巻同3-8月号計6話、第4巻同9月-昭和54年(1979)2月号計6話、総計22話。読み切り連載のような、そして、少しずつ人間関係が進んでいくような、くーちゃんとお花屋さんの咲子さんと、そのまわりの人々の日々。
第2巻で秋の七草の名前で、オミナエシのところをオカエシとなってしまっているのは、作品の性質上で最もない方がいい誤植、校正で気づくべきだった箇所かと思われる。
可愛らしい絵と、話のふんわりはとても合っているから、少し感情のもつれがキャラ間に現れてもおさまっていくところには安心する。
そうは簡単にはいかないものだろうというようなことでも、キャラ達が動き回ったり、あれこれ考えたり、その中に優しさがある。
ポエムっぽいコマの出現もこの作品の一貫性を見せるようで合っている。花詩集のタイトル通り。
一方、その分現実感は少なくなった。
各話のタイトルに花の名がつけられていることから、昨年のTVドラマ「らんまん」を思い出したが、出現する新人物にストーリーを捻り出して「花詩集」を編み込んだ点、少々の強引さはあった。三四朗の母の出方も唐突感があった。 -
宇宙人の話と浪人生の話。絵の可愛さが好み




 2024年5月22日全5巻。表題作851頁で、第5巻には「ロマンチックな火星人」50頁と「青い鳥おっかけて」50頁が同時収録。
2024年5月22日全5巻。表題作851頁で、第5巻には「ロマンチックな火星人」50頁と「青い鳥おっかけて」50頁が同時収録。
【新装版】というだけあって、カラー巻頭頁だとかイラストレーションも収録されており、表紙の色味の方と本編の後に掲載の色味と異なるものも。恐らく印刷技術の発展で、原画に近い発色が可能になったのかと想像。
岩館真理子先生を思い出す、実に私好みの可愛らしい絵全開で、手抜き感ゼロ、且つ夢の中を見せているようなメルヘンチックさでラブリーな存在のキャラ達。悪者ポジションも悪意というよりは「小」憎らしさで毒が強くない。しかもストーリーもほんわかしていて、主人公は割と動いてはいるのだけれど見た目ちょこまかしていて、慌てようと怒ろうと可愛らしい。
表題作は宇宙人と幼馴染みとの三角(?)関係の話。ひとみ誌1982年2-8月号の何処か~1984年3月号掲載が初出らしい。フェニックスの場面が良かった。やりとりを省いて結果のみ匂わした2箇所、突如ゴロッとした感じがしたが消化させるしかなかった。
「ロマンチックな火星人」プリンセス誌1979年4月号、一樹クンのお嫁さんになることが夢の、主人公の彼との距離感の悩みなど。シャンソン歌手フランソワーズ・アルディさんの名前が、「アルティ」になってる箇所がある。主人公の心を乱す存在の正体不明さを描いているが、彼自身を主人公の目から見せるので、彼のことは行動で読み取ることに。
「青い鳥おっかけて」はプリンセス誌1983年11月号初出とのこと。浪人生のことを題材にするのは、少女漫画では「おしゃべり階段」(くらもちふさこ先生)くらいしか記憶になく、まして今や現実にも浪人生超激減時代、読んでいてとても新鮮だった。せがわ先生の大学時代に身の回りには多くおられたと想像。
その立場ならではの孤独感や焦りなども伝わってくるし、時間が無いと感じながらも手が回らない美容や日頃通過してるだけの場所をゆっくり味わう散歩など、主人公の日々が少し潤うのが、読み手の私も心和んだ。便利屋という存在の使われ方はなんとなく既視感あるも、関わり方の、漫画ならではの近さとか、少女漫画っぽい展開が当方の期待感をくすぐられて良かった。 -
喫茶店、女性の自立、養蜂家の子のこと




 2024年5月20日表題作は週少コミ1977年5月8/15号,5/22,5/29号初出。70年代は捨て子の話も世の中あるにはあったし、日常着が和服姿の女性もまだ時々居た。今と比べると個人的事情に人にずかずか入って来られることは比較的あった。そんな古い濃い時代の町の小さな喫茶店コミュニティと、そばに資本にモノ言わせた規模の大きめ喫茶店に進出された生存戦略の話。主人公が姉の居る都会に出て来て多々感じることなど。前半に見せる子どもっぽさが気になった。118頁。
2024年5月20日表題作は週少コミ1977年5月8/15号,5/22,5/29号初出。70年代は捨て子の話も世の中あるにはあったし、日常着が和服姿の女性もまだ時々居た。今と比べると個人的事情に人にずかずか入って来られることは比較的あった。そんな古い濃い時代の町の小さな喫茶店コミュニティと、そばに資本にモノ言わせた規模の大きめ喫茶店に進出された生存戦略の話。主人公が姉の居る都会に出て来て多々感じることなど。前半に見せる子どもっぽさが気になった。118頁。
同時収録の「サヨナラさしすせそ」50頁は、現代からは想像もつかないような今なら当たり前の男女平等の在り方が、その当時の古い男女観の下、女権拡張論者は過激だとの見方がなされている時期のストーリー。実は…というところに笑いを作り出している。この作品が、私には、あの頃の世相を踏まえて一番可笑しかった。軽快にぶっ飛んでいて、逆にノスタルジック!?。同誌76年2月1日号初出。
同収「蜂っ子菜っちゃん」32頁は掲載時期場所情報不明。小学生を購読層に描いたと思われる。
今から何十年か前の作品を、未読のまま大人になって現代の視点で読んでしまうと、何かともどかしいような、じれるような気分になったりもする。
びっくりしたり、また、横暴な印象を持つこともある。
しかしこの、今と隔絶した感覚は紛れもなくその漫画を取り巻いていた当時の空気。リアルタイムで読んではいないが、そのときの読者は、ほっこりしたりじんと来たり笑い飛ばして、支持していた。
灘しげみ先生といえばスポーツ少女漫画、という定評だが、こうした(学園)生活作品、他にはSF作品も手掛けて(「時のかなたに」等)おられた事を確認した。スポーツ物での極限まで肉体を苛める主人公達が、今度は(別人だが)舞台を日常に持ってきても、やはりエネルギッシュで何かを頑張る姿は読んでいて頼もしかった。 いいね
0件
いいね
0件 -
パートナーに出会うテニス物とスキー物




 2024年5月19日結構楽に上手く行く話と、挫折や挑戦の恐怖を克服する話の2話構成。表題作136頁、「雪原の夜明け」50頁。
2024年5月19日結構楽に上手く行く話と、挫折や挑戦の恐怖を克服する話の2話構成。表題作136頁、「雪原の夜明け」50頁。
テニスを始めた動機が不純な主人公が、辛すぎない悲壮感の無い練習メニューで、テニス上級者の手で短期で安易にレベルアップ出来てしまう為、上手くいきすぎな話にリアリティを期待することは間違いだとわかる。特に主人公の言動に好感を持ちにくいシーンが冒頭続く。スポ根物にある厳しくて過酷な練習は無縁。明るく楽しく、恋もテニスの腕も望んで何でも手に入るかのおいしい目にあう。
「雪原の夜明け」は恐怖心を克服する話。こちらは事故でスキー競技から一度は離脱した男性主人公が、ある日知り合った女の子とのやりとりを通じて、お互いが怖がっていた物からそれぞれが向き合うことになるストーリー。発表の当時は題材や展開には新味があったのかもしれないが、既視感拭えぬ感じ。1980年2月開催のレークプラシッド五輪の出場がかかる代表選考の競技大会が描かれる。単行本化は同年だが、初版は7月1日とのこと、五輪後半年経っている。
直前読んだ「栄光のストローク」もだが、この「逆転のラブ・スマッシュ」の巻にも誤字散見。残念。
王子様幻想、大人の恋への憧れ、等を砕くストーリーは今やそこそこ世に出ていると思う。今どきのご時世ならばもっと男性はしたでに、丁重に女性を扱うだろう。
子どもっぽい独り善がりで序盤気が回らない欠点を見せ続ける主人公ではあるが、そんな、ただ恋に憧れるだけだった女の子が、いろいろなことを考えられるようになっていくのは、話としての収束感纏まり感から好ましい。作品名の意味の種明かしがあった後は、そうかダブル主人公だったのか、と思い返した。 -
泳法を変えたりして成長するスイマーの活躍




 2024年5月19日泳法は二度進化を遂げる。更に作品内では、ターンを新たに開発して、もうひとつの主人公の必勝技に。その時代は、身体の使い方の地味な工夫などの小手先の域を軽々超えて、何種類もの非現実的ターンを編み出すようなTVドラマがあったこともあり、、考えられない無茶なやり方で本作品も主人公が新しい手法に進んでいく。当時は、超人的な技術による、野球でいうところの魔球みたいのが多々。
2024年5月19日泳法は二度進化を遂げる。更に作品内では、ターンを新たに開発して、もうひとつの主人公の必勝技に。その時代は、身体の使い方の地味な工夫などの小手先の域を軽々超えて、何種類もの非現実的ターンを編み出すようなTVドラマがあったこともあり、、考えられない無茶なやり方で本作品も主人公が新しい手法に進んでいく。当時は、超人的な技術による、野球でいうところの魔球みたいのが多々。
そこがストーリー作り面で安易に感じられてならない。
主人公は中学生なのだが、切ない片想いなどよりも順調にして堅固な想い想われでほぼ安定。当時の中学生は現実はおませではなかったと思料、恋愛初期にその辺に悩まされ過ぎないこのストーリー、あくまで水泳選手の水泳人生がメインなのだ。もちろん、誰が誰を好き、といった要素は描かれる。しかし、あくまで、幾つかある主人公の集中力を揺さぶるエピソードの中で、恋愛感情によっても乱されたことはあります、といった程度。
新たな技術をものにするための特訓がまた当時スポ根あるあるの激しさ。荒唐無稽といってもいい。
資質、才能を見出されて、ハイレベルの環境で這い上がる迄は作者の他の作品と構造的に類似。
ライバルが仲間となったり、やり過ぎの策士が離脱していく。発端となる事件や背景の憎悪みたいなものも、昔の漫画では珍しくはないだろう。しかしそれもまた、新技同様リアリティが遠のいている。そこをお話だから楽しんでしまえば…難しさもある。
全3巻。201,203,205頁で、総計609頁。作品から、昭和48(1973)年週刊少コミ誌発表(6/17~12/23号)らしいが、これもやはり単行本化は遅くなって昭和54(1977)年初版と。本作品もモントリオール五輪に合わせた時期の物なのに、単行本化タイミングは合っていない。当時は漫画というものが読み捨てメインだったという残念な現象を如実に物語る。
ストーリーは勢いがあって、不幸な事故や人を陥れる策略や病になってしまったケースなど、いろいろな登場人物達が賑やかに出入りして盛り上げる。それにしても当時のアマチュア至上主義的な部分が罪作り。
13歳の主人公、更に身長は高くない設定、ターンや泳法のレベルアップなどは、彼女の弱点克服ツールと思って寛容に受けとめたとしても、ストーリーの波瀾万丈さが少しだけ作りすぎ感が目に余った。
しかし楽しんでしまえば、どうなっていくのかとの好奇心で導かれて楽しく読み終える。 -
ヒューマン色も入るスポーツ少女漫画集




 2024年5月19日表題作はバスケ物505頁。3巻目に体操物「雨あがりのライバル」41頁(別コミ73/6月号)、アイススケート物51頁「燃えるライバル(ちゃお75/12/10号)。バスケ部経験者としては兎とび以外の練習メニューが懐かしく、ジャッジ厳しめ運用の当時の反則場面とか、30秒ルールの瀬戸際の雰囲気とか、よく表されてると感じた。
2024年5月19日表題作はバスケ物505頁。3巻目に体操物「雨あがりのライバル」41頁(別コミ73/6月号)、アイススケート物51頁「燃えるライバル(ちゃお75/12/10号)。バスケ部経験者としては兎とび以外の練習メニューが懐かしく、ジャッジ厳しめ運用の当時の反則場面とか、30秒ルールの瀬戸際の雰囲気とか、よく表されてると感じた。
ただ、運動音痴が贖罪意識からという動機が主人公美鹿を持続させるのは相当の困難さを思う。中学なら、あの当時ミニバス経験者よりも初心者から入る者が多かったろうが、バスケ名門校に高校からは現実的ではない。そこをお話だからと割り切ると、美鹿の強い意思はドラマを動かす力となる。不幸な事故を取り巻く人間模様の感情のやりとりと、バスケというスポーツへの作者の理解度には却って舌を巻いた。スポーツ少女漫画を描く事にかけては、他にこの作品直前に既読のテニス物も相応の知識を下敷きにしたことが判っていたから、バスケットボールのほうもここまで?、という意味だ。もっとも、フリースローはその昔私達は、それは他人に邪魔されない性質上100%目指すべきシュートとして扱われたため、意外感あり。
贖罪だけではもたない競技継続への美鹿の心境変化描写も良かった。
1976年モントリオール五輪で女子バスケが正式種目に採用されたことを受けての、恐らく相当時宜にかなったその着眼が、ストーリー的にも確かに内容を伴っていたことは高い評価に値する。因みに現実男バスは1936年正式種目化の後1976年に出場、今年2024パリ五輪が44年ぶり出場。一方女バスは1976,96,2004,16,21(=20),24年と6度出場を誇り、東京2020では銀メダル。「栄光への出発」単行本化は初版で1977年らしい。当時の日本国内での認知度upに繋がらなかったし、単行本化が遅い出版事情(週少コミ連載のほうは5/3~11/7号でタイムリーだったのに)がなんともさびしい。
体操物のほうは、ライバルであり競技仲間でもある身近な人物との関係にスポットを当てた、走れメロスではないけれど人間が試されるように展開。
ここまで2作共に、当人の図らずも築き上げた競技以外の要素を活用する、キャリアの浅い主人公の話。
「燃えるライバル」は今と異なり当時ならではの、含有を知らずして服用してしまった意図せざる不幸なドーピング問題に触れていて、そこも目を引く。クライマックスの事件はこのテにはありがちエピなのだが盛り込み方巧み。 -
スポーツ少女漫画のルーツ的な存在




 2024年5月19日熱い。魔球が出てくる。奇妙な特訓がある。そこには理屈は一応ちゃんとある。ライバルの存在が居る。
2024年5月19日熱い。魔球が出てくる。奇妙な特訓がある。そこには理屈は一応ちゃんとある。ライバルの存在が居る。
縦ロールのロングヘアの後頭部をリボンで飾ったお嬢さまが登場、華麗なるプレイのその背中には蝶々の羽が描かれる。そして、突如彼女の前に出現した主人公の実力を認め、白目で「おそろしい人」と言うシーンがある。
後年の有名作品の幾つかを髣髴とさせる。
根性論も出てくる。蛋白質は摂りましょうとは思う。寺のお堂で養う精神統一の場面などは、どうしたって本作が元祖。
そう、灘先生作品は恐らく当時の(リアルタイムの読者ではない私にとって)スポーツ少女漫画の中では、格段にパワフルで先駆的な位置取りしていたと思わせる印象的な漫画。だからしっかりと読めるチャンスが此処にあることを、本当に嬉しく感じる。
全3巻。第1巻では守りと攻め、球のバウンド、第2巻にかけて球の回転や、縦方向と横方向の戦略、第3巻辺りではパワーテニスという新時代の主力選手としての歩みが具体化していくことなど。
そして主人公がソフトボールのキャリアを全編で活かし、ラケットの持ち手をスイッチしたり両手打ちをしたりなど繋げていて、趣向を凝らしている。
それにまた、テニスウェアはもちろん、コート外での服も可愛い。
もちろん時代性を感じない訳にはいかない全体の漫画の作りはある。それはしょうがない。漫画が貸本屋さんを主戦場とした時期からの作家であるのだから。
アマチュアリズムとプロフェッショナリズムとの相克など、今やボーダーが低くなったところにこだわりがあったり、テニスの協会や大スポンサーが存在したり。学校のクラブ活動としての矜恃、或いはテニス部に反感を持つ教師の存在など、内容が盛り沢山。
しかしその根底には、成長を続ける主人公の主体的で未来志向の明るさと、前途洋々の若さがあり、読んでいて時代の空気も吸いながら楽しめる。
コマの使い方に、試合途中の緊迫や、跳ぶ球のスピード感、選手の懸命な執着心なども窺える描き方がなされていて、のちの有名作品をインスパイアしたと思える箇所が多い。すごい存在感のあるスポ根作品。ロマンスは添え物として少しの比重。
調べたところ、単行本としては、元は昭和50年(1975)年に初版された物。1974/2/17号~10/27?号週刊少女コミック誌に連載されたのが初出。 -
りぼん誌の大人っぽい漫画集




 2024年5月14日とある情報で、りぼん誌の別冊付録だった、という作品を読みに来た。
2024年5月14日とある情報で、りぼん誌の別冊付録だった、という作品を読みに来た。
今まず第2巻。「雨のにおいのする街」128頁1972年8月号、「摩耶の葬列」同年7月号128頁。
発表当時のことを考えると、なんて凄い漫画家だろうと思う。「時代がかった村、ここだけ時間が止まったような村」など、成る程引き込んでくる。
出逢いの力に抗えない二人のSF的な作品だとか、サスペンスを混ぜながら同性愛を題材にした作品だとか、その果敢にして攻め姿勢を貫く創作力に脱帽。
この総頁数に、2編しっかりと入ってることが信じられない。頁数稼ぎの無駄遣いな脇道逸れのエピソードがない。既に確立された一条ゆかり先生の絵柄の雰囲気ぷんぷんの一方、当時の大衆生活臭がない、先生の構築されたある種の特殊な環境描写の説得力、読み進めるうちに主人公達の置かれたポジションの微妙さがどんどん伝わる。
次は第1巻の予定。楽しみだ。
第1巻読了。「春は弥生」1972年4月号、「おとうと」同年6月号。この分量なら今なら普通に短編集の感覚なのに「長編」で通る内容だから恐れ入る。「春は弥生」は主人公は一体何処に行ってしまうのか、を読み手として振り回されながら当て馬の彼を気の毒に思った。「おとうと」は、“ザ・一条ゆかりの世界”を見せつけられて、こちらの当て馬にも思うところ頻り。
後は第3巻。翌15日追記。
第3巻は、「9月のポピィ」1972年9月号、「クリスチーナの青い空」同年5月号。3巻全てが1作品128頁だった訳だ。ご多忙の時期にこれだけ続々作品を作り出した旺盛な創作力、同じ年の発表作品を検索すると「恋はお手やわらかに」、「さらばジャニス」、「セントメリーの牧師さま」(「雨あがり」に収録)と量に驚かされる。しかし中表紙に月間スケジュールなるものが描かれ、かなりのオフを入れているように見えてもっと驚かされる。
「9月のポピィ」は初恋の人の話。「クリスチーナの青い空」は戦争が遠くなっていた日本の読者に戦争というものを伝えようとした意思を感じる話。後者は重い。こういうものもちゃんと入れてくるところに気骨を感じさせる。ただの甘いロマンス作家でいるわけではないと。
第1巻から第3巻までの全6作が、「一条ゆかり全集」と銘打って刊行されたらしい。幅広い領域を硬軟混ぜて描ききった、活躍ぶりが窺える『全集』。
高校1年でデビューされて第一線の少女漫画家でらした先生の、初期の勢い余るお力に圧倒された。 -
人の役に立つということとはなんなのか




 2024年5月10日「ジークの左手」の寓話性を思うに本作は、ジークあれからどうした?との読み手の好奇心に応えた意味以上に、あの時蒔かれた種のひとつの彼の存在意義、というアンサー漫画みたいな感触があった。話は黒くて暗いのに、画面が白くて希望を明るく持ちたいファンタジー、そんな前作から、今回はまだまだ引き摺るかのように冒頭から、場面の白っぽさとは皮肉なくらいに対照的な後ろ暗い主人公登場で、なかなかに気分が重い。少女も如何にも薄幸風吹かしていて救われない話かもと身構える。
2024年5月10日「ジークの左手」の寓話性を思うに本作は、ジークあれからどうした?との読み手の好奇心に応えた意味以上に、あの時蒔かれた種のひとつの彼の存在意義、というアンサー漫画みたいな感触があった。話は黒くて暗いのに、画面が白くて希望を明るく持ちたいファンタジー、そんな前作から、今回はまだまだ引き摺るかのように冒頭から、場面の白っぽさとは皮肉なくらいに対照的な後ろ暗い主人公登場で、なかなかに気分が重い。少女も如何にも薄幸風吹かしていて救われない話かもと身構える。
しかし彼は客として接触しに行った母子に大層喜ばれるという「善行」を見せる。ここが「ジークの左手」に連なるところであり、本作の大きな転回部。
この腕(能力)こそが彼がその業とするものの持つ後ろ暗さであり、同時にひとさまから求められる一種の奇跡の光。前作は功罪の内の「罪」部分強調してた。
本作は彼は生きるためにおこなっている側面を示していることから、彼の損得勘定を根拠にその腕に関して少女に(読み手にも)安易な期待を抱かせない。
しかし救いのある話に仕上がっている。
描線に何処にも劇画タッチがないために、リアリティを見せない絵本仕立てではあるが、その世界で得られた彼女(少女)の居心地は、読み手のこちらにも読後居心地良くさせてくれる。
前作の強烈な恐ろしさや不条理、奇妙に強引な寓意が、本作は引っ込み、緊張絶えない前作にはあまり味わえなかった静かなスローな感じ、この頁数でも持つ落ち着きが冒頭の彼の行動の不可解さのそばにもずっとある。
衝撃は前作に、含みを残しつつ着地を一旦本作で、という印象だ。 -
ふわふわキュートな恋愛状態楽しい年の差物




 2024年5月10日花田先生作品は二作目。本作もTL分類はやはり変。少女漫画よりも少女漫画しています。
2024年5月10日花田先生作品は二作目。本作もTL分類はやはり変。少女漫画よりも少女漫画しています。
好きな気持ちだけでガーッと突っ走れない大人が、恐る恐る未踏の領域へ、年下の彼によって心を持ってかれる話。
歳を重ねていても、必ずしも恋愛経験豊富とは言えない、そんなところが二人の関係を簡単に発展させない穏やかな(慎重な)滑り出し。彼も悪いところがないために、お姉さま相手にずるいところ無く奮闘していて、なんだか読み手のほうが心洗われます。
大きなトラブルだとか粘着性鞘当ても無く、サラリと少しずつ前に進む、それが物足りない人も居るかもしれません。しかしそこが優しいふんわりラブストーリーを望んで読んだ私の心には、ジワリ来ました。
ピアノ、バー、店の客からの相手のもて方等々、少々細工が多い展開だとは思いましたが、出会いから二人が育てていく関係を大切に描いた、という意味では素敵な味付けとみてもいいと思います。
遼平さんのお友達のご両親のこと、ストーリー中あっさりだったので、抵抗感や問題とするほどでなかったかどうか、など読み切れずしまい。
一軒家設定はかなりすごいなとは思ったものの、二人が二人でいる雰囲気を表すいい背景かもと、逆に使える感じが新鮮でした。
彼の家庭環境について、少しも要素として必要な気がしなかったところ、私が一時期固め読みしていたハーレクインによくあるイージーさを思い出してしまい、彼の人間を示す別要素を出して勝負する話であって欲しかったな、と思いました。
 ERR_MNG
ERR_MNG
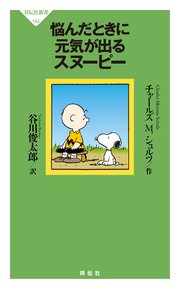
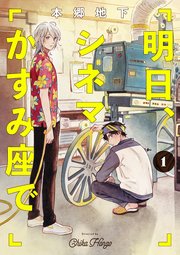
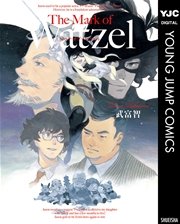
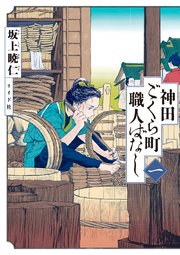
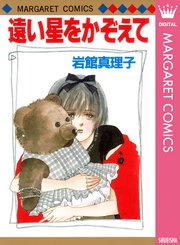

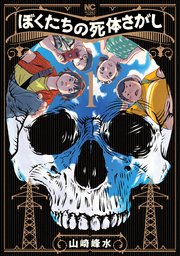

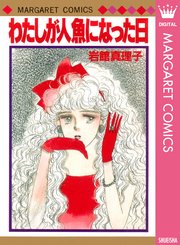
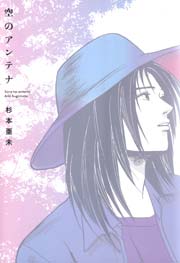
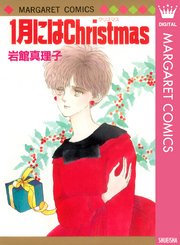
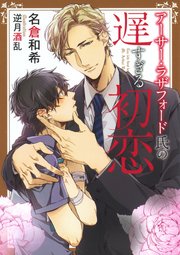
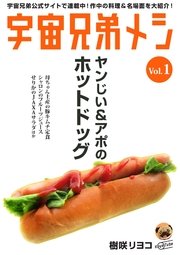
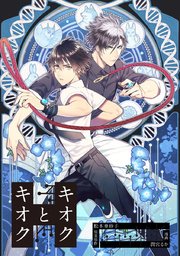
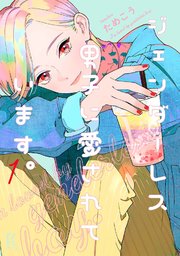
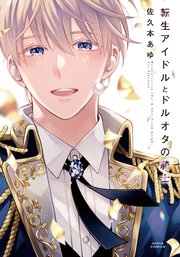
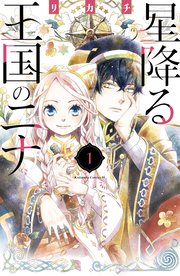
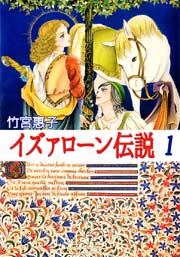

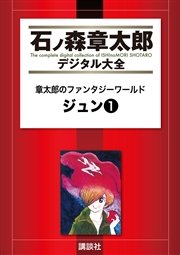
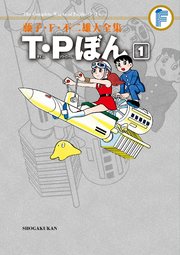
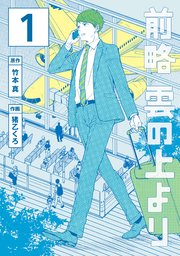
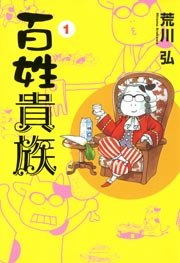
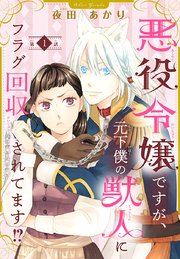

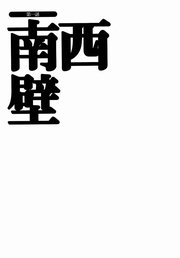
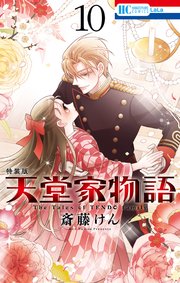
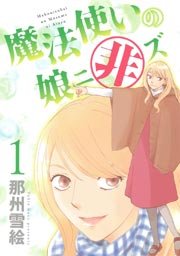
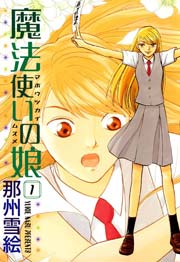


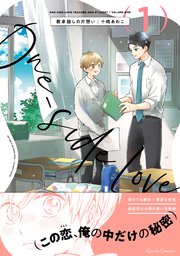
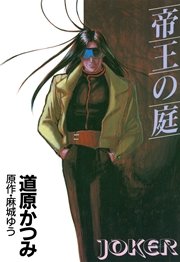
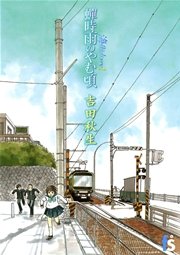

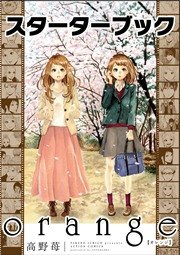
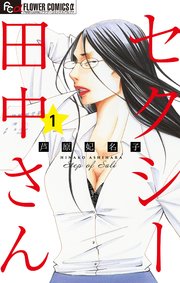
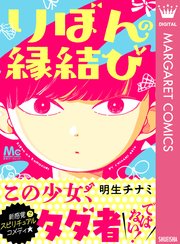

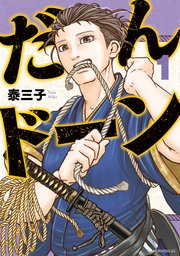
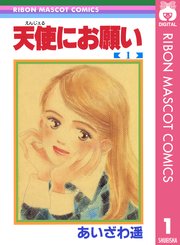
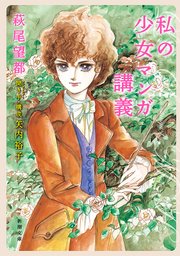
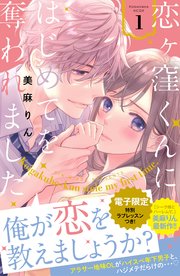
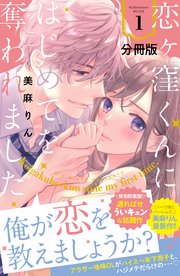
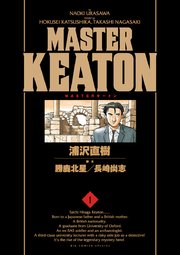

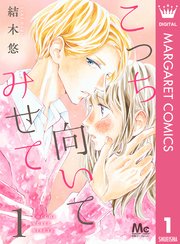


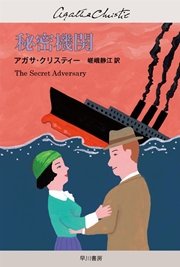
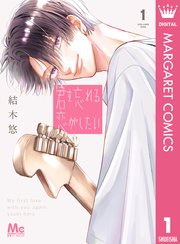
![完全に犯罪[1話売り]](http://cmoa.akamaized.net/data/image/title/title_0000232645/VOLUME/100002326450001.jpg)
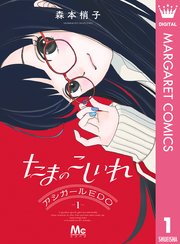
![長浜To Be,or Not To Be[コミックス版]](http://cmoa.akamaized.net/data/image/title/title_0000285467/VOLUME/100002854670001.jpg)